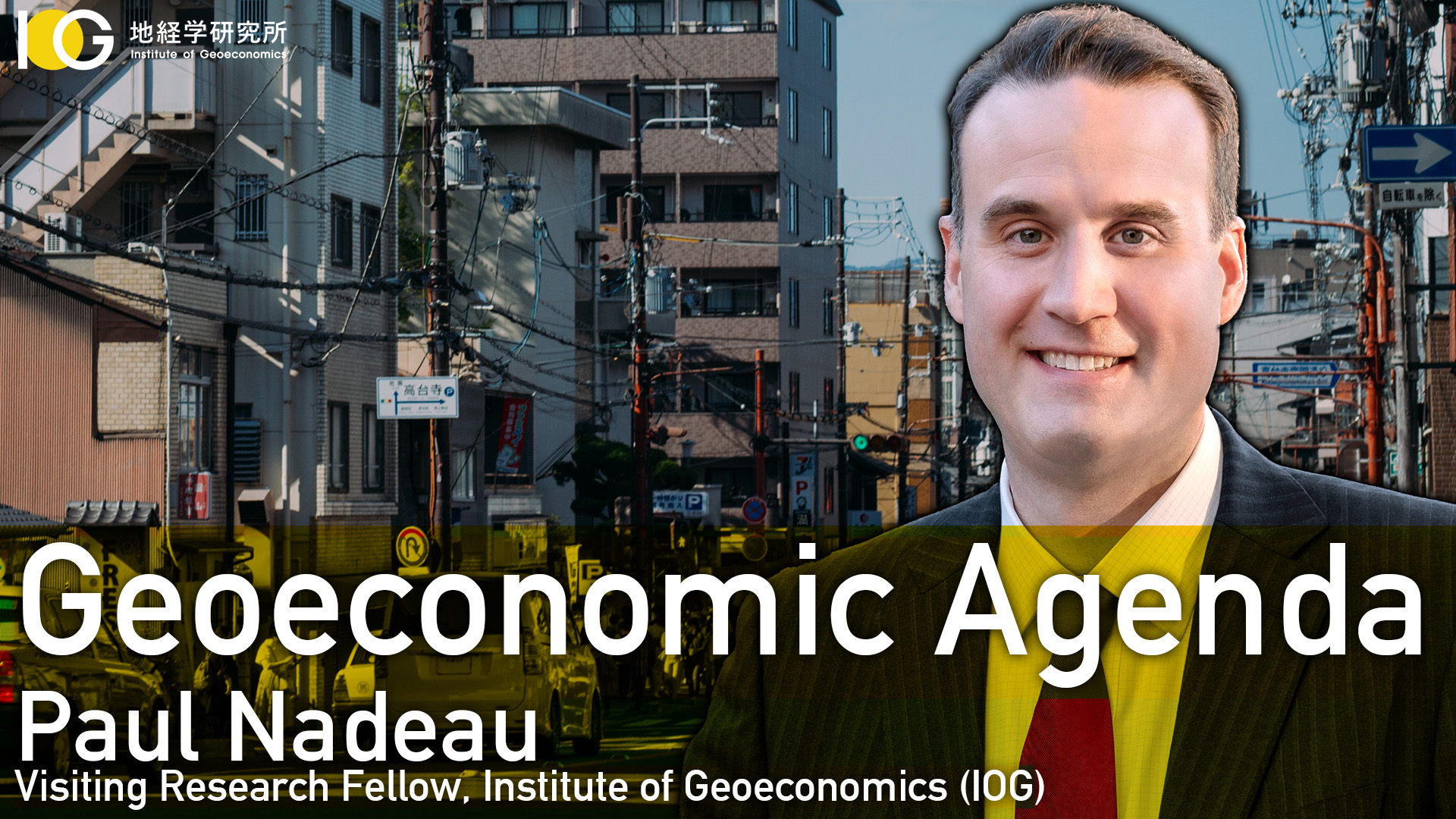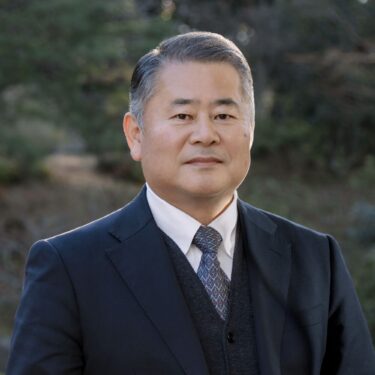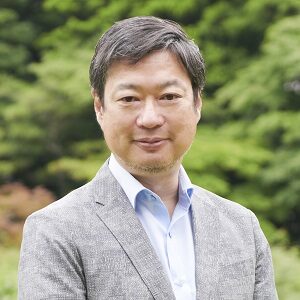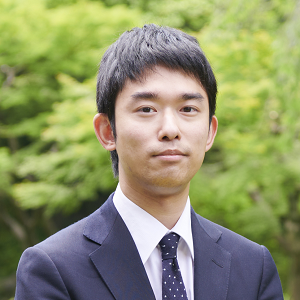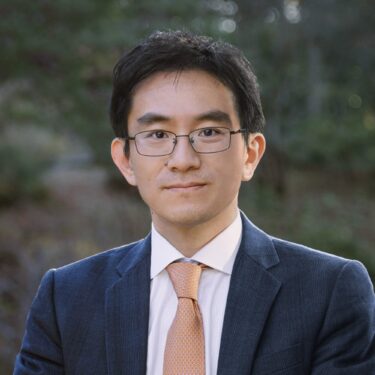2024/07/20  【参加募集】IOG地経学オンラインサロン「欧州選挙をめぐる地経学」を開催します(8月3日10時~)
【参加募集】IOG地経学オンラインサロン「欧州選挙をめぐる地経学」を開催します(8月3日10時~)
2024/05/15  【執筆】地経学研究所編「経済安全保障とは何か」(東洋経済新報社)刊行
【執筆】地経学研究所編「経済安全保障とは何か」(東洋経済新報社)刊行
2023/12/07  【レポート公開】地経学研究レポート「各国防衛産業の比較研究-自律性、選択、そして持続可能性-」
【レポート公開】地経学研究レポート「各国防衛産業の比較研究-自律性、選択、そして持続可能性-」
地経学研究所
Institute of Geoeconomics (IOG)
民間・独立のシンクタンクという立場から、アジア・太平洋地域を代表する知の交流の拠点となり、グローバルでより高いインパクトを発することを目指してまいります。
新着情報
- 2024/07/24ウクライナ戦争解決に向けての人権規範の重要性(地経学ブリーフィング・松村五郎)
- 2024/07/18国際安全保障秩序の変局にどう向き合うか(地経学ブリーフィング・尾上 定正)
- 2024/07/10変質しつつあるアメリカのリベラリズム(地経学ブリーフィング・熊谷奈緒子)
- 2024/07/03ドイツと欧州議会選挙――若者は右傾化したのか(地経学ブリーフィング・板橋拓己)
- 2024/06/26欧州議会選挙2024 2つの「疲れ」表出と2つの域外脅威への対抗(地経学ブリーフィング・鈴木均)
IOG特設ページ
 2024年は台湾、欧州連合(EU)や米国を始めとして各国で選挙が実施される「選挙イヤー」となります。選挙による国内政治のダイナミクスの変化は世界政治に影響を与え、地政学・地経学上のリスクを生じさせる可能性があります。また、報道の自由の侵害や偽情報の急増など、公正な選挙の実施に対する懸念が高まっているなか、今後の民主主義の行方が注目されています。本特集では、2024年に実施される各国の選挙の動向を分析するとともに、国内政治の変化が国際秩序に与える影響についても考察していきます。
2024年は台湾、欧州連合(EU)や米国を始めとして各国で選挙が実施される「選挙イヤー」となります。選挙による国内政治のダイナミクスの変化は世界政治に影響を与え、地政学・地経学上のリスクを生じさせる可能性があります。また、報道の自由の侵害や偽情報の急増など、公正な選挙の実施に対する懸念が高まっているなか、今後の民主主義の行方が注目されています。本特集では、2024年に実施される各国の選挙の動向を分析するとともに、国内政治の変化が国際秩序に与える影響についても考察していきます。
 中国の台湾軍事侵攻の可能性に言及する議論がある一方で、その能力を疑問視するものもある。はたして真実はどこにあるのか。判断を下す前に、事実を整理する必要がある。世界は、この問題にいかに向き合おうとしているのか。そして、日本はいかなる態度をもって向き合うべきなのか。本特集では、関連文章を掲載するほか、地経学ブリーフィングやインサイト、研究員の解説と論考を中心に考察する。
中国の台湾軍事侵攻の可能性に言及する議論がある一方で、その能力を疑問視するものもある。はたして真実はどこにあるのか。判断を下す前に、事実を整理する必要がある。世界は、この問題にいかに向き合おうとしているのか。そして、日本はいかなる態度をもって向き合うべきなのか。本特集では、関連文章を掲載するほか、地経学ブリーフィングやインサイト、研究員の解説と論考を中心に考察する。
 地経学研究所(IOG)は、APIのプロジェクトを引き継ぎ、昨年に続いて2回目となる経済安全保障100社アンケートを実施しました。ウクライナ情勢を受けて、対ロ制裁は企業のコスト増や事業の将来性など経済活動に様々な影響を及ぼすとともに、米中対立や台湾有事への危機意識も高まっています。そのような中で、日本企業は、情報管理の強化やサプライチェーン強靭化など、安全保障と経済活動のはざまで苦悩しつつ様々な取組を進めています。経済安全保障をめぐり、企業は何を課題とし、どのように対処しようとしているのか、アンケートの結果などを踏まえて考察を深めます。
地経学研究所(IOG)は、APIのプロジェクトを引き継ぎ、昨年に続いて2回目となる経済安全保障100社アンケートを実施しました。ウクライナ情勢を受けて、対ロ制裁は企業のコスト増や事業の将来性など経済活動に様々な影響を及ぼすとともに、米中対立や台湾有事への危機意識も高まっています。そのような中で、日本企業は、情報管理の強化やサプライチェーン強靭化など、安全保障と経済活動のはざまで苦悩しつつ様々な取組を進めています。経済安全保障をめぐり、企業は何を課題とし、どのように対処しようとしているのか、アンケートの結果などを踏まえて考察を深めます。
地経学研究レポート
 戦略三文書を受けて防衛力の抜本的強化が進められる一方で、日本の防衛産業に対する危機感が示されています。その要因や課題は何なのか。現在提示されている解決手法は適切なのか。日本や海外の事例を比較研究することにより、日本の防衛産業政策のあるべき方向性を考察します。
戦略三文書を受けて防衛力の抜本的強化が進められる一方で、日本の防衛産業に対する危機感が示されています。その要因や課題は何なのか。現在提示されている解決手法は適切なのか。日本や海外の事例を比較研究することにより、日本の防衛産業政策のあるべき方向性を考察します。
定期配信コンテンツ
経済的な「デカップリング」が困難である中で、対立する関係にある国家がどのような関係を作っていくのか。地政学だけでは読み解けない時代を「地経学」という観点で読み解きます。
中国 / 経済安全保障 / 欧米 / 国際安全保障秩序 / 新興技術 / ウクライナ戦争 / 戦略3文書 / G7サミット
毎月第2土曜日の午前に、最新の地経学的重要テーマについて、鈴木一人地経学研究所長(東京大学公共政策大学院教授)が、そのテーマに関する第一線の論客をゲストに迎え、議論を深めます。
IOG地経学インサイトでは、世界や日本が注目する国際関係、地政学、地経学的なニュースについて、IOGのエキスパートがQ&A形式でわかりやすく解説します。
大きく変化する国際情勢の動向、なかでも刻々と変化する大国のパワーバランスについて、世界の論壇をフォローするAPIの研究員がブリーフィングします。
(執筆:細谷雄一 API研究主幹、地経学研究所欧米グループ・グループ長、慶應義塾大学法学部教授)
IOG Economic Intelligence Report
The IOG Economic Intelligence Report will cover the latest regulatory developments on economic security & geoeconomics in the United States and Europe along with background and analysis of what it means for Japan and Asia. Written by Paul Nadeau, visiting research fellow at the Institute of Geoeconomics (IOG) and assistant adjunct professor with Temple University, Japan Campus, the Economic Intelligence Report will be released every two weeks.
Geoeconomic Agenda is a new Pacific-centric, globally-minded podcast that investigates the connections between economics, geopolitics, business, and society. Hosted by Paul Nadeau, Geoeconomic Agenda will feature interviews with guests from across the Asia-Pacific region and beyond, from the policy world, academia, business, and more. Available on Apple Podcast, Spotify, and YouTube.
研究員紹介
国際情勢の変化に応じたより広い社会貢献を果たすため、国際関係、地政学、地域研究、経済安全保障、国際安全保障秩序、サイバー・宇宙などの分野を中心に、研究調査・提言、国内外の有識者との知的対話、人材育成を促進する専門家が研究員として所属しています。研究員の氏名をクリックすると詳細をご覧いただけます。
研究グループ・グループ長
鈴木一人
地経学研究所長
経済安全保障グループ・グループ長
細谷雄一
API研究主幹
欧米グループ・グループ長
江藤名保子
上席研究員
中国グループ・グループ長
尾上定正
シニアフェロー
国際安全保障秩序グループ・グループ長
塩野誠
経営主幹
新興技術グループ・グループ長
神保謙
常務理事
APIプレジデント
研究員(50音順)
イベント報告
2023.06.20
地経学研究所は、読売新聞社と共催で2023年6月20日、国際文化会館において、『半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』著者で米タフツ大准教授のクリス・ミラー氏をお招きし、「半導体戦争 問われる技術力(読売国際会議)」を開催しました。
2023.05.30
2023年5月29日David Eby カナダブリティッシュ・コロンビア州首相、Ian Mckay駐日カナダ大使 兼 インド太平洋地域担当特使を国際文化会館にお招きし、カナダ大使館と共催で講演会を開催しました。最初にIan Mckay大使より‘Canada, Japan and Indo-Pacific Strategy’と題して、カナダが昨年11月に発表したインド太平洋地域戦略の背景や内容、今月行われたG7サミットの評価についての講演をいただきました。その後David Eby州首相より、‘British Colombia’s growing role as a key partner of Japan’と題して、同州の投資先としての魅力について、日本がこれまで取引を行ってきた鉱物資源、食品、木材に加え、LNGや水素分野での協力にかかるお話をいただきました。
2023.05.30
経済安保100社アンケート、企業の声を政府に提出 高市早苗経済安全保障担当大臣
地経学研究所は2023年5月30日、高市早苗経済安全保障担当大臣に経済安全保障100社アンケートの結果及び回答企業の声をとりまとめたブックレットを鈴木一人より提出しました。「経済安全保障担当大臣に何を期待しますか」との問いに対して企業からいただいた60以上のご意見、要望を伝えました。また高市大臣が法制化を目指すセキュリティ・クリアランス制度について、地経学研究所主任研究員による論考を中心に議論を深めました。
2023.05.13
G7広島サミット2023:日本政府に経済安全保障「9つのチェックポイント」を提出
地経学研究所(IOG、所長:鈴木一人)は、G7広島サミット2023に向けて、5月11日に外務省経済安全保障政策室、13日に内閣官房国際広報室に、経済安全保障における「9つのチェックポイント」を提出しました。内容としては、「経済安全保障の手段は、ルールに基づく国際秩序と一貫性を持たせるべき」(Item1)、「G7各国のサプライチェーン強靭化のために信頼できるサプライチェーンネットワークを構築すべき」(Item2)といった経済安全保障のあるべき原則を述べたものです。このチェックポイントの作成にあたっては、5月2日(火)、G7とEUに本部を置く各国シンクタンク、大学の研究所、在京大使館の関係者を招いて、オンライン会合を実施の上、出席者からフィードバックを頂きました。
2023.03.29
Asia Pacific Geoeconomics Council準備会合「米中の狭間を生き抜くアジア各国の戦路」
地経学研究所(IOG、所長:鈴木一人)は2023年3月29日、国際文化会館にて、韓国、シンガポール、オーストラリア、インドから経済安全保障の専門家を招いてAsia Pacific Geoeconomics Council準備会合を開催しました。アジア各国において、置かれている環境、政治や経済状況が異なる中で、それぞれの国にとっての経済安全保障について議論を深め、共通の理解を得ることを目的としたものです。会合の一環として、各専門家と地経学研究所長・鈴木一人の座談会を収録しました。
2022.10.24
地経学研究所と蘭語系ブリュッセル自由大学安全保障・外交・戦略研究所(VUB-CSDS)は2022年10月24日、シンポジウム「変容する世界における欧州と日本」を国際文化会館にて共催しました。シンポジウムでは、冒頭にハイツェ・ジーメルス駐日EU代表部公使・副代表より開会ご挨拶をいただいたのち、林芳正外務大臣およびエンリケ・モラ欧州対外活動庁事務次長による基調講演、「インド太平洋地域の安定に向けた連携構築」と題したパネルディスカッションへと続きました。パネルディスカッションでは、VUB-CSDSの初代ジャパン・チェアに就任したエヴァ・ペイショヴァー氏がモデレーターを務め、パネリストとして登壇したダニエル・フィオットVUB-CSDS防衛・ステートクラフトプログラム長、ミヒャエル・ライテラーVUB-CSDS Distinguished Professor)、神保謙国際文化会館常務理事兼APIプレジデント、江藤名保子地経学研究所上席研究員兼中国グループ長により、活発な議論が繰り広げられました。
2022.07.26
地経学研究所(IOG)主催シンポジウム「日英から見た経済安全保障」
IISSからロバート・ウォード日本部長兼地経学・戦略担当ディレクターおよび越野結花安全保障・技術政策担当担当リサーチ・フェローをお招きし、「サプライチェーンの強靭化」「デュアルユース技術の管理と推進」をテーマに、国内の経済安全保障に強い関心を有する企業の代表、駐日英国大使館の経済・金融参事官、地経学研究所のエキスパートとの間で、議論を行いました。
2022.10.05
地経学研究所(IOG)設立記念シンポジウム「危機の時代の地経学」
ロシアによるウクライナ侵略が長期化し、台湾情勢をめぐる不確実性が増す中、国際秩序はどう変わるのか、地経学リスクとどう向き合えば良いのか。地経学研究所は、初代経済安全保障担当大臣を務めた小林鷹之衆議院議員や、ロシア・台湾・エネルギーといった分野の専門家を招聘し、議論を深めました。
関連プログラム
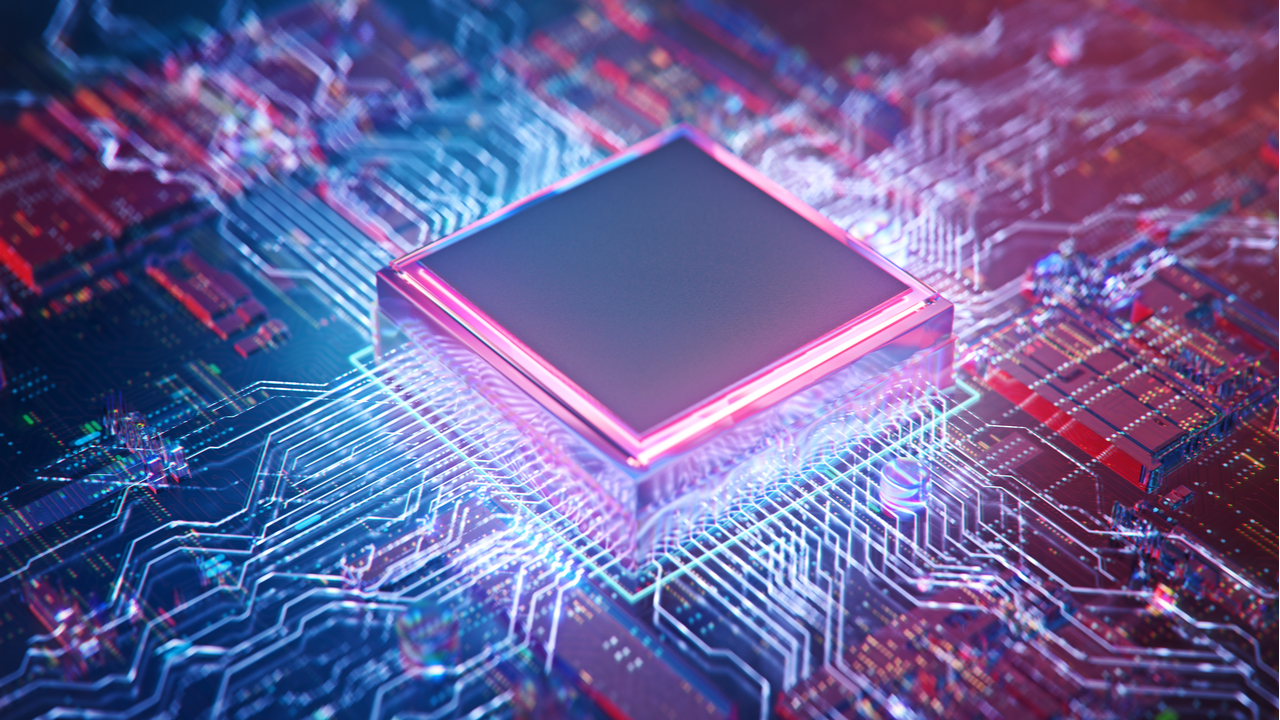
日本の経済安全保障戦略はどうあるべきか、そのために政府と民間はどう協力すべきか、について検討し、国家としての「全体最適解」を探求するべく、政・官・民・学の集う経済安全保障政策コミュニティの構築を目指します。詳細は こちら から

当プロジェクトの研究の成果として、2020年2月にBrookings Institution Pressより『The Crisis of Liberal Internationalism: Japan and the World Order』を出版し、本書の日本語版として、2020年8月に東洋経済新報社より『自由主義の危機』を出版しました。詳細はこちらから

米国の統合参謀本部議長経験者と日本の統合幕僚長経験者が一堂に会し、議論することで戦略的リバランシング時代における日米の政策対話を強化し、両国の安全保障政策コミュニティをより深くつなぐ上での絆になることを目指しています。詳細はこちらから
会員募集・お問合せ
地経学研究所では、設立趣旨に賛同し、活動にご関心のある法人を、会員として募集しております。お問合せはこちらまで。
 APIニュースレター 登録
APIニュースレター 登録