IOG地経学オンラインサロン

地経学研究所(Institute of Geoeconomics: IOG)では、最新の地経学的重要テーマについて議論を深める「IOG地経学オンラインサロン」を、原則毎月第3土曜日午前10時~11時に開催しております。なお、視聴するためには事前登録が必要です(参加費無料)。
2024.08.03
【申込受付中】欧州選挙をめぐる地経学(ゲスト:国末憲人 東京大学先端科学技術研究センター特任教授)


東京大学先端科学技術研究センター特任教授。1963年岡山県生まれ。85年大阪大学卒業。87年パリ第2大学新聞研究所を中退し朝日新聞社に入社。パリ支局長、論説委員、GLOBE編集長、ヨーロッパ総局長などを経て退職し、2024年1月より現職。著書に『ロシア・ウクライナ戦争 近景と遠景』(岩波書店)、『自爆テロリストの正体』『サルコジ』『ミシュラン 三つ星と世界戦略』(いずれも新潮社)、『テロリストの誕生』『イラク戦争の深淵』『ポピュリズムに蝕まれるフランス』『巨大「実験国家」EUは生き残れるのか?』(いずれも草思社)、『ユネスコ「無形文化遺産」』(平凡社)など。
2024.07.20
【申込受付中】日米加関係の地経学(ゲスト:フィリップ・リプシー トロント大学政治学部教授)

2001年、スタンフォード大学経済学部・政治学部卒業。同大学院国際政策研究修士課程修了後、2008年にハーバード大学よりPh.D.(政治学)を取得。スタンフォード大学政治学部助教授を経て、2019年トロント大学日本研究センター所長・政治学部准教授に就任。2022年よりトロント大学政治学部教授・東京大学大学院法学政治学研究科教授を兼任。専門分野は国際関係理論、日本の政治と外交、金融危機の政治経済、エネルギー・環境政策。著書に「Renegotiating the World Order: Institutional Change in International Relations」、「The Political Economy of the Abe Government and Abenomics Reforms」など。コロンビア大学WEAI Japan Research Program Advisory Board、マンスフィールド財団U.S.-Japan Network for the Future Advisory Committee、ハーバード大学Program on U.S.-Japan Relations Faculty Associate、米日カウンシルCouncil Leaderなど。
2024.06.15
【申込受付中】中東情勢の地経学(ゲスト:坂梨祥 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター副センター長・研究理事)

(一財)日本エネルギー経済研究所中東研究センター副センター長。東京大学総合文化研究科国際社会科学専攻国際関係論コースで修士号を取得後、英国ダーラム大学中東イスラム研究コース修士課程を修了。在イラン日本国大使館専門調査員を経て、2005年に東京大学大学院総合文化研究科博士課程を単位取得退学後、日本エネルギー経済研究所中東研究センターに入所。ガルフ・リサーチ・センター(ドバイ)客員研究員などを経て、2018年より日本エネルギー経済研究所研究理事。2019年より現職。専攻はイラン現代政治。
2024.05.18
日米中韓をめぐる地経学(ゲスト:佐橋亮 東京大学東洋文化研究所准教授)

国際基督教大学教養学部卒。東京大学大学院博士課程修了、博士(法学)。専攻は国際政治学、特に米中関係、東アジアの国際関係、秩序論。オーストラリア国立大学博士研究員、東京大学特任助教、神奈川大学教授・同アジア研究センター所長を経て2019年度より現職。土地等利用状況審議会委員、科学技術外交推進会議委員、文化庁国際文化交流・推進委員会委員。また、日本国際交流センター客員研究員、日本経済団体連合会21世紀政策研究所客員研究委員、全米アジア研究所諮問委員を兼ねる。 スタンフォード大学アジア太平洋研究センター客員准教授、ウィルソン国際学術センター・ジャパンスカラー、ソウル国立大学客員研究員、経済産業研究所ファカルティフェローを歴任。著書に『米中対立:アメリカの戦略転換と分断される世界』(中央公論新社)、『共存の模索 アメリカと「2つの中国」の冷戦史』(勁草書房)、編著書に『冷戦後の東アジア秩序』(勁草書房)、訳書にアーロン・フリードバーグ『支配への競争:米中対立の構図とアジアの将来』(日本評論社)など。論文は日本語、英語、中国語にて多数。神奈川大学学術褒賞、日本台湾学会賞など受賞。
2024.04.20
日本の海洋安全保障をめぐる地経学(ゲスト:奥島高弘 公益財団法人海上保安協会理事長)

1959年7月7日生まれ。北海道小樽市出身。1982年海上保安大学校を卒業。海上保安官として警備救難、航行安全等の実務に携わり、根室海上保安部長、第三管区海上保安本部交通部長、政務課政策評価広報室海上保安報道官、警備救難部警備課領海警備対策官、警備救難部管理課長、総務部参事官、第八管区海上保安本部長、警備救難部長などを歴任する。2018年7月31日海上保安監、2020年1月7日海上保安庁長官に就任。2022年6月28日退任。2022年11月1日公益財団法人海上保安協海理事長に就任。
2024.03.09
セキュリティ・クリアランスと地経学(ゲスト:北村滋 前国家安全保障局長)

前国家安全保障局長。1956年12月27日生まれ。東京都出身。東京大学法学部卒業。1980年4月、警察庁に入庁。83年6月、フランス国立行政学院(ENA)に留学。92年2月、在フランス大使館一等書記官。その後、警備局外事情報部外事課長、内閣総理大臣秘書官(第1次安倍内閣)、警備局外事情報部長を歴任。2011年12月、野田内閣で内閣情報官に就任。第2次~第4次安倍内閣で留任。特定秘密保護法の策定・施行。19年9月、第4次安倍内閣の改造に合わせて国家安全保障局長・内閣特別顧問に就任。同局経済班を発足させ、経済安全保障政策を推進。20年9月、菅内閣において留任。同年12月、米国政府から国防総省特別功労賞を受章。21年7月、退官。22年1月、オーストラリア政府からオーストラリア情報功労章を受章。同年6月、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章オフィシエを受章。23年12月、台湾政府から大綬景星勲章を受章。北村エコノミックセキュリティ代表。
2024.02.10
軍備管理の地経学(ゲスト:髙見澤將林 東京大学公共政策大学院客員教授)

略歴は1955年生まれ。東京大学公共政策大学院客員教授。元軍縮会議日本政府代表部大使
2024.01.13
2024年の地経学の見通し(ゲスト:森聡 慶應義塾大学法学部教授)

1995年3月京都大学法学部卒。同大学大学院法学研究科及び米コロンビア大学ロースクール修士課程修了。外務公務員採用Ⅰ種試験で外務省入省。同省退職後、2007年に東京大学大学院法学政治学研究科にて博士(法学)。2008年より法政大学法学部准教授、2010年から2022年3月まで同教授。この間、米プリンストン大学(2014~2015年)及びジョージワシントン大学(2013年~2015年)で客員研究員。2022年4月より現職。現在の研究テーマは、米中関係・日米関係を含むアメリカのアジア戦略、先端技術と国防イノベーション、冷戦期アメリカの戦略史。主な著書に『国際秩序が揺らぐとき―歴史・理論・国際法からみた変容』(編著、千倉書房、2023年)、『ウクライナ戦争と世界のゆくえ』(共著、東京大学出版会、2022年)、『「強国」中国と対峙するインド太平洋諸国』(共著、千倉書房、2022年)、『アメリカ政治の地殻変動』(共著、東京大学出版会、2021年)、『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』(共編著、東京大学出版会、2020年)、『アメリカ太平洋軍の研究』(共著、千倉書房、2018年)『ヴェトナム戦争と同盟外交』(単著、東京大学出版会、2009年、日本アメリカ学会清水博賞受賞)ほか。
2023.12.09
AIと地経学(ゲスト:山本麻理 株式会社FRONTEO取締役)

株式会社FRONTEO取締役。広告代理店に入社後、リスクマネジメント会社に在籍。メンタルヘルスケア事業を立ち上げ、事業計画、商品開発、マーケティング、営業戦略を実行し同社を業界トップシェアへと導く。2014年に取締役に就任し、2017年に東証一部上場を実現。2018年に FRONTEOに参画、2020年取締役に就任し社長室およびAIソリューション事業全域を管掌・指揮。ライフサイエンスAI事業、ビジネスインテリジェンス事業、経済安全保障事業を担当。自然言語解析分野でのトップカンパニーとして、AIソリューション事業の成長戦略を立案・指揮。
2023.11.11
日韓関係をめぐる地経学(ゲスト:西野純也 慶應義塾大学法学部政治学科教授・朝鮮半島研究センター長)

慶應義塾大学法学部政治学科教授、同大学東アジア研究所長、朝鮮半島研究センター長。慶應義塾大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科修士課程卒業、同博士課程単位取得。韓国・延世大学大学院博士課程卒業、政治学博士。専門は現代韓国朝鮮政治、東アジア国際政治、日韓関係。在韓国日本大使館政治部専門調査員、外務省国際情報統括官組織第3国際情報官室専門分析員、ハーバード・エンチン研究所交換研究員、ウッドロー・ウィルソンセンター客員研究員(ジャパン・スカラー)、ジョージ・ワシントン大学シグールセンター客員研究員、慶南大学極東問題研究所招聘研究委員、延世大学統一研究院専門研究員などを歴任。著書に、『激動の朝鮮半島を読みとく』(編著、慶應義塾大学出版会、2023年)、『アメリカ太平洋軍の研究』(共著、千倉書房、2018年)、『朝鮮半島の秩序再編』(共編著、慶應義塾大学出版会、2013年)、『転換期の東アジアと北朝鮮問題』(共編著、慶應義塾大学出版会、2012年)など。
2023.10.07
経済学から見た地経学(ゲスト:白井さゆり 慶應義塾大学総合政策学部教授)

コロンビア大学経済学部大学院修了,経済学博士。アジア開発銀行研究所のサステナブル政策アドバイザー。野村サステナビリティリサーチセンターと日清オイリオグループのアドバイザー。2020-21年EOS at Federated Hermes(英国系の世界主要企業に関するESGエンゲージメント専門会社)の上級顧問。2011-16年日本銀行政策委員会審議委員として金融政策決定などに関与。2016-17パリ政治学院客員教授。元IMFエコノミスト。世界経済、金融政策、国際金融を専門とし、数多くの書籍・論文を英語と日本語で出版。最近の書作としては、『SDGsファイナンス』(日経BP、2022年)、『カーボンニュートラルをめぐる世界の潮流』(文真堂、2022年)、Global Climate Challenges, Innovative Finance, and Green Central Banking(Asian Development Bank Institute, 2023年7月)がある。最近の英語論文として日本銀行の20年の金融政策史がある。世界の国際会議や討論会などで数多くの講演や討論者として参加。国内外の新聞・TV・ラジオほかでコメンテーターとして日本・世界経済、国際金融、金融政策について数多くコメントを実施。ジャパンタイムズ紙への寄稿。
日経電子版のThink!エキスパートとしてニュースにひとこと解説も実施中。オフィシャルホームページURL;http://www.sayurishirai.jp/を参照。
2023.09.09
宇宙安全保障をめぐる地経学(ゲスト:片岡晴彦 内閣府宇宙政策委員会委員 / 日本宇宙安全保障研究所JISS副理事長 / 株式会社IHI顧問)

1952年札幌生まれ。 1976年、防衛大学校を卒業し、航空自衛隊へ入隊。1979年、東京工業大学総合理工学研究科修士・博士課程(電子化学)に入学し、理学博士号を取得。 その後、戦闘機等の研究開発部門や防衛計画部門などで勤務。中部航空方面隊司令官、航空教育集団司令官、航空総隊司令官を歴任し、2012年に航空幕僚長に就任、2013年に退官。 2014年から株式会社IHI顧問に就任。
2014年から内閣府宇宙政策委員会基本政策部会の委員に就任し、現在、宇宙政策委員会委員、宇宙政策委員会の宇宙安全保障部会 部会長代理、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構分科会委員などに就任し、宇宙基本計画、宇宙安全保障構想などの策定に携わる。 2018年には、日本宇宙安全保障研究所副理事長に就任。 また、内閣官房国家安全保障局 顧問会議顧問、防衛大臣政策参与を歴任。
2023.08.05
日本の経済安全保障における半導体(ゲスト:小柴満信 Cdots合同会社共同創業者)

Cdots合同会社 共同創業者
1955年東京生まれ。1978年千葉大学工学部(印刷・画像工学)卒業、1980年同大学院修了。ロータリー財団奨学金を受けて米国ウィスコンシン州立大学大学院材料科学科に留学後、1981年に日本合成ゴム㈱(現JSR㈱)入社。東京研究所にて半導体材料の開発に従事する。1990年に米国シリコンバレーに赴任し、JSR Micro Inc. にて半導体材料事業の米国市場での地位確立に尽力。2002年に帰国後、電子材料事業部長、ファイン事業担当役員を経て2009年に代表取締役社長に就任。2019年に代表取締役会長、2021年6月に退任後、2023年6月末まで名誉会長。現在はAホールディングス、TBM、商船三井、ラピダスの社外取締役を兼任する一方、Cdots合同会社(シンクタンク)を設立し、先端技術、経済安全保障、イノベーション戦略に関する政府審議会委員を務め、政策提言・意見公表を行う一方、 TBM、Spiber、Quantinuumなどの国内外のスタートアップを支援中。2019年より経済同友会にて経済安全保障及び先端技術関連委員会を運営。
2023.07.08
地経学プレーヤーとしてのインド(ゲスト:伊藤融 防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授)

中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程後期単位取得退学、広島大学博士(学術)。在インド日本国大使館専門調査員、島根大学法文学部准教授等を経て2009年より防衛大学校に勤務。2021年より現職。『新興大国インドの行動原理―独自リアリズム外交のゆくえ』(慶應義塾大学出版会 2020年)、『インドの正体―「未来の大国」の虚と実』(中公新書ラクレ 2023年)など、インドを中心とした国際関係、安全保障問題に関わる著作多数。
2023.06.10
トルコ大統領選と地経学的役割(ゲスト:春日芳晃 朝日新聞国際報道部長)

朝日新聞国際報道部長。1971年鹿児島県生まれ。1997年に朝日新聞入社後、大阪社会部記者などを経て、2006-07年、カリフォルニア大学バークレー校ジャーナリズムスクール客員研究員。2011-14年、ニューヨーク支局員として国連を担当。2014-17年、イスタンブール支局長としてトルコとシリアを担当。内戦が続くシリアに計9回入り、約90日にわたって首都ダマスカスや商都アレッポ、世界遺産パルミラで戦闘の前線や市民生活を取材した。トルコでは2016年7月にクーデター未遂事件が起きた際、イスタンブールから発信を続けた。今回のトルコ大統領選で野党6党の統一候補であるケマル・クルチダルオール共和人民党党首と2015年7月に単独会見。
2023.05.13
G7サミットと議長国日本の役割(ゲスト:四方敬之 内閣広報官)

1963年京都市生まれ。1986年外務省入省後,1989-91年 在米国日本大使館、1999-2002年OECD日本政府代表部一等書記官、2004-06年 北米局日米地位協定室長,2006-07年 国際報道官、2007-09年 北米局北米第二課長、2009-10年 国際法局経済条約課長,2010-12年 内閣副広報官・官邸国際広報室長、2012-14年 在英国日本大使館政務公使,2014-16年 大臣官房人事課長,2016-17年 アジア大洋州局参事官、2017-2019年 在中国日本大使館公使・特命全権公使、2019-20年 在米国日本大使館公使(ハーバード大学客員研究員)、2020‐21年 外務省経済局長等を歴任。京都大学法学部卒,ハーバード大学ケネディ行政大学院修士(MPP)。Public Affairs Asiaの「The Gold Standard Award for Political Communications 2011」受賞。2016-17年 京都大学公共政策大学院客員教授(国際政治と日本外交)。
2023.04.08
ロシアのウクライナ侵攻でドイツはどこまで変わったのか
(ゲスト:岩間陽子 政策研究大学院大学教授)

京都大学法学部卒業、同大学院法学研究科博士課程修了。京都大学博士。京都大学助手、在ドイツ日本大使館専門調査員などを経て、2000年から政策研究大学院大学助教授。同大学准教授を経て、2009年より教授。専門はドイツを中心としたヨーロッパの政治外交史、安全保障、国際政治学。著書に『核の1968年体制と西ドイツ』(有斐閣、2021年)、『核共有の現実―NATOの経験と日本』(共著、信山社、2023年)、『冷戦後のNATO』(共著、ミネルヴァ書房、2012年)、Joining the Non-Proliferation Treaty: Deterrence, Non-Proliferation and the American Alliance, ed. With John Baylis (Routledge 2018); などがある。安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、法制審議会委員など、多くの政府委員会等のメンバーも務める。日経Think!コメンテーター、毎日新聞、政治プレミア、「今週の本棚」執筆者。
2023.03.11
12年目の3.11
(ゲスト:竹内純子 国際環境経済研究所理事・主席研究員 / 東北大学特任教授(客員) / U3innovations合同会社 共同代表)

東京大学大学院工学系研究科にて博士(工学)取得。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、東京電力株式会社で主に環境部門に従事した後、独立。複数のシンクタンクの研究員や、内閣府規制改革推進会議やGX実行会議など、多数の政府委員を務める。気候変動に関する国連交渉(COP)にも長く参加し、環境・エネルギー政策提言に従事。2018年10月U3innovations合同会社を創業。スタートアップと協業し、新たな社会システムとしての「Utility3.0」を実現することを目指し、政策提言とビジネス両面から取り組む。2022年12月23日に新刊『電力崩壊ー戦略なき国家のエネルギー敗戦』(日本経済新聞出版社)を上梓。
2023.02.11
ウクライナ侵攻から1年
(ゲスト:東野 篤子 筑波大学人文社会系教授)

筑波大学人文社会系教授。慶應義塾大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了、英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了(Ph.D)。OECD日本政府代表部専門調査員、広島市立大学国際学部准教授などを経て現職。専攻は国際関係論、ヨーロッパ国際政治。主な関心領域は、EUの拡大、対外関係、国際統合理論。著作に、『変わりゆくEU ーー永遠平和のプロジェクトの行方』(共著・明石書店、2020)、『共振する国際政治学と地域研究』(共著・勁草書房、2018年)等、訳書に『ヨーロッパ統合の理論』(勁草書房、2010年)。
2023.01.14
地経学時代の経営
(ゲスト:柴沼 俊一 株式会社シグマクシス・ホールディングス取締役)

株式会社シグマクシス・ホールディングス取締役、株式会社シグマクシス・インベストメント代表取締役社長。東京大学経済学部卒、ペンシルべニア大学経営大学院ウォートンスクール卒。1995年日本銀行入行。経済産業省産業政策局に出向。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て国内ファンドの投資先企業再生に携わり、2009年にシグマクシスに入社。事業開発コンサルティングのほか、投資責任者としてベンチャー投資、JV、カーブアウト、Pre IPO投資などに従事。未来社会を創造することをライフワークとし、社会への発信に加え多数のプロジェクトに参画。Future Society 22代表幹事。グロービス経営大学院教授。共著『知られざる職種 アグリゲーター』(2013年、日経BP)。
2022.12.17
半導体を巡る地経学
(ゲスト:風木 淳 政策研究大学院大学 政策研究院参与(経済安全保障と先端・重要技術担当))

1966年広島県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。米国コロンビア大学ロースクール・法学修士、ニューヨーク大学ロースクール・経済法学修士、ニューヨーク州弁護士。1990年に通商産業省(現:経済産業省)に入省し、公正取引委員会、貿易局為替金融課、大臣官房秘書課研修・採用担当、経済協力開発機構(OECD)、ジュネーブ国際機関日本政府代表部、通商機構部参事官、安全保障貿易管理課長、資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長、製造産業局総務課長、大臣官房審議官(経済産業政策局担当)、内閣官房内閣審議官・日本経済再生総合事務局次長(未来投資会議構造改革徹底推進会合担当)、経済産業省貿易管理部長・大臣官房経済安全保障政策統括調整官等を経て、2022年7月から現職。
2022.11.12
不安定化するイランと中東の地経学
(ゲスト:田中 浩一郎 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授)

1961年東京生まれ。1988年東京外国語大学大学院修士課程修了。専門はイランとアフガニスタンを中心とする西アジア地域の安全保障とエネルギー安全保障。1989年から在イラン日本大使館専門調査員、外務省国際情報局専門分析員、国際連合アフガニスタン特別ミッション政務官、一般財団法人日本エネルギー経済研究所常務理事などを歴任。経済産業省臨時専門アドバイザー。
2022.10.08
中間選挙でアメリカは変わるか
(ゲスト:前嶋和弘 上智大学教授、総合グローバル学部長)

静岡県生まれ。上智大学教授、総合グローバル学部長。アメリカ学会会長。専門は現代アメリカ政治外交。上智大学外国語学部英語学科卒、ジョージタウン大学大学院政治学部修士課程修了(MA)、メリーランド大学大学院政治学部博士課程修了(Ph.D.)。主な著作は『アメリカ政治とメディア』(北樹出版、2011年)、『危機のアメリカ「選挙デモクラシー」』(共編著、東信堂、2020年)、『現代アメリカ政治とメディア』(共編著、東洋経済新報社、2019年)、Internet Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan (co-edited, Palgrave, 2017)など。
2022.09.10
地経学時代における国連:その取材現場から
(ゲスト:宮本晴代 TBSテレビ報道局記者)

TBSテレビ報道局記者。現在は政治部で与党取材を担当。2017年から2021年まで、ニューヨーク支局特派員として国連を担当し、北朝鮮に対する安保理制裁や、史上初の米朝首脳会談を取材。2005年入社以来、報道局で警視庁、文科省担当を経て、「報道特集」ディレクター時代は日本人遺骨問題を中心に北朝鮮での取材を重ねる。「news23」ディレクターとして英国のEU離脱、米国トランプ大統領の誕生を取材。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒。
2022.08.20
戦争と地経学
(ゲスト:高橋杉雄 防衛研究所防衛政策研究室長)

1972年神奈川県生まれ。1997年早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。2006年ジョージワシントン大学大学院修了。1997年より防衛研究所。1998年より2001年まで防衛省防衛政策局防衛政策課研究室、2008年より2016年まで防衛省防衛政策局防衛政策課戦略企画室兼務。核抑止論、日本の防衛政策を中心に研究。主な著作に『新たなミサイル軍拡競争と日本の防衛』(並木書房、2020年)(共編著)、『「核の忘却」の終わり:核兵器復権の時代」』(勁草書房、2016年)(共編著)、China’s Strategic Arsenal: Worldview, Doctrine, and Systems (Georgetown University Press, 2001) (『中国の戦略的能力:世界観、ドクトリン、システム』(共著)。
2022.07.16
地経学時代におけるビジネス
(ゲスト:新浪剛史 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長)

ハーバード大学経営大学院を修了。ローソン代表取締役社長CEOを経て2014年より現職であるサントリーホールディングス代表取締役社長を務める。公職では、2014年から内閣総理大臣が議長で日本の経済財政のコントロールタワーである経済財政諮問会議に民間議員として参画、2019年から全世代型社会保障検討会議、そして、未来投資会議2020年議員。他、2011年よりアジア・パシフィック・イニシアティブ理事、2020年より2度目の経済同友会副代表幹事を務める。国際商業会議所(International Chamber of Commerce)Executive Board、世界経済フォーラムInternational Business Council、世界経済フォーラム第四次産業革命センターAdvisory Board、Asia Business Council Vice Chairman、米国外交問題評議会Global Board of Advisors、米国The Business Councilのメンバーとして、グローバルに活躍。
2022.06.11
API創立10周年記念ーロシア・ウクライナ戦争をめぐる地経学と国際秩序の変動
(ゲスト:細谷雄一 API研究主幹、神保謙 API MSFエグゼクティブ・ディレクター)


API研究主幹、慶應義塾大学法学部教授、ケンブリッジ大学ダウニング・カレッジ訪問研究員。立教大学法学部卒業、英国バーミンガム大学大学院国際学研究科修了(MIS)、慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程および博士課程修了。博士(法学)。北海道大学法学部専任講師、敬愛大学国際学部専任講師、プリンストン大学客員研究員(フルブライト・フェロー)、パリ政治学院客員教授(ジャパン・チェア)などを経て現職。安倍晋三政権において、「安全保障と防衛力に関する懇談会」委員(2013年)、および「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」委員(2013年-14年)、国家安全保障局顧問会議顧問(2014年-16年)を歴任。自民党「歴史を学び、未来を考える本部」顧問(2015年-18)。
API MSFエグゼクティブ・ディレクター、慶應義塾大学総合政策学部教授。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了(政策・メディア博士)。専門は国際政治学、安全保障論、アジア太平洋の安全保障、日本の外交・防衛政策。タマサート大学(タイ)で客員教授、国立政治大学、国立台湾大学(台湾)で客員准教授、南洋工科大学(シンガポール)客員研究員を歴任。政府関係の役職として、防衛省参与、国家安全保障局顧問、外務省政策評価アドバイザリーグループ委員などを歴任。
2022.05.14
新しい宇宙開発時代の地経学(ゲスト:石田真康 A.T.カーニーディレクター/一般社団法人SPACETIDE共同創業者 兼 代表理事 兼 CEO)

一般社団法人SPACETIDEの共同創業者 兼 代表理事 兼 CEOとして、「宇宙ビジネスの新たな潮流をつくる」ことをミッションに、年次カンファレンス「SPACETIDE」を主催。また、経営コンサルティングファームKearneyのGlobal Space Groupのリーダーとして国内外の政府機関や企業に対して経営コンサルティングを実施。内閣府 宇宙政策委員会 基本政策部会をはじめとする各種政府委員会を通じて日本政府の宇宙政策立案・実行を支援。日経産業新聞および日経デジタルにて「WAVE」を2018年より連載中。また著書に「宇宙ビジネス入門 Newspace革命の全貌」(日経BP社)。東京大学工学部卒。
2022.04.02
経済安全保障と国家安全保障戦略に向けて(ゲスト:佐藤丙午 拓殖大学海外事情研究所副所長 / 国際学部教授)

拓殖大学海外事情研究所副所長/国際学部教授
岡山県生まれ。一橋大学大学院修了(博士・法学)。拓殖大学国際学部教授兼海外時事情研究所副所長。防衛庁防衛研究所主任研究官(アメリカ研究)を経て、2006年より現職。専門は国際関係論、安全保障論、軍備管理軍縮など。2010年に外務省参与および外務大臣の政策参与(軍縮・核不拡散担当)を務める。特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の自律型致死兵器システム(LAWS)などの国連専門家会合に出席。著作に、『自律型致死性無人兵器システム(LAWS)』(国際問題・2018年6月号)、『エコノミック・ステートクラフトの理論と現実』(国際政治、第205号)など。安全保障貿易学会副会長、日本軍縮学会副会長。
2022.03.12
ロシア・ウクライナ問題を地経学で読み解く(ゲスト:小泉悠 東京大学先端科学技術研究センター専任講師)

東京大学先端科学技術研究センター専任講師(グローバルセキュリティ・宗教分野)、新領域セキュリティの諸課題に関する分科会座長、中国・権威主義体制に関する分科会委員(ロシア班・班長)。
民間企業、外務省専門分析員等を経て、2009年、未来工学研究所に入所。2017年に特別研究員となり、2019年2月まで勤務。この間、外務省若手研究者派遣フェローシップを得てロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所に滞在したほか(2010-2011年)、国立国会図書館立法及び考査局でロシアの立法動向の調査に従事した(2011-2018年)。2019年3月、東京大学先端科学技術研究センター特任助教。2022年1月より現職。専門は安全保障論、国際関係論、ロシア・旧ソ連諸国の軍事・安全保障政策。
2022.02.12
ASEANと東南アジア諸国の地経学(ゲスト:大庭三枝 神奈川大学法学部・法学研究科教授)

1968年東京生まれ。国際基督教大学卒業。東京大学大学院総合文化研究科修士課程、博士課程終了。博士(学術)。東京大学大学院助手、東京理科大学准教授、東京理科大学教授、南洋工科大学(シンガポール)客員研究員、ハーバード大学日米関係プログラム研究員、参議院第一調査室客員研究員等を経て2020年4月より現職。専門は国際関係論、国際政治学、アジア太平洋/東アジアの国際政治、ASEANを含むアジア全般の地域主義、および地域秩序の変容を中心とした国際関係についての研究に従事。主な邦語主著として『アジア太平洋地域形成への道程:日豪のアイデンティティ模索と地域主義』ミネルヴァ書房、2004年(単著)、『重層的地域としてのアジア:対立と共存の構図』2014年、有斐閣(単著)、『東アジアのかたち:秩序形成と統合を巡る日米中ASEANの交差』2015年、千倉書房(共著)など。2005年に第21回大平正芳記念賞、第6回NIRA大来政策研究賞受賞。2015年に第11回中曽根康弘奨励賞受賞。
2022.01.08
バイデン政権の1年で見えてきた地経学的課題(ゲスト:中山俊宏 慶應義塾大学総合政策学部教授)

慶応義塾大学総合政策学部・教授/日本国際問題研究所・上席客員研究員
一九六七年生まれ、東京都出身。青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科卒。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際政治学専攻博士課程修了。博士(国際政治学)。ワシントン・ポスト紙極東総局記者、日本政府国連代表部専門調査員、日本国際問題研究所主任研究員、ブルッキングス研究所招聘客員研究員、津田塾大学国際関係学科准教授、青山学院大学国際政治経済学部教授等を経て、二〇一四年四月より現職。二〇一七年にはサー・ハワード・キッペンバーガー・チェア客員教授(ビクトリア大学ウェリントン戦略研究センター)、二〇一八~一九年にはウッドロウ・ウィルソン・センター・ジャパン・スカラー、二〇一九~二〇年には防衛省参与。専門はアメリカ政治・外交、国際政治、日米関係。主な著書に『アメリカ政治の地殻変動』(共編著、東大出版会)『アメリカン・イデオロギー』(単著、勁草書房)、『介入するアメリカ』(単著、勁草書房)、『アメリカにとって同盟とはなにか』(共著、中央公論)、『オバマ・アメリカ・世界』(共著、NTT出版)、『世界政治を読み解く』(共編著、ミネルヴァ書房)などがある。第10回中曽根康弘奨励賞受賞。
2021.12.11
岸田政権の経済安全保障(ゲスト:大野敬太郎 衆議院議員・内閣府副大臣(経済安全保障・防災等担当))

1991年東京工業大学工学部卒、93年同大学院修士修了。同年富士通入社。01年米国カリフォルニア大学バークレー校客員フェロー。04年国務大臣秘書官。06年東京大学産学官連携研究員(情報理工学博士号取得)。12年総選挙にて初当選。爾来、自民党の外交・農林・国防の副部会長、財務金融や外交の部会長代理、17年防衛大臣政務官、19年副幹事長、20年国防部会長代理等を経て現職。
2021.11.13
AUKUS時代のインド太平洋の地経学(ゲスト:鶴岡路人 慶應義塾大学総合政策学部准教授)

東京都生まれ。1998年慶應義塾大学法学部卒業、米ジョージタウン大学を経て、英ロンドン大学キングス・カレッジで博士号取得。専門は国際安全保障、現代欧州政治。在ベルギー日本大使館専門調査員、防衛研究所主任研究官などを経て、2017年から現職。東京財団政策研究所主任研究員、ブリュッセル自由大学(VUB)安全保障・外交・戦略研究所(CSDS)上席研究員などを兼務。近著に『EU離脱ーーイギリスとヨーロッパの地殻変動』(ちくま新書、2020年)など。
2021.10.09
米軍撤退後のアフガニスタン(ゲスト:青木健太中東調査会研究員)
中東調査会.jpg)
公益財団法人中東調査会研究員。2001年上智大学卒業、2005年英国ブラッドフォード大学大学院平和学修士課程修了(平和学修士)。専門は現代アフガニスタン・イラン政治。アフガニスタン政府省庁アドバイザー、在アフガニスタン日本国大使館二等書記官、外務省国際情報統括官組織専門分析員、お茶の水女子大学講師等を経て現職。著書に『ハイブリッドな国家建設:自由主義と現地重視の狭間で』(ナカニシヤ出版、2019年、共著)、「ターリバーンの政治・軍事認識と実像――イスラーム統治の実現に向けた諸課題」(『中東研究』第538号、2020年)等。
2021.09.11
日本のエネルギー戦略の地経学(ゲスト:岩瀬昇エネルギーアナリスト)

1948年10月、埼玉県生まれ。エネルギーアナリスト。浦和高校、東京大学法学部卒業。71年三井物産入社、2002年三井石油開発に出向、10年常務執行役員、12年顧問。三井物産入社以来、香港、台北、2度のロンドン、ニューヨーク、テヘラン、バンコクの延べ21年間にわたる海外勤務を含め、一貫してエネルギー関連業務に従事。14年6月に三井石油開発退職後は、新興国・エネルギー関連の勉強会「金曜懇話会」代表世話人として、後進の育成、講演・執筆活動を続けており、「岩瀬昇のエネルギーブログ」で情報発信中。著書に『石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか? エネルギー情報学入門』(2014年9月、文春新書) 、『日本軍はなぜ満洲大油田を発見できなかったのか』 (2016年1月、同)、『原油暴落の謎を解く』(2016年6月、同)、最新刊に『超エネルギー地政学 アメリカ・ロシア・中東編』(2018年9月、エネルギーフォーラム)がある。
2021.08.14
台湾半導体産業の地経学(ゲスト:川上桃子アジア経済研究所地域研究センター長)

1991年、東京大学経済学部を卒業し、アジア経済研究所に入所。2011年、経済学博士号(東京大学)取得。1995-97年、2012-13年に台湾、カリフォルニアで在外研究を行う。専門は台湾を中心とする東アジアの経済発展。台湾半導体産業に関する最近の論考に「米中ハイテク覇権競争と台湾半導体産業――『二つの磁場』のもとで」(川島真・森聡編『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』東京大学出版会、2020年、に所収)がある。
2021.07.10
台頭する中国と米中関係(ゲスト:秋田浩之日本経済新聞社コメンテーター)

日本経済新聞社コメンテーター。1987年(昭和62年)入社。流通経済部、政治部、北京支局、ワシントン支局などを経て、2009年9月から、外交・安全保障担当の編集委員兼論説委員。2016年10~12月、英フィナンシャル・タイムズに出向し、「Leader Writing Team」で社説を担当した。2017年2月より現職。外交・安保分野を中心に、定期コメンタリーを執筆する。優れた国際報道に与えられる2018年度のボーン・上田記念国際記者賞を受賞。著書に、米中日関係の現状と行方を分析した「乱流 米中日安全保障三国志」(2016年 日本経済新聞出版社)、「暗流 米中日外交三国志」(2008年、同)がある。87年3月、自由学園最高学部卒。91年、米ボストン大学大学院修了(国際関係論)。2006~2007年、米ハーバード大学日米関係プログラム研究員。
2021.06.12
中東を地経学で読み解く(ゲスト:池内恵東京大学先端科学技術研究センター教授)
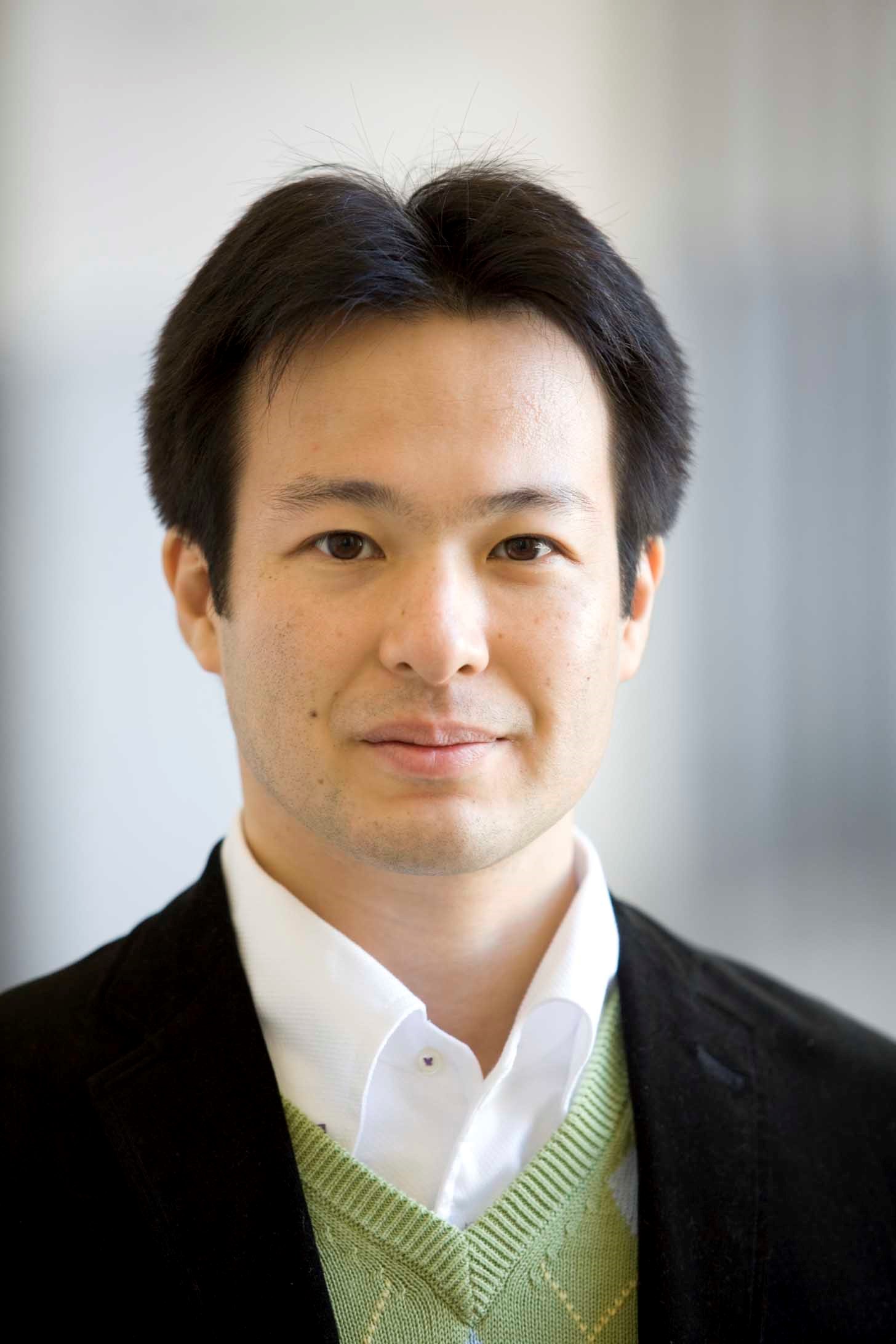
1973年東京生まれ。1996年東京大学文学部イスラム学科卒業、2001年に東京大学大学院総合文化研究科博士課程を単位取得退学し、アジア経済研究所に入所。国際日本文化研究センター助教授・准教授を経て、2008年10月より東京大学先端科学技術研究センター准教授(イスラム政治思想分野)、2018年10月より東京大学先端科学技術研究センター教授(グローバルセキュリティ・宗教分野)。ケンブリッジ大学客員研究員(2010年)、ウッドロー・ウィルソン国際学術センター客員研究員(2009年)、アレクサンドリア大学客員教授(2008年)等を歴任した。専攻はイスラーム政治思想史、中東地域研究。2016年に第12回中曽根康弘賞を受賞。
(おことわり)
地経学オンラインサロンで表明された内容や意見は、講演者やパネリストの個人的見解であり、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)や地経学研究所等、スピーカーの所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
 APIニュースレター 登録
APIニュースレター 登録