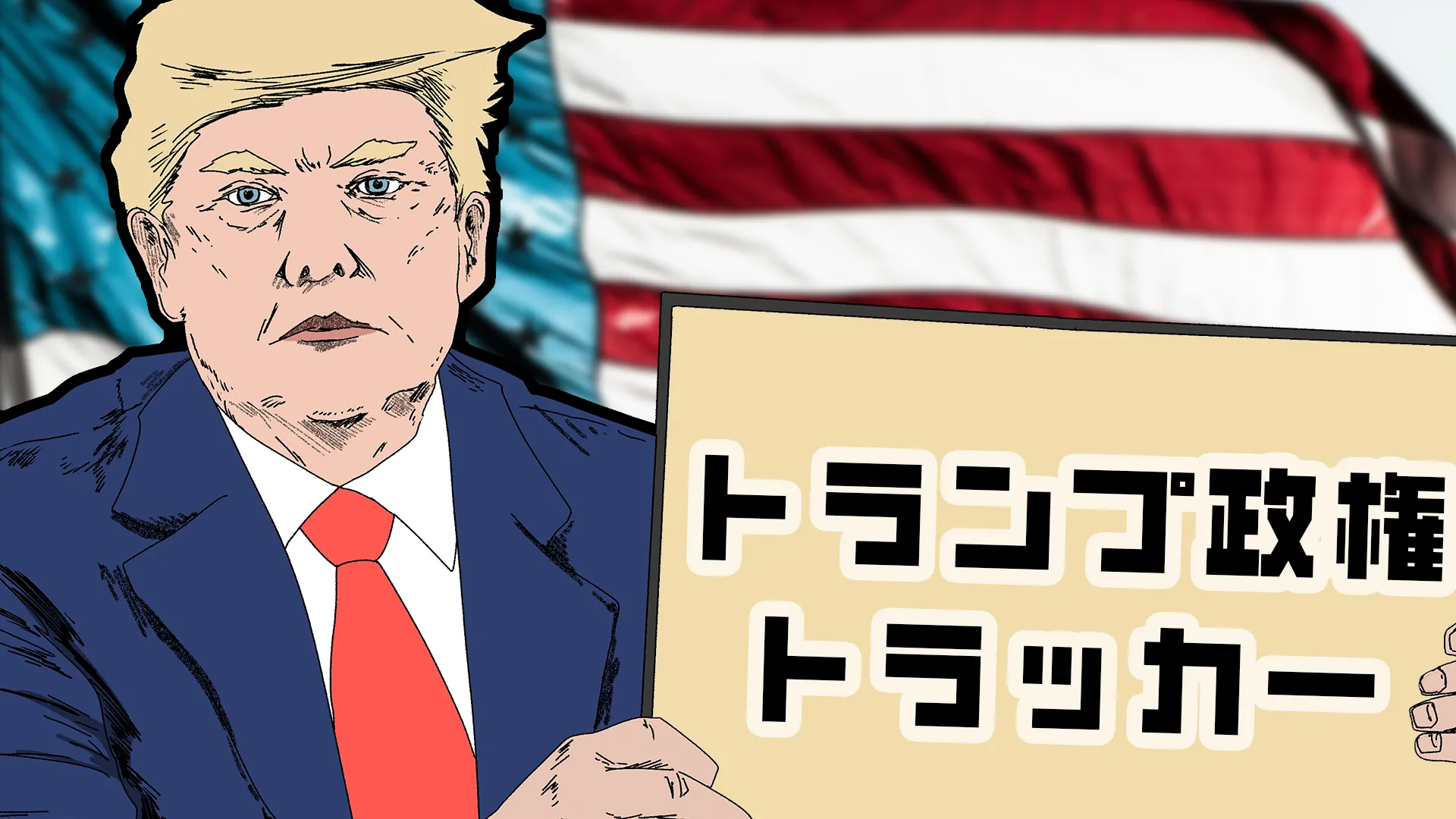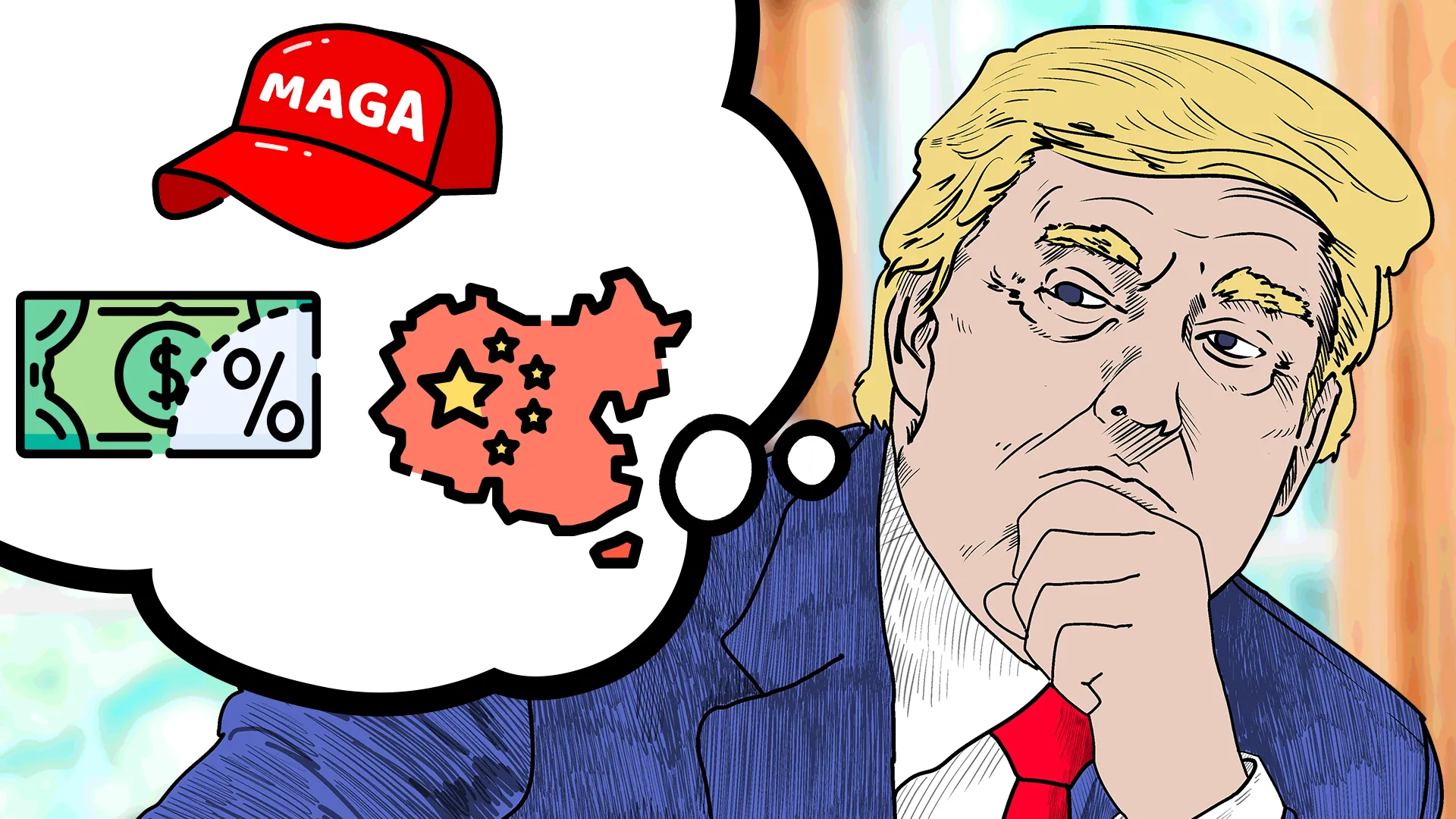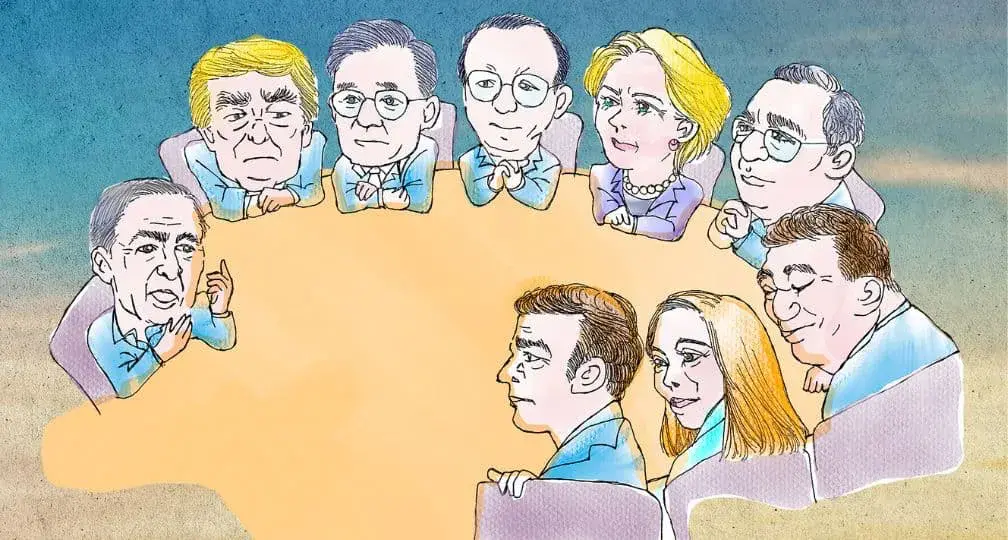露朝パートナーシップに対応した日米韓連携
欧州とインド太平洋を結び付ける露朝パートナーシップ
2024年6月14日、岸田総理がG7プーリア・サミットで表明したインド太平洋地域と欧州の安全保障が「不可分一体」であるとの認識は、皮肉にもその数日後、実体として裏付けられることとなった。6月19日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領が平壌を訪れ、金正恩総書記と共に「包括的戦略パートナーシップ条約」に署名したことが伝えられたからである。北朝鮮の朝鮮中央通信によると、同条約第4条では、「どちらか一方が、武力侵攻を受け、戦争状態になった場合、国連憲章第51条とそれぞれの国の法律に従い、遅滞なく保有する全ての手段で軍事的及びその他の援助を提供する」ことが規定されているという。
同条約は、1961年に締結され、1996年に失効したソ朝友好協力相互援助条約以来の軍事同盟条約となる。上記第4条の規定が、国連憲章第51条への言及やソ朝友好協力相互援助条約と同じ表現を用いていることを踏まえれば、少なくとも概念上、相互防衛義務を含み得るためだ。実際、北朝鮮がウクライナに部隊を派兵する可能性についても取り沙汰されている。一方で、当該条約は自動参戦義務を規定しているわけではないとの抑制的な見方もある。
そのような中で疑いがないのは、当面、同条約が相互の軍事援助や軍事協力強化の根拠として機能するという点だろう。ロシアにとっては、2023年9月頃から既に行われている北朝鮮からのKN-23(「火星11」)短距離弾道ミサイル等の弾道ミサイルや弾薬の提供の継続、そして北朝鮮にとっては、偵察衛星打ち上げに用いるエンジン技術を始めとする軍事技術支援の強化が期待される。
これらの目先の協力は、今回のパートナーシップ条約締結以前から事実上行われてきたものであるが、今回の条約によりそれらが中長期的なコミットメントへと発展していく可能性が指摘されている。特に、米国が対ウクライナ軍事援助を再開し、NATOもウクライナ支援を主導する構えを見せる中、安定的な協力関係の構築はロシアにとって少なくない意義をもたらす。また北朝鮮にとっても、ロシアからの継続的な技術支援は、制裁下にあって目標とする各種兵器開発事業を進める上で、効果的な手段となるだろう。
露朝の相対利得と中国の反応
しかし、プーチンと金正恩の間に温度差も見え隠れする。例えば、金正恩が露朝関係を「同盟」と表現したのに対し、プーチンは「北朝鮮との軍事技術協力を排除しない」と述べるにとどめた。通常「排除しない」という表現は、積極的に物事の可能性を認めたくない場合に用いるものと解するのが適当だろう。また、条約のテキストを真っ先に公表したのも朝鮮中央通信である。客観的な実態はどうあれ、少なくともロシア側の認識は、この条約からより多くを得るのは金正恩であるということなのかもしれない。
そのような認識が形成され得る理由は様々に考えられるが、その一つとしては、北朝鮮製武器の品質が低いというものがある。2024年5月、ウクライナ当局は、ロシアがウクライナに対して使用した北朝鮮製のKN-23のうち、およそ半数が発射後空中で機能不全となり爆発した旨を明らかにしている。KN-23は、ロシア地上軍が装備するイスカンデル短距離弾道ミサイルとの外観の類似が指摘されてきたが、その品質は本家には及ばない可能性が高い。この点、ロシアの技術支援が北朝鮮の品質管理能力を向上させることができれば、ロシアは北朝鮮を兵器庫として利用することもできるかもしれない。一方、そのような努力は現在進行形のウクライナ戦争において直ちに実を結ぶとは限らない。プーチンの慎重な発信は、そのような北朝鮮に対する冷めた値踏み姿勢の表れだろう。
さらに冷めた対応を示したのが中国である。中国外交部報道官は、露朝パートナーシップ条約の締結の受け止めを問われた際、「二国間の協力事案であり、論評しない」と述べた。2022年2月の中露首脳共同声明によりロシアとの「制限なき協力」を確認したはずの中国であったが、ウクライナ戦争の長期化により両国の間に一定の距離が生じている中、中露朝三か国間の結び付きを強化し得るはずの今回の動きを手放しで支持しなかったことは注目に値する。中国は1996年以来、中朝友好協力相互援助条約により北朝鮮に対して相互防衛のコミットメントを約束する唯一の国であったが、ロシアが同様のコミットメントを含む今般の条約を締結したことで、北朝鮮に対する自らの影響力低下を警戒している可能性も否めない。一方、だからと言って、中国が欧米や日韓と歩調を合わせて露朝連携を非難するほどの戦略転換に至るインセンティブも見出していない様子である。このため、露朝連携への対応に当たって、中国の役割に期待を寄せることは難しい。
日米韓の調査ミッションを欧州に派遣せよ
では、「差し迫った脅威」、「防衛上の強い懸念」(国家防衛戦略)とそれぞれを位置付ける北朝鮮、ロシアに囲まれた日本は、どう対応すべきだろうか。ロシアが何らかの見返りを期待して北朝鮮のミサイル開発能力を向上させるとすれば、それにより直接影響を受けるのはまず韓国、次いで日本である。日本としては、国際場裏や米国、韓国等と連携してパートナーシップ条約を非難することは当然必要だが、それだけでは十分ではない。具体的な対応が必要である。
この点、露朝両国が相互の軍事援助関係の発展を公に表明した以上、日本を含む関係国にも大手を振ってその関係性を精査する根拠を与えられたとも解することができる。そこで一つ考えられる行動が、日本を含む有志国が専門家の合同調査ミッションをポーランド等のウクライナ近隣に派遣し、ウクライナ当局の協力を得て北朝鮮製弾道ミサイルの残骸を分析することである。既に、民間の調査団体である紛争武器研究所(Conflict Armament Research: CAR)が、2024年1月にハルキウで回収された北朝鮮製ミサイルを分析し、その調査結果を発表した事例がある。当該調査では、北朝鮮が主に2021-2023年頃に製造された米国、ドイツ、日本などの民生部品を利用してミサイルを製造した可能性が示された。この調査は、北朝鮮製ミサイルのサプライチェーンを明らかにし、制裁の実効性に対する課題を投げかけた点で意義は大きい。しかし、当該調査は必ずしも北朝鮮のミサイルの能力、性能等を軍事的観点から分析したものではないため、その意味で十分とは言えない。一方、国連北朝鮮制裁専門家パネルの委員もウクライナを訪れ、北朝鮮製ミサイルの分析を行ったとされるが、2024年4月末でロシアの拒否権により同パネルは解散に追い込まれてしまった。
これに対し、日米韓等の防衛技術に関する政府専門家などによって構成する多国籍調査団を欧州に派遣すれば、北朝鮮のミサイルの脅威の度合い・能力に関する客観的評価に資する可能性がある。また、有志国により調査ミッションを組成するのであれば、安保理とは異なりロシアの拒否権を気にする必要もない。日本の国内法上も、防衛省であれば防衛省設置法上の「調査研究」の一環として可能であり、また経産省であれば外為法の実効性確保を根拠とすれば問題ない。調査によりどの程度有益な結果が得られるかは分からないが、少なくとも実施するためのハードルはそれほど高くはない。
日米韓を始めとする関係国は、今回の露朝パートナーシップ条約を、欧州方面から北朝鮮のミサイル能力を解剖する機会とすることができる。インド太平洋と欧州の安全保障が「不可分一体」であるとの声明を、単なるレトリックで終わらせる必要はない。



主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る