「地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。
https://toyokeizai.net/articles/-/617147
「地経学ブリーフィング」No.121

(画像提供:ロイター / アフロ)
2022年9月12日
ウクライナ戦争が古典的な戦いになった3つの訳 - テクノロジー、非軍事手段、戦争様態から考える
東京大学先端科学技術研究センター専任講師 小泉悠
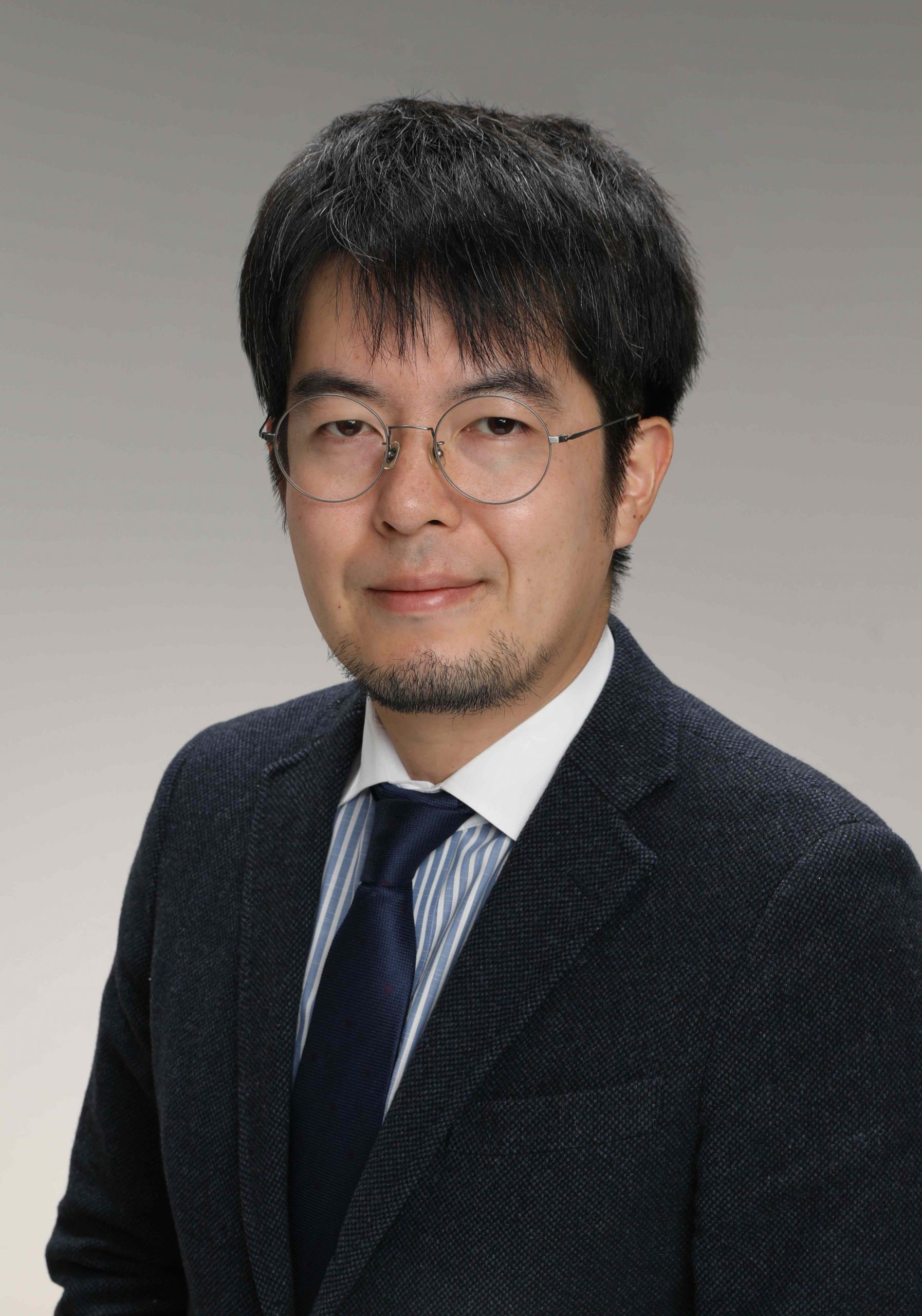
本稿は、今次のウクライナ戦争が古典的な戦争概念と大きく離れた非在来型の闘争……「新しい戦争」と言えるのかどうかを検討するものである。結論から言えば、ウクライナ戦争には非在来的要素が多々含まれるものの、戦場における大規模な暴力行使が闘争の趨勢を決するという点で、この戦争は古典的な戦争と見ることができる。
この点を明らかにするため、本稿では、①テクノロジー、②非軍事手段、③戦争様態の3つの側面からこの戦争のありようを検討した。そのうえで、この戦争はなぜ古典的なのか、日本の安全保障が汲み取るべき教訓は何か、といった点についても論じた。
テクノロジーが変える戦場:UAVを一例として
ウクライナ戦争には、2020年代初頭時点において想定しうる軍事テクノロジーがほとんど投入されている、と言ってよいだろう。
代表例は無人航空機(UAV)、いわゆるドローンである。中でも小型の戦術UAVはロシア・ウクライナ双方がほぼ標準装備として用いており、情報・監視・偵察(ISR)を担う。より大型で飛行性能やISR能力の高い中高度UAV(MALE)も双方が実戦投入しており、こちらは限定的に攻撃任務も担っているようだ。交戦国の双方が大規模にMALEを投入しあう戦争は、おそらく今回が初めてであろう。
さらにウクライナは民生用マイクロドローンによってごく近距離におけるISRを分散的に行ったり、アメリカから供与された徘徊型攻撃UAV(いわゆる自爆ドローン)でロシア軍の後方を打撃するという戦術を採用しており、UAV利用の幅という点ではロシアを凌ぐ。
ただし、現行のUAVは遠隔操縦型であるため、電子戦によって妨害可能であるし、有力な防空システムが存在する環境下でも活動を制約される。実際、ロシア軍が大規模な電子戦を開始すると、ウクライナ軍のUAVの平均寿命は1週間以下に落ち込んだ。他方、アメリカが高速対レーダーミサイル(HARM)をウクライナ軍に供与し始めると、ロシア軍の防空システムは次々と損害を受け、その間隙をついてウクライナのUAVや有人戦術航空機が活動できる余地が広がっていった。
この点からも明らかなように、UAV(あるいはその他の新テクノロジー)はそれ単独で戦闘の様相を一変させるというものではない。UAVが効果を発揮するためには、そのような環境を作り出す因子(エネーブラー)が必要なのであり、あるいはUAV自体がその他の軍事アセットのためのエネーブラーとして機能しているということである。
非軍事手段による「戦わない戦争」
2014年にロシアが行ったクリミア半島の強制併合やドンバス地方への軍事介入では、非軍事手段、特に情報戦の活用が注目を集めた。政変で成立した暫定政権はロシア系住民を弾圧するネオナチ集団である、政変自体が西側に操られている、ロシアに併合されれば生活がよくなる、といった情報が紛争地域の住民に浴びせかけられ、認識を操作したのである。また、ロシアはウクライナ各地のインフラに対して大規模なサイバー攻撃を仕掛け、オンライン化されたサービスの機能不全や停電といった事態を引き起こしてもいる。
翻って今回の戦争では、非軍事手段はあまり目立っていない。ロシア側は、ゼレンスキー政権がネオナチであるとか、密かに核兵器を開発しているといったナラティブを展開したものの、ウクライナ国民に幅広い動揺を引き起こすことはなかった。国民の間で偽情報に対する耐性ができていたことに加え、ロシアのSNSやマスコミが軒並みブロックされていたことがその主な要因として挙げられよう。また、ロシアが開戦前後に行った大規模サイバー攻撃も、結局はウクライナ社会に壊滅的な混乱をもたらすことはなかった。
一方、ウクライナ側は、国民と国際社会の支持を広く獲得することに成功している。被侵略側であるという道義的な正当性に加え、ゼレンスキー政権の巧みなメディア戦略がここで大きな役割を果たした。ただ、ウクライナの情報戦はロシア社会を揺るがし、プーチンに停戦を決断させるには至っていない。プーチン政権が進めてきた国内情報統制が効果を発揮している形であり、この意味でも情報戦の限界が改めて確認される。
戦争の様態
今回の戦争の様態は非常に古典的である。つまり、大量の兵士と火力を投入し、互いの軍事力を撃滅することで政治的意志の強要を目指す戦争、クラウゼヴィッツが「拡大された決闘」と呼んだ戦争だということである。実際、今回の戦争では、ウクライナ側が国民総動員令によって大量の戦時動員を行う一方、ロシア軍は新型から旧式に至るまでの多様な火砲・ロケット砲・ミサイルを大量に投入し、火力の優位を前面に押し立てて戦いを進めてきた。
ただ、開戦後半年以上を経ても、双方は依然として決定的な勝利を得ることができておらず、総延長2500kmに及ぶ戦線もまた顕著な変動を見せてはいない。その結果として出現したのは、長大な戦線を挟んで双方が消耗戦を繰り広げるという、第1次世界大戦の縮小版のような事態である。この間、ロシア側では7万~8万人の兵員が死傷したほか、1000両以上の戦車が破壊されたとされ、ウクライナ側の損害もおそらくはこれと同等か、それ以上であろう。
それでも戦争が継続できているのは、ロシア側が膨大な予備兵器を保有し、ウクライナ側は総動員による兵員の補充能力と西側からの軍事援助を得られているからにほかならない。
まとめるならば、ウクライナ戦争では兵力や火力、それらの補充能力といった古典的な要因が戦況を左右しているのであり、テクノロジーや非軍事手段・非国家主体という要素は(戦争の性質というマクロな視点に立つ限り)その従属変数と見たほうがよい、ということである。
「新しい戦争」とはならなかった
では、ウクライナ戦争はなぜ、古典的な戦争になったのだろうか。
革新的な軍事テクノロジーによって兵力や火力の多寡に関わらず勝敗が決まる戦争というビジョン、あるいは非軍事手段によって敵国を内部から瓦解させる戦争というビジョンは、古くから存在してきた。この点はロシアにおいても例外ではなく、参謀本部内では多くの「新しい戦争」のあり方が論じられてきた。
にもかかわらず、戦争の様相が古典的なものになった要因は3つ挙げられる。
第1に、2014年の戦争でロシアが用いた非軍事手段は、必ずしも期待通りの成果をもたらさなかった。元々ロシア系住民が多いクリミアやドンバスの一部地域を除いて住民の認識操作は成功せず、多くの地域はウクライナ政府の統治下に残ることを選んだのである。大規模な正規軍による侵攻という方法が選ばれたのは、これに対する反省であったのだろう。
第2に、ウクライナの抗戦意志の強固さが挙げられる。開戦後、ゼレンスキー大統領は首都に踏みとどまってロシアへの抵抗を呼びかけ、国民も概ねこれを支持した。この結果、ロシア軍は短期間で首都を占領してウクライナの国家体制を瓦解させることができず、その間に西側からの大規模軍事援助が始まったため、早期の勝利はより困難になった。
第3に、今回の戦争では、核抑止が機能している。ロシアは西側との直接対決を恐れて軍事援助を強制的な手段で排除することができず、逆に西側もウクライナに直接介入を行うことができていない。この結果、ロシアとウクライナは破滅的な核戦争にエスカレートするという可能性をひとまず脇に置き、持てる通常戦力すべてをぶつけ合う「限定全面戦争」を行うことができているのである。
以上のように、一定の条件下においては、現在の世界でも国家間の古典的な戦争は生起しうるのであって、わが国の安全保障を考えるうえでも貴重な教訓となろう。特に、激しい消耗に耐えながら戦い続けるための継戦能力はわが国の防衛体制における大きな弱点であると思われ、今後の防衛力整備における焦点となろう。これは弾薬の備蓄にとどまらず、防衛・民生用インフラの抗堪化・分散化・冗長化、それらの復旧能力の強化といった措置にも及ばねばならない。
古典的な戦争と「新しい戦争」の相関関係
また、ウクライナでの戦争が古典的なものであったとしても、「新しい戦争」に備えなくてもよいということにはならないだろう。戦争はある様態からまた別の様態に変遷していくのではなく、むしろ戦争という営みに際して選択可能なオプションが増加しているというふうに考えるべきだからである。
さらに言えば、古典的な戦争と「新しい戦争」の間には一定の相関関係がある。今回の戦争の場合、古典的な戦争を中心としつつも「新しい戦争」的要素は補助的な形で使用されているし、その逆であるとか、両者の要素が同じくらいの割合で併存しているとか、さまざまな戦争様態がありえよう。わが国としては、将来のこうした多様な戦争にどう備えるのか、限られたリソースの範囲内でそのうちの何を特に重点とするのかを真剣に考慮していくことが求められるのではないだろうか。
(おことわり)地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
最新の論考や研究活動について配信しています
 APIニュースレター 登録
APIニュースレター 登録