「API地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:細谷雄一API研究主幹 兼 慶應義塾大学法学部教授)。
本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。
https://toyokeizai.net/articles/-/433084
「API地経学ブリーフィング」No.57
2021年06月14日
日本と台湾「52年ぶりの出来事」に映る有事の備え―日米共同声明「台湾条項」の戦後史から考える
成蹊大学法学部教授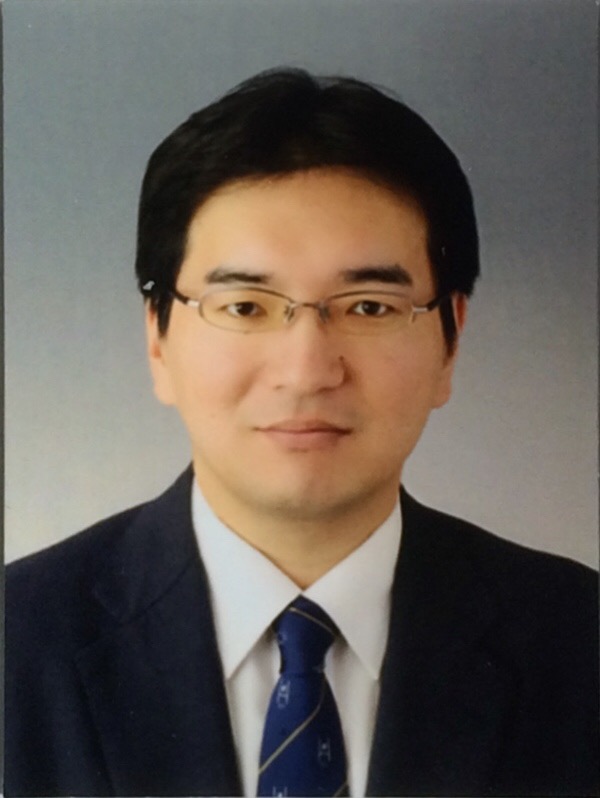
井上正也
半世紀以上もの間、共同声明に言及されてこなかった
2021年4月に行われた日米首脳会談で、「台湾海峡の平和と安定の重要性」と「両岸問題の平和的解決を促す」という文言を盛り込んだ共同声明が発表された。日米首脳間の共同声明に「台湾」が明記されるのは、1969年11月の日米共同声明において、「台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとってきわめて重要な要素である」という文言が盛り込まれた、いわゆる「台湾条項」以来、実に52年ぶりのことである。
今回の声明については、中国の軍事的脅威の増大を前に、台湾への武力行使に日米両国が共同で反対を表明した点で画期的だという評価もある。しかし、内容自体は従来からの日本政府見解の域を出ない。
それにしても、中国の軍事的脅威が唱えられて久しいにもかかわらず、なぜ半世紀以上もの間、「台湾」の存在が日米首脳間の共同声明に言及されてこなかったのであろうか。本稿では、歴史的文脈から、改めて今回の日米共同声明が持つ意義について考えてみたい。
台湾地域が日米安全保障条約(以下、安保条約)の適用対象であるか否かは、半世紀前においても敏感な政治問題であった。安保条約の対象地域は「フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下」にある「極東」と定義されている(1960年2月26日政府統一見解)。
しかし、1960年に改定された安保条約で、在日アメリカ軍が日本の外への「戦闘作戦行動(combat operation)」を行う際には、日米両国が前もって協議を行うという「事前協議制度」が設けられた。そのため、アメリカ側は、台湾有事が起こったとき、日本政府が事前協議で在日アメリカ軍の出撃を認めるかの確信を持てないでいた。
1969年11月の日米共同声明に盛り込まれた「台湾条項」は、沖縄返還後も、台湾有事における沖縄からのアメリカ軍出撃を、日本政府が政治的に担保する狙いがあった。中国政府の反発を懸念していた日本政府であったが、最終的には沖縄返還のバーターとして、台湾有事における在日アメリカ軍出撃の保証を行った。
ところが、日本が台湾の安全保障に関与することを明らかにした時期は、中国が国際社会に復帰する時期とも重なっていた。1971年の米中電撃接近の後、国際連合でも安保理常任理事国の議席が、台湾の中華民国政府から中国政府に入れ替わった。その前後から西側諸国も続々と中国との外交関係を樹立し始めていた。
中国政府が、西側諸国との国交樹立に際して求めたのは、台湾の中華民国政府との外交断絶と、台湾が中国の領土の一部であることを認めるという「一つの中国」の原則であった。そのため、日本政府も中国との国交正常化に踏み切る際に、安保条約の「台湾条項」をいかに扱うかが大きな問題になった。
アメリカと中国との狭間に立たされた日本政府の方針は、「台湾条項」をめぐる法律的な効力を維持したまま、中国側との間で台湾問題を政治的に処理するというものであった。日中国交正常化交渉がはじまる直前、日本政府はひそかにアメリカ政府に対して、もし台湾有事のときに在日アメリカ軍の出撃を拒否するように中国側が申し入れてきても、これに応じることはないと伝えている。
その一方で、中国側に対しては、日中国交正常化に際しての共同声明(1972年9月)で、「台湾は中国の領土の不可分の一部である」とする中国側の主張に、日本側が「理解」と「尊重」を示し、さらに台湾の中華民国(中国)への返還に触れた「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」(日中共同声明第三項)という政治的な歩み寄りを示した。
安保条約を適用する可能性を留保
中台対立の平和的解決を志向しつつも、台湾有事の際には安保条約を適用する可能性を留保した日本政府の立場は、現在に至るまでの政府見解の基礎となった。
もっとも、日本政府は、こうした姿勢を当初から戦略的にとっていたわけではない。日中国交正常化の前後、外務省でも意見は割れていた。「台湾条項」に手を加えることは日米安保体制の弱体化につながるという声がある一方、日米安保体制と日中関係の矛盾を解消するためには、同条項の削除や修正をアメリカ側に求めるべきだという声もあった。米中接近によってアメリカの台湾へのコミットメントが不透明になる中で、日本側としては明確な方針が立てられるはずもなかったのである。
また台湾問題を考えるうえで無視できないのは国内政治である。憲法問題が保革両陣営の一大争点であったように、中国政策(台湾問題)もまたしばしば自民党内の権力闘争と結びついた。
例えば、田中角栄と福田赳夫が激突した1972年の自民党総裁選は日中国交正常化が争点となり、国交正常化後も日中航空協定交渉をめぐって、親台湾派が大平正芳外相を激しく攻撃した。台湾問題と派閥対立の連動は、自派に親台湾派が多くいた福田赳夫首相が、党内合意を取り付けて、日中平和友好条約の締結に踏み切るまで続いた。このように台湾問題をめぐって出された玉虫色の政府見解は、戦略的意図に基づくものというより、国内政治のアウトプットによるところが大きかった。
中国の関心は対ソ包囲網に向けられた
とはいえ、日中国交正常化以降、安保条約に関わる「台湾条項」が再び争点に浮上することはなかった。最大の要因はアジアの国際情勢である。1970年代に米中関係のデタントが進展するなかで台湾有事の蓋然性が低くなった。さらに日本側の予想に反して、中国側も安保条約に関わる争点を対日交渉で持ち出さなくなった。中ソ対立が激化するなかで、中国の関心は日米安保体制から対ソ包囲網に向けられ、対ソ戦略での足並みを揃えることが国交正常化後の日中関係の新たな争点になった。
かくして、「台湾条項」は、それを有効とする解釈と、日中関係を尊重する立場から発動されることはないとする政治的立場の乖離が埋められないままとされた。かつて、国際政治学者の永井陽之助は、憲法九条の解釈を、内部エリートに向けられた説明である「密教」と、大衆に向けられた説明である「顕教」の二重構造からなると論じたが、「台湾条項」もまた同様の構図があった。
外務省条約局が国会対策用に緻密にくみあげた内部向け解釈と、台湾有事は起こりえないという前提に立った一般向け解釈の二重構造が長らく維持されたのである。
こうした構造に揺らぎが見えはじめたのは1990年代以降である。台湾の民主化が進み、台湾海峡危機が生じると改めて台湾有事の可能性が懸念されるようになった。同じ頃、日本では安保条約に基づく日米ガイドラインの見直しに伴って、周辺事態法の制定が進められていたが、この安保条約の「周辺事態」に台湾が含まれるのかが大きな議論となった。
自民党内でも加藤紘一幹事長が、ガイドラインは「中国を念頭においていない」と明言したのに対して、梶山静六内閣官房副長官は、台湾海峡が「周辺」に含まれるとの異なる認識を示した。外務省は「周辺事態」は地理的な概念ではないという解釈を示し、台湾海峡に安保条約が適用されるのかを明言しなかったが、そのことは台湾問題に対する日本政府の姿勢の曖昧性を改めて浮き彫りにした。
2021年4月の日米共同声明に議論を戻すと、「台湾」が明記された背景としては、中国の軍事拡大や、米中対決の激化もさることながら、台湾問題をめぐる日本の「政治的立場」を支えてきた自民党の親中派が力を失ったことも無視できない。
自民党において、田中派―経世会が圧倒的な影響力を誇った1980年代から1990年代初頭は、経済建設を目指す中国側とそれを支援する日本側との間で利害関係が一致した時代でもあった。経済協力をテコに日中間で構築された政治レベルのパイプは、日中関係の悪化を防ぐ歯止めになってきた。
しかし、1990年代後半から進められた政治改革・統治機構改革のなかで、自民党内の派閥は弱体化し、日本の対中政策決定の中心も非公式ルートから首相官邸へと移った。これまで政府内だけで了解されていた内部向け解釈が、オープンの場で語られるようになった背景には、対中政策をめぐる国内政治のバランスの変化があるといえよう。
日本に求められる能動的な働きかけ
とはいえ、台湾問題をめぐる日本政府の立場が根本的に変化したわけではない。「台湾海峡の平和と安定を求める」という立場は、この半世紀における日本の一貫した主張である。日本に求められるのは、この台湾問題の「平和的解決」に向けて、いかに能動的に働きかけられるかであろう。
日米同盟の実効性を高め、中国への抑止力を強化することは不可欠であるが、日本有事へと直結する台湾有事が現実のものとならないために、中国との間で政治レベルでの信頼醸成を再構築することも重要である。「台湾条項」をめぐる戦後日本の対応は、一見矛盾するかのような日米同盟と日中提携を両立させてきた歴史でもある。こうした対中外交を支えてきたのは、さまざまな矛盾や対立を抱えながら、大局的見地に立った政治指導者たちであった。約半世紀ぶりに日米共同声明で「台湾」が明記されるなかで、日本外交にも積極的な役割が求められているといえよう。
(おことわり)
API地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)やAPI地経学研究所等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
最新の論考や研究活動について配信しています
 APIニュースレター 登録
APIニュースレター 登録