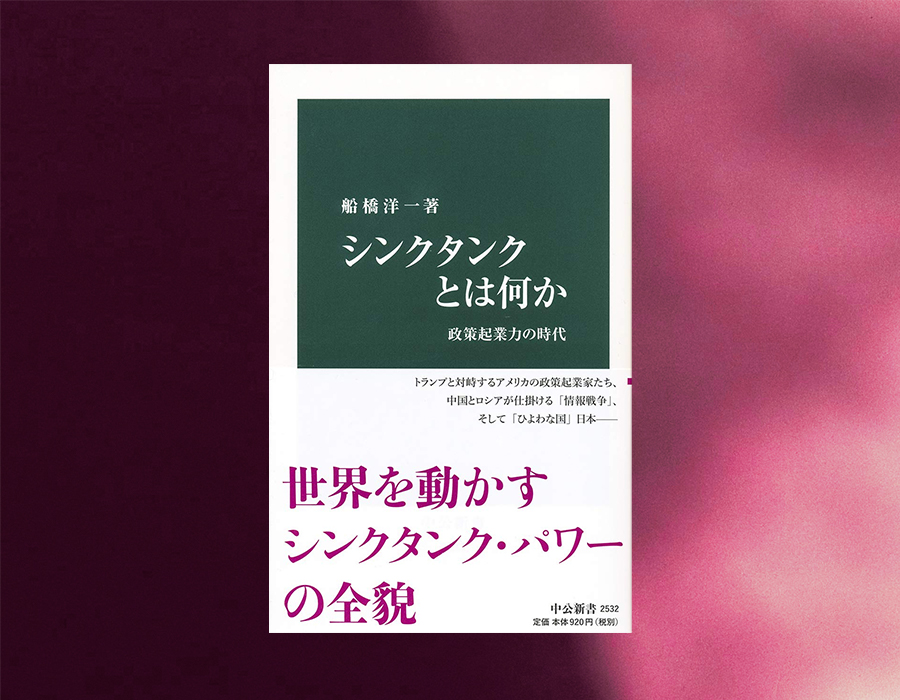船橋洋一『シンクタンクとは何か』(中公新書、2019年)より一部転載
第2章 米国シンクタンクの政策起業力

米国のシンクタンクが持つ政策起業力とはどういうものなのか。
政策起業力の現場をこれから見ていきたい。
ここでは、米国を代表するシンクタンクであるカーネギー国際平和財団(CEIP)、ブルッキングス研究所、外交問題評議会(CFR)、ランド(RAND)、戦略国際問題研究所(CSIS)、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)を取り上げることにする。ブルッキングス研究所を除いては、いずれも外交・安保・国際経済を主たる分野とするトップ・シンクタンクである。
カーネギー国際平和財団と不戦・平和
このうちもっとも古いのは一九一〇年に設立されたカーネギー国際平和財団(Carnegie Endowment for International Peace)である。カーネギー国際平和財団は、鉄鋼王のアンドリュー・カーネギーが国際平和を実現するという理想を実現するため、一〇〇〇万ドルの大金を投じて、つくった。現在の貨幣価値でいえば、約二・七億ドルである。
カーネギーは基金を提供するに当たって、その目的を明確にしている。
「国家間の戦争、我々の文明のもっとも穢れた汚点である戦争、を一刻もはやく廃止すること」
カーネギーの親友であり国務長官を務めたイライヒュー・ルートが初代の所長となった。ルートが最初に手がけたプロジェクトが「戦争の原因とその予防策に関する科学的研究」だった。その研究は、国際紛争を解決する手段としての戦争放棄を規定した不戦条約の成立(一九二八年)につながった。
不戦条約は、米国のフランク・ケロッグ国務長官とフランスのアリスティード・ブリアン外相が主導し締結された多国間条約であるが、その原案をまとめた法律家たちのうちの一人がジェームズ・ショットウェルだった。ショットウェルは、当時コロンビア大学総長と同財団理事長を兼務していたニコラス・マレイ・バトラーの勧めで、財団のプロジェクトに参加、バトラーとともに不戦条約成立のために奔走した。
国際連盟体制下、戦争を違法とした不戦条約の締結にもかかわらず、その後、日本の満州事変、イタリアのエチオピア侵攻、ドイツのポーランド侵略など武力侵略が激発した。
しかし、その理念は国際連合憲章に盛り込まれ、国際平和の基本的な原則として認知されることになった。
「ジェノサイド」という概念を世に出し、ユダヤ人虐殺を告発する上でカーネギー国際平和財団が果たした役割は大きい。「ジェノサイド」の概念は、ユダヤ系ポーランド人ラファエル・レムキンが一九四四年、カーネギーから刊行した『占領下欧州における枢軸国の支配』で示した。この概念は、ドイツの戦争犯罪を裁いた戦後のニュルンベルク裁判において犯罪要件として認知されることになる。
カーネギー国際平和財団の戦後の代表的プロジェクトは、「核不拡散・核なき世界」に向けての長年にわたるアジェンダ形成とアイデア発信である。
一九八五年、財団の先任研究員だったレナード・S・スペクターは『新核国家』を出版し、核物質や核技術のグローバル不法取引ネットワークの詳細を明かした。スペクターは、この本の中で、パキスタンの核技術者、アブドゥル・カディール・カーンが、勤務先のウレンコ(URENCO)社のウラン濃縮に関する機密情報をオランダ人の上司から盗み出し、米国、カナダなどから不法に技術を手に入れつつ、ウラン濃縮プログラムをパキスタンで指揮していることを暴露した。スペクターはさらに、核拡散により核テロリズムの脅威が高まっていると見て、中東を中心とする国々が潜在的敵対者の核施設に対して先制攻撃するリスクに注意を呼びかけた。
二一世紀に入ってからもジェシカ・マシューズ理事長の下、カーネギー国際平和財団は、この分野で野心的な取り組みを続けている。財団が二〇〇五年に刊行した、『普遍的順守──核セキュリティのための戦略』もその一つである。
そこでは、米国をはじめ核保有国が核なき世界と核軍縮への取り組みを真摯に行っていないことが、核不拡散にとっての大きな障壁になっていると指摘し、「米国が自ら身を正さないまま、他国のお行儀がよくなることを期待するのは非現実的である」と米国政府の姿勢を厳しく批判した。報告書は、「米国は、核不拡散条約(NPT)のもともとの約束事である、核兵器の全廃に向けて再び真剣に取り組むため先頭に立て」と促した。
これは、その後のいわゆる〝四賢人〟(ヘンリー・キッシンジャー、ジョージ・シュルツ、ウィリアム・ペリー、サム・ナン)の核全廃論アピールにも影響を及ぼし、さらにはオバマ大統領の「核なき世界」のプラハ演説へとつながる論理の枠組みを用意した研究とされている。キッシンジャーとシュルツはそれぞれフォード政権とレーガン政権の国務長官を、ペリーはクリントン政権の国防長官、ナンは上院議員として上院軍事委員会委員長を務めた。
カーネギー国際核政策会議(Carnegie International Nuclear Policy Conference)は、核/原子力問題においてもっとも権威のある国際会議の一つとなっている。これは、二年に一度開催。四五を超える国や国際機関から八〇〇名以上の専門家と関係者が集まり、核兵器不拡散条約のこれからの課題、世界的な核秩序、核抑止力、核軍縮、核不拡散、核セキュリティー、さらには原子力エネルギーの問題について議論する場である
ジェシカ・マシューズ理事長時代のカーネギー国際平和財団について、一言、言及しておかなければならないことがある。イラク戦争に当たってワシントンのほとんどのシンクタンクが戦争支持を打ち出した中で、同財団は戦争反対の論理と立場を明確にしたことである。「不戦と平和」のカーネギー国際平和財団の面目躍如の決断だった。
外交問題評議会と『フォーリン・アフェアーズ』
第一次世界大戦を契機とする米国の国際的な地位向上に伴う国際主義の広がりを反映して生まれたもう一つのシンクタンクが、外交問題評議会(Council on Foreign Relations:CFR)である。
こちらは、ウッドロー・ウィルソン大統領がベルサイユ講和条約を締結し、国際連盟を設立するためにつくった助言者集団である「インクワイアリー」(大調査)に起源を発する。
「インクワイアリー」はウィルソンの懐刀のエドワード・ハウス大佐が組織した頭脳集団であり、一〇〇人以上の研究者で構成された。後に二〇世紀の米国を代表するジャーナリストとなるウォルター・リップマンも先に触れたショットウェルもそのメンバーだった。メンバーの何人かは、パリ講和会議に出席するウィルソンに随行し、現地で英国側代表団のメンバーと親交を結んだ。そこから、英米が主導し、戦後の世界秩序を構築するため、それを政策面から支援する研究機関を共同で創設しようという大西洋主義ビジョンが湧きだした。
この構想自体は実らなかったが、英国側は一九二〇年に王立国際問題研究所(チャタム・ハウス)を設立。また、資金難から設立が難航していた米国側も翌一九二一年に「大調査」グループと、イライヒュー・ルート前国務長官が主宰していたニューヨークの実業家との国際情勢懇話会のメンバーが合流し、外交問題評議会を創設した。
外交問題評議会は一九二二年、専門知識の普及と党派を超えた政策対話の実現を目指し、外交専門誌『フォーリン・アフェアーズ』誌を創刊する。雑誌発行の実務と編集を取り仕切ったのはハミルトン・フィッシュ・アームストロング。彼もまたベルサイユ講和条約の米代表団に加わった一人だった。『フォーリン・アフェアーズ』はその後、世界の外交専門家のバイブルとなり、外交政策の上でもっとも影響力のある雑誌であり続けている。世界のシンクタンクの中で、これほど強大な影響力を持つ刊行物を手にしているところは他にない。『フォーリン・アフェアーズ』は、外交問題評議会のシンクタンク・パワーそのものといってよい。
外交問題評議会の本部は、ニューヨークのアッパーイーストサイドにある四階建ての格式豊かなハロルド・プラット・ハウスである。現在では結婚式場としても使われているが、もともとは、一九四五年に同評議会に寄贈された邸宅である。ここに政府関係者や研究者らが集い、とくに冷戦期、アメリカの外交政策に関するさまざまな議論が交わされた。
評議会は政府からの独立、特定の党派からの中立を謳っており、ホワイトハウスの具体的な政策決定にその名前が登場することを意識的に避けている。しかし、ここで開催された数々の会議やフォーラムで交わされた政策論議は、アメリカ外交政策に大きな影響を与えてきた。
日本の戦後計画の青写真
評議会が米国の外交政策へと影響を及ぼすきっかけとなったのは、第二次世界大戦の開始後の「戦争・平和研究」(WPS:War and Peace Studies)と名づけたプロジェクトだった。
これは、太平洋戦争で日本に勝利した後の日本の戦後計画の青写真をつくる研究である。
国務省側の対日戦後計画作成のブレーンの一人がジョージ・ブレイクスリーだった。彼は日本語を解さなかったが、日本に深い造詣を持っていた。戦後、日本を国際貿易の枠組みの中に入れ、日本の経済の回復と成長が平和と安定のカギであると信じていた。
当時の米国はまだ日本と死闘を演じている時であり、こうした〝ソフト・ピース〟論を主張するのは時局柄注意を要したが、ブレイクスリーは持論を正面から展開した。彼はまた、『フォーリン・アフェアーズ』にそうした論旨の論文を投稿したが、フィッシュ編集長は掲載を拒否した。日本に「優しすぎる」というのが理由だった。日本の軍国主義の原因を、日本が国際貿易で差別されたことに求めると、いまの戦争は米国が悪いからだと主張していると誤解されるおそれがある──との点をフィッシュは懸念した。
一九四四年、「戦争・平和研究」グループは「日本に対する安全保障政策」と題する政策提言メモを作成、国務省に送付した。日本を完全に武装解除した上で、産業を統制することで「二等国」とする内容だった。「戦争・平和研究」グループは日本の降伏後、解散した。しかし、グループに何らかの形で参画した人々のうち実際に日本で占領の政策と行政を担当した者もおり、評議会の影響力は永続的な性格を帯びることになった。
マーシャル・プランと「封じ込め」
戦後も、外交問題評議会の国務省に対する政策企画研究の面での支援は続いた。その中には、米国による欧州復興計画(通称マーシャル・プラン)への関与がある。評議会は一九四六年、ドイツ問題研究会を設置し、ドイツの復興計画の基本的方針の提言を発表した。提言の方針は、経済復興を推し進めることで戦後ドイツを立て直そうというもので、経済復興をヨーロッパ統合や安全保障政策と絡めたパッケージとする欧州復興計画として結実する。これは、その後のマーシャル・プランの先駆けだった。実際、トルーマン政権がマーシャル・プラン委員会を設立した時、評議会の研究員が多数、参画した。同委員会のメンバー一九名中八名までが評議会の研究員だった。
冷戦期の米国と西側の根本的な戦略概念となった対ソ・対共産主義「封じ込め」政策も、もとはといえば、米国のソ連専門外交官だったジョージ・ケナンが一九四七年一月七日、ハロルド・プラット・ハウスで行われた〝ソ連の外交関係〟に関する討議の場で発表した考え方だった。討議に出席していた国際銀行家の一人がケナンにその構想を『フォーリン・アフェアーズ』誌に寄稿することを勧め、アームストロング同誌編集長が寄稿を依頼した。ケナンは当初、当時の米国海軍長官だったジェームズ・フォレスタルに対して送った 報告書(「ソ連外交の心理的背景〔The Psychological Background of Soviet Foreign Policy〕」)を同誌に投稿したのだが、フォレスタルはその報告書を高く評価して、米国国務長官ジョージ・マーシャルに提出した。そのため、この報告書は公式文書となってしまった。そこで、ケナンはフォレスタルに許可を取り、自分の名前の代わりに〝X〟という筆名を使い、その報告書を投稿した。これがいわゆるX論文である。
論文は、「ソ連の脅威は、常に変化する地政学的かつ政治的な分岐点におけるカウンター・フォース(対抗力)を巧妙に、また機敏に適用することで封じ込めることができる」と主張し、ユーラシア大陸の東西の戦略的重要拠点(とくに英・独・日などのパワー・センターと呼ばれる各国)に経済・軍事援助を与え、ソ連の勢力膨張を長期にわたり封じ込め、ソ連の内部崩壊を生じさせるべきだと説いた。
ヘンリー・キッシンジャー元国務長官も、若いころ評議会で政策研究に従事した一人である。ハーバード大学で博士課程を取得した後、一九五〇年代からここの活動に参加するようになった。キッシンジャーは核戦略を中心に研究し、その成果は一九五七年に刊行した『核兵器と外交政策』に結実した。この本は、外交に関する本としては珍しくベストセラーとなり、キッシンジャーの名前を一躍、広く知らしめることになった。キッシンジャーはその後、ニクソン政権の大統領補佐官(国家安全保障担当:NSA)に就任したが、アカデミックから政策立案者へと転身するきっかけは、評議会での政策研究だった。
外交問題評議会は、戦後の米外交の節目で、政策当局者が「新政策」を打ち出す際の格好の舞台を提供してきた。一九五四年ジョン・フォスター・ダレス国務長官が、アイゼンハワー政権の軍事戦略について「大量報復戦略を最優先とする」と宣言したのは、評議会で開かれた夕食会の後のスピーチだった。演説はその後、論文の形に編集され、『フォーリン・アフェアーズ』に掲載された。
評議会は大戦期から現在まで、外交政策形成に必要なアイデアと人材を政府に供給するとともに、政府の要職にあった人材を受け入れ、政策研究に、政策形成の現場のリアリズムを注入している。レスリー・ゲルブ元理事長(在任一九九三~二〇〇〇年)がかつて記したように、「CFRは米国の国益を踏まえた国際主義を代表している」のである。
評議会のシンクタンク機能の中核にあるデイビッド・ロックフェラー・スタディー・プログラムには、現在、七〇人を超える専門家が集い、外交・安全保障・国際経済・貿易・気候変動などの分野での研究と政策提言を行っている。政府要職者や官僚だけでなく、ウォール街はじめ経営者や実務家との不断の対話を行っていることも、評議会の強みである。有名なのはCEOスピーカー・プログラムである。これは、企業会員向けプログラムの一環だが、全米の一四〇(二〇一八年二月現在)の企業をメンバーとし、主にそれらの企業のトップ経営者と直接、意見交換するプログラムである。もっともランクの高い企業メンバーである「ファウンダー」のカテゴリには、グーグル、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、エクソンモービルなどのグローバル企業が名を連ねている。これだけの企業をネットワークし、そのトップに直接、ニューヨークまで来てもらい、ビジネスと「政府の政策決定者、メディア、NGO、アカデミアをつなぎ」、外交問題について意見交換すること、つまりは政策に関する「議論の場を主宰する力(convening power)」もまた、外交問題評議会の政策起業力の源泉となっている。
ブルッキングス研究所と大恐慌
ブルッキングス研究所(The Brookings Institute)も、第一次世界大戦を境に米国内で広がった科学的政策研究と進歩主義を背景に生まれたシンクタンクである。
このシンクタンクは、海外では外交・安全保障のシンクタンクとして知られるが、もともとは経済、なかでも財政・金融政策を重点的に研究した。その前身は、行政府の予算改革に貢献した政府調査研究所(一九一六年設立)をはじめとする、複数の調査機関である。
ブルッキングス研究所を一躍、米国を代表するシンクタンクにしたのは一九三〇年代の大恐慌時代に発表した米国経済の制度改革に関するさまざまな提言だった。
一九二九年一〇月、ウォール街の株価大暴落に端を発し、世界恐慌が起こった。
一九三二年の米大統領選挙で、民主党のフランクリン・ルーズベルトが共和党のハーバート・フーヴァーを破り、大統領に選出された。共和党が唱えていた自由放任ではもはや人々に雇用の場を与えられない。経済を救えない。ルーズベルトは、政府が市場に対して限定的に介入することで経済の立て直しを図ると宣言し、国民の支持を得た。
当時、ブルッキングスの所長は、シカゴ大学教授出身でエコノミストのハロルド・モールトン。モールトンは、ルーズベルトを支持していた。政権の「均衡の取れた、予算と政府経済」という経済政策方針が、モールトンはじめブルッキングスの研究者の見解に沿うものだったからである。一九三二年、創設者のロバート・ブルッキングスが死去すると、ルーズベルトの叔父であるフレデリック・デラーノが会長の座についた。こうした経緯から、ブルッキングス研究所はルーズベルト政権に近く、また、大きな影響力を行使すると思われていた。実際、大統領の就任直後から、ブルッキングス研究所のスタッフは財務省主計局や商務省に対して、予算の削減や産業再編についての助言を行っていた。
一九三三年、モールトンは全国産業復興法案に関する法案をつくる法案起草委員会に参加、ニューディール政策の立案過程に深く関与するようになる。その後も、いくつかの州政府に対するコスト削減案や税制についての助言、さらには商工会議所やアメリカ労働総同盟への助言を行うなど活動範囲を拡大した。それとともに、大恐慌の根本原因を検証、分析するプログラムを立ち上げ、一九三三~三五年にかけて全四巻からなる報告書(通称“Capacity Studies”)を刊行した。報告書は、大企業のカルテルやトラスト形成、投機や事業合併へと向かった資本集中を厳しく批判。これらの阻害要因によって生産能力が有効に使われていなかったことが、給与や利潤の格差拡大の原因となったと主張した。報告書の最終巻は一〇万部も売れたといわれる。ジャーナリストのリップマンは「大恐慌を通じて、米国で行われたもっとも役に立った経済研究」と高く評価した。
ただ、ルーズベルト大統領のニューディールはその後、一段とリベラル色を強め、それまで支持していた中道保守からは「社会主義的」との批判を浴びるようになる。モールトンもそうしたルーズベルトの左旋回に警戒感を抱いた。一九三四年、『米国復興局──分析と評価』と題する論文を出版し、米国復興局(NRA)の運営に関する実態を検証した。そして、NRAが市場メカニズムに対して過剰に干渉しており、経済の回復を促すどころか、それを妨げていると批判した。この論文は、大きな社会的反響を呼び、ルーズベルト政権はNRAの再検討を行うなど対応を迫られた。一九三六年以降、ルーズベルト政権に批判的な論文を立て続けに発表、ニューディール政策に対する批判的姿勢を強めていった。これが原因で、一九三七年にデラーノは会長を辞職している。
もっとも、ブルッキングス研究所は組織としてはニューディール政策に批判的な立場を取ったものの、中心的な研究者であったヘンリー・サイードマンが農業調整局(AAA)で働くなど、一九三〇年代末までに約六五人のスタッフがルーズベルト政権に政治任命された。
「ガバナンスの改善が仕事」
戦後もブルッキングス研究所は、歴代政権に多数の人材を政治任命者として送り込み、また、政権交代に伴い前政権の有力高官を政策プロとして迎え入れてきた。
時代はずっと下るが、私が在籍した二〇〇五~〇六年当時は、クリントン政権の外交政策の要だったストロブ・タルボット(国務副長官)とジェームズ・スタインバーグ(国家安全保障問題担当大統領次席補佐官)が理事長、副理事長を務めていた。研究員の中には、スーザン・ライス、ジェフリー・ベーダーなど、オバマ政権誕生とともに政権入りした者も多かった。
ブルッキングス研究所は、超党派の立場を取っているが、一般にはリベラル系のシンクタンと見なされている。そうした見方はニクソン政権の時から、生まれたようである。
保守派のニクソンはブルッキングス研究所をリベラルの牙城と見なし、毛嫌いした。補佐官に「ブルッキングスに侵入して、連中のベトナムファイルを盗み出してこられないか」と言ったり、別の補佐官に「ブルッキングスを爆破し、その混乱に乗じてFBIのエージェントにファイルを持ち出させることはできないか」と相談したりした。ニクソンはかの有名な「エネミー・リスト(政敵一覧)」に同研究所を含めている。
私は一度、タルボットに、ブルッキングス研究所の戦後のプログラムの中で「これはと思う取り組み」を尋ねたことがある。
タルボットの回答は次のようなものだった。
1 国際連合と欧州復興計画(マーシャル・プラン)に関する構想。
国際連合については、ブルッキングスの研究員からコーデル・ハル国務長官補佐官に転じたレオ・パスボルスキーが、戦後の国際組織構築の研究のため、戦後対外政策諮問委員会を発足させ、国際連合憲章に示される基本的枠組みを構想した。それは、ダンバートン・オークス会議で採用されることになる。
2 ブルッキングス研究所シニア・フェローだったアリス・リブリンが提案した米議会予算局(Congressional Budget Office)構想。
これはブルッキングス研究所の『国家の優先順位の設定』シリーズの一環として提案したものだが、一九七四年の議会予算局の新設につながった。提案者のリブリンは、その初代局長に就任した。
3 ジェームズ・スタインバーグとマイケル・オハンロンが九・一一後に立案した対テロ戦略構想。
『米国本土の防衛──基礎的分析』などの著作が中心。これは、対外的な防衛に軸足を置いたブッシュ政権の国土安全保障政策の弱点を指摘しつつ、国内でのテロ活動の抑止やテロ対象となりうる場所の防御も含めた、より包括的な国土安全保障政策を提案したものである。
二〇一六年に創立一〇〇周年を迎えたブルッキングスは、さらなる一〇〇年先を見据えて長期的な展望を示すプロジェクト「Brookings 2.0」を開始し、自らの役割を再定義している。
タルボット理事長は、その際、研究所の研究の主たる照準を「二一世紀のガバナンスの複雑さを理解し、現実に生かすことのできるアイデアを育む」ことに置いた。「シンプルに言えば、我々はガバナンスの改善を仕事としているのだ」。
先に述べたように、ブルッキングス研究所はもともと金融・財政分野のシンクタンクとして発足したいきさつから、いまでもこの分野の活動は分厚いし、研究者に多彩な人材をそろえている。
米連邦準備制度理事会(FRB)議長だったベン・バーナンキを退任後直ちに、名誉客員研究員として引き抜いたのもその表れである。バーナンキはブルッキングス研究所のウェブサイトに自らのブログを開設し、精力的に発信を始めた。
「また民間人に戻ってきました。FEDウォッチャー(投資判断の重要な要素として金融政策の方向をつねに注視し、それをビジネスとしている人々)だけがわかる隠語のような言葉を使わずに、経済と金融の問題についてもっとコメントできます」
バーナンキはブログ・デビューに当たって、そんなコメントを発した。
「そのような形で市民を教育できればと思います。そしてこちらも何かを学びたいと思います」
バーナンキに限らず、英米では中央銀行総裁や金融監督庁総裁の経験者がシンクタンクを足場に、それらの機構の組織利害を離れ、一人の識者として発言を続けているケースが多い。中央銀行総裁経験者が金融政策につき実務家としての経験を踏まえ、大所高所からの御意見番として活躍する、そうした場をシンクタンクは提供している。
ところで、カーネギー国際平和財団、外交問題評議会、ブルッキングス研究所はいずれも戦前に生まれたシンクタンクの老舗である。
次に、戦後に生まれたトップクラスのシンクタンクを見てみたい。
ここでは、ランド(RAND)、戦略国際問題研究所(CSIS)、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)を取り上げる。
ランドと米空軍
一九四六年、米空軍と航空機メーカーのダグラス社は、「第二次世界大戦中に行われた科学研究の知見を戦後(平時)においても維持・発展させる」ための研究プロジェクト(Research AND Development:RAND)を協同で発足させた。中心となったのは第二次世界大戦の英雄であったヘンリー・アーノルド元帥だった。
「米空軍の父」といわれるアーノルドは、ライト兄弟から飛行機の操縦方法を習ったというパイロットの先駆けで、米陸軍に入隊して揺籃期の航空部を最初から育て上げた。空軍パワーの強化に力を入れ、第二次世界大戦は集中爆撃も含めて圧倒的な制空権の確保によって連合軍を勝利に導いた航空軍司令官として知られる。空軍では初の元帥になった。
空軍司令官時代には、科学担当の顧問を起用し、戦時中の軍と民間の密接な共同研究開発協力を、平時においても持続的に発展させなければならないという考えの下、「科学諮問グループ」を発足させた。外部の科学者が参加して政策判断を速めることを企図した頭脳集団だった。
アーノルドは、諮問委員会と並行して、民間企業と協同して次世代兵器を開発する計画に着手した。大陸間誘導ミサイルの開発が可能かどうかダグラス社にアプローチし、そこからランド計画が生まれた。アーノルドは、このランド計画をダグラス社から独立させ、非営利の研究機関、RANDを設立した。
ランドは当初は、主に米空軍の委託研究を行った。研究に対しては、フォード財団が潤沢な資金を提供した。フォード財団を率いていたのは、マーシャル・プランの実施機関である経済協力局の局長を務め上げた後、同財団理事長に就任したポール・ホフマンだった。ホフマンは、ランドへの財政支援や相互の人事交流を進めた。
ランドは、「国家安全保障上の脅威に対する上で必要な解は外交よりむしろ科学にある」という組織哲学に基づき、定量的・数理理論に基づく研究を得意とした(それゆえ、しばしば数値至上主義と批判された)。そして、核抑止論、合理的選択論、ゲーム理論、システム分析、ゼロサムゲーム、フェイルセーフ、囚人のジレンマ、といった独創的なアイデアと先進的な理論を次々と世に出した。一九五〇年代ごろまでに、〝冷戦の戦士のためのアイデアの宝庫〟との評価を確立し、五〇年代後半には戦略空軍司令部(SAC)と空軍の〝頭脳〟となった。
ランドの数多くの研究のうちで、名高いものは、人工衛星に関する研究がある。ランドは一九四六年の段階で、「地球を回る実験用宇宙船の初歩的デザイン」という報告書を発表し、宇宙時代の到来や人工衛星の機能を予見した。ところが、最初に人工衛星を打ち上げたのはソ連だった。一九五七年のスプートニク・ショックである。
〝防衛知識人〟たち
ランドの研究員は、ランダイトと呼ばれ、畏怖と敬意を持たれる存在となった。歴代のランダイトから二九名のノーベル賞受賞者を輩出した。
ランダイトの中には、数学者のジョン・フォン・ノイマン(ゲーム理論、ゼロサム理論)とジョン・ナッシュ(ゲーム理論)、コンピューター科学者のジェームズ・ギログリーとアレン・ニューエル、経済学者のケネス・アロー(合理的選択論)、トマス・シェリング(コミットメント理論および各種抑止戦略)、ハーバート・サイモン、物理学者のエドワード・テラーとブルーノ・オーゲンスタインらがいる。
なかでも、ジョン・フォン・ノイマンがランドを飛躍させる上で果たした役割は大きい。ノイマンは、ハンガリー生まれ。ナチスドイツの難を逃れて第二次世界大戦前に米国に移住。彼は、同じプリンストン高等研究所に在籍したアルバート・アインシュタインから「考える動物」と形容されたほどの知の巨人だった。ノイマンを一躍有名にしたのは、一九四四年にオスカー・モーゲンスタインと共著で著した『ゲームと経済行動の理論』である。この著書で、ノイマンらは、「囚人のジレンマ」の喩えなどで有名なゲーム理論の基礎を確立した。
戦後、ノイマンはプリンストン大学で教鞭を取る傍ら、顧問としてランドに加わった。ソ連はすでに原子爆弾の開発に関する米国の研究成果を入手している。核戦争が現実味を帯びている。先制攻撃の必要性を検討する上でゲーム理論は冷戦期の世界秩序づくりに決定的な役割を担う、とノイマンは考えたのだった。ランドはこのゲーム理論の導入により、純粋な技術研究から核戦略研究、防衛政策研究へと活動の幅を広げた。核戦略研究では「相互確証破壊」(Mutually Assured Destruction)の戦略概念を発展させた。いわゆる核を用いた〝恐怖の均衡〟による相互抑止論である。〝恐怖の均衡〟の不条理は、スタンレー・キューブリック監督の映画『博士の異常な愛情』に描かれているが、ピーター・セラーズ演じる主人公の科学者ストレンジラブ博士はノイマンや、ハーマン・カーンなど、複数のランダイトたちの人物像を参考にしたといわれる。
ランドのもう一つの特色は、バーナード・ブロディ(核戦略論)、アルバート・ウォルスタッター(基地研究・フェイルセーフ理論)、ハーマン・カーン(熱核戦争論)、アンドリュー・マーシャル(RMA:軍事における革命理論)などの戦略理論分野での一群の〝防衛知識人〟(defense intellectuals)を世に出したことである。
バーナード・ブロディは、初期の時代のランドを牽引した核戦略論の泰斗である。彼は一九五九年に『ミサイル時代の戦略』を出版し、「限定戦争」の概念を提案した。戦術核兵器を限られた地域でのみ使用することで全面戦争となる前に停戦合意を図るという考えである。当初は、米空軍の反発もあり米政府は受け入れなかったが、一九六一年五月、ケネディ政権はカウンター・フォース戦略こそが、米ソの全面核戦争による世界滅亡を防ぎ、かつ米国を防衛する現実的な政策であると判断した。これが後のケネディ政権の核戦略である柔軟反応戦略の源流となる。ブロディは、「核兵器とその使用についての基本的なアイデアと哲学のすべてが、軍とは無関係に、シンクタンクの文民によって生み出された」と回顧している。
空軍との深い関係からして、「軍とは無関係」という評価は当たらないかもしれないが、政府と綿密な連繫を取りながらも、独立・非営利を貫き、自由で独立した思考を保証する知的環境を維持したことが、ランドのシンクタンク・パワーの源泉だったといえる。
アルバート・ウォルスタッターは哲学、論理、数学を専攻。妻のレベッカは「パールハーバー攻撃と日米開戦」研究の第一人者である。ランダイトの中で、おそらくもっとも権力に近いところにいたのがウォルスタッターであろう。アイゼンハワー政権末期、ソ連が核戦力で優位に立ち、米国の核抑止の安定性が損なわれているとする「ミサイル・ギャップ論争」が噴出する。ウォルスタッターは、同僚のハーマン・カーンやアンドリュー・マーシャルらとともに、超党派の諮問委員会の顧問を務め、ソ連の軍事的脅威を強調し、国防予算の大幅増額、核・通常戦力の強化を提言した。
数あるランダイトの中でも、もっとも一般に名の知られた防衛知識人は、ハーマン・カーンだった。カーンは、物理学専攻。ランドでは、ソ連への核兵器の先制攻撃の必要性を訴えるフォン・ノイマンらの薫陶を受け、『熱核戦争論』(一九六〇年)を著した。
ここでは、ソ連との核戦争の具体的な予測シナリオを発表、また米国が核戦争を戦い抜く上での核シェルターなどの民間防衛の必要性などを提言した。米空軍からは不評であったが、核戦争のリアルな描写と解説は、核戦争による世界絶滅の可能性に警鐘をならし、平和活動家からの高い評価を受け、世界的な大ベストセラーとなった。カーンは、米社会にどこまで核戦争の覚悟があり、どこまで犠牲を耐え抜く用意があるのか、と問いかけた。先制攻撃の有効性を認める一方で、核攻撃による破滅的な被害予想を公表したのも、それに耐える覚悟があれば最終的に核戦争にも勝利できるが、なければ米国の核抑止力は空洞化するとの警告でもあった。
なお、カーンは、その後、ランドの他の研究員とともに、ハドソン研究所を立ち上げている。カーンは、「一般社会への判断材料を可能な限り提供して自由な議論を促すことがシンクタンクの重要な役割である」と考えていた。ランドのようなシンクタンクは政策立案に当たり、政府の機微情報を共有することも多く、とりわけ軍事分野では情報の取り扱いに制約がある。そのことが、シンクタンクの社会への情報発信を妨げ、公共的な役割を曖昧にする。
カーンは「一般的に入手が可能なファクトを注意深く考察すれば、一般市民も防衛政策についてかなり容易に理解して議論することができる。機密情報に依存しなくても、積極的に情報発信ができる」と主張し、ハドソン研究所を立ち上げた。
カーンが掲げた原則がある。「民主主義に於いては、(政治家や政策立案の)専門家で意見が割れた問題は、最終的には一般人が解決しなければならない」
アンドリュー・マーシャルは、一九五〇年代、ランドの若輩の研究員だった時、ブロディやカーンやチャールズ・ヒッチ(後にケネディ政権で国防次官補)らの戦略家とともに、戦略目標委員会と呼ばれるランドのトップ戦略家グループの委員に選ばれた。
マーシャルは、その後NATO本部やNSC(国家安全保障会議)での勤務を経て、一九七三年、国防総省に新設された「ネットアセスメント室(ONA)」の室長に就任した。
ここは、ソ連やその他の脅威とリスクの予測とこれらの国々と米国との長期的な関係や優劣の包括的な総合評価と分析を行うことを目的とする国防総省内の内部シンクタンクだ。
冷戦後は、軍事における革命(RMA)やアンドリュー・クレピネビッチらとともに、オバマ政権の対中軍事戦略である「統合エアシー・バトル構想」の必要性を主張した。嚙み砕いていえば、中国などの米国のライバル国家が、米国の軍事力展開を脅かす能力を高めている中で、米軍、とくに米海空軍の戦力の統合運用を同盟国軍と適切に連携させ、相手を叩く能力(戦力投射能力)を高めることで地域の紛争を抑止する戦略である。
マーシャルは二〇一五年、四二年間にわたって自らつくり、育てたONAに別れを告げた。後任は、統合参謀本部議長の戦略問題主査(chief strategic officer)を務めたジェームズ・ベーカーである。ベーカーは、トランプ政権の対中戦略、なかでも地経学的戦いの戦略論のチーフ・ストラテジストと目されている。
『歴史の終わり』を記したフランシス・フクヤマは、一九八〇年代、一〇年近くランドで研究員として働いた。ソ連の外交政策のチームの一員として、第三世界、なかでも中東とアフリカのソ連の外交政策を研究した。「クレムリノロジーとかクレムリノロジスト(ソ連政治・政策研究や研究者)といった言葉もランドが生んだ」。フクヤマは、ランド時代、「政策立案におけるコスト・ベネフィット(費用対効果)の重要性をとことん叩き込まれた」と私に語ったことがある。
ベトナム戦争の後遺症
ランドの歴史の中で、最大の転機は、ベトナム戦争だっただろう。
ケネディ政権の国防長官となったロバート・マクナマラは、以前、ランドで働いた。彼は、国防長官になると、古巣のランドからヘンリー・ローウェン(後に国防次官補)やチャールズ・ヒッチ(後に国防次官補)らを引き抜いた。
ケネディ政権からジョンソン政権へ。米国はベトナム戦争の泥沼にのめりこんでいった。
それとともにマクナマラはますますランドに依存していった。しかし、ランド内部では、ベトナム戦争への批判的な意見も噴出していた。ドイツからの亡命者である政治学者のコンラッド・ケレンは「ベトコンを根絶することはできても、征服することはできない」と主張した。
もっとも有名なランドの反戦反逆児は、ダニエル・エルズバーグである。
エルズバーグは、一九五七年のスプートニク・ショックからキューバ危機を経てベトナム戦争までの一〇年間、ここで戦略問題の研究を行った。一九六二年一〇月のキューバ危機の際は、ペンタゴン入りしていたヘンリー・ローウェンに呼ばれ、ペンタゴンやホワイトハウスで極秘の危機対応プランづくりに従事した。エルズバーグの「核戦争プラナーの告白」との副題をつけた自伝『最終兵器』によれば、当時のランドは、世界を核戦争から救うのだという信念を持った人々が「イエズス教徒のような兄弟愛を持って、集い」、研究室の多くは未明まで蛍光灯が灯っていた。そして、ここの保秘やセキュリティーはペンタゴンやホワイトハウスよりはるかに厳しかった。
一九六七年夏、マクナマラは米国のベトナムへの軍事介入の歴史(一九四五~六七年)を記録するドキュメント(〝ペンタゴン・ペーパーズ〟)の作成をペンタゴンに指示した。エルズバーグもこの年数ヶ月、この作成作業に参画した。彼はベトナム戦争の現状を視察し、戦争に反対の意思を固め、そのドキュメントのコピーをニューヨーク・タイムズ紙のニール・シーハン記者に手渡し、その後、ワシントン・ポスト紙のベン・バグディキアン記者にも提供した。両紙が中心となってベトナム戦争の真実を報道、地方紙もその後を追ったことで、ベトナム反戦は全国的広がりを持つムーブメントとなっていった。その時、ランドの理事長となっていたヘンリー・ローウェンやエルズバーグ、そしてかつてランドの同僚だったバグディキアンらの間の緊迫した会話と状況は映画『ペンタゴン・ペーパーズ(The Post)』に生々しく描かれている。
ベトナム戦争は、「ランドの世界」に深刻な課題を突きつけることになった。
それは、国民に、科学やエンジニアリングや定量分析やモデルへの違和感と科学的と称する専門性への疑問を抱かせたのである。ランドはその標的となった。一九六〇年代以降、ランドは、ベトナム戦争の対ゲリラ戦や、海外における体制変革作戦などの分野に研究対象を広げるとともに、経済、社会、健康保険、教育などの内政のテーマにも取り組むようになったが、ベトナム戦争への加担とランド・アプローチに対する深刻な疑問は、その後も重い負の遺産として残った。現在、ランドの予算の半分以上が非軍事関連に向けられている。
ランドは、シンクタンクとしての自らの歩みをどのように評価しているのであろうか。ランドが発行した『違いを出す』(二〇一八年)には、実験的世界一周宇宙船の初歩的デザイン(一九四六年)、インターネットの基礎づくり(一九六二年)、AIの基礎研究(一九六三年)、政策研究大学院の創設(一九七〇年)、オランダを破局的洪水から守る(一九七五年)、米軍におけるゲイ排除に反論(一九九三年)、中国軍事近代化追跡(二〇一二年)、真実腐食と戦う(二〇一七年)など七〇の分析や提言や取り組みが挙げられている。
ランドの近年の研究で特筆すべきは、『真実腐食──米国の公共における事実と分析の役割の衰退の初期的探求』であろう。これは〝真実はさておいて(post truth)〟のような事実認定を蔑ろにして自らの嗜好や信条を〝真実〟として氾濫させる政治とメディアがもたらす深刻な問題を分析し、それが真しん摯しな議論の衰退、政治の麻痺、政治と社会からの個人の疎外と離脱、国家政策の不確実性などの問題をもたらしていると警鐘を鳴らした。その最大の問題は、人々の「考え抜く力(critical thinking)」を育てる環境を破壊することにあるという。
アンディー・ホーン副理事長は、「ランドは、政治を動機としない。イデオロギーも動機としない。ただ、実証主義(empiricism)を動機とする。最善の分析による最善の解を提供する、そこから来る信頼が我々の命」だと私に語った。ランドをランドたらしめている「考え抜く力」のための「証拠本位(evidence based)」の基が崩されかけようとしている。『真実腐食』を、マイケル・リッチ理事長自ら著した(ジェニファ・カヴァノーとの共著)ことの切実な意味をぜひ察してほしい、とホーンは言った。
CSISと地政学
戦略国際問題研究所(Center for Strategic and International Studies:CSIS)はいまでは、ランドと並ぶ外交・安全保障のトップ・シンクタンクと見なされている。しかし、米空軍の後押しとフォード財団の潤沢な資金によって産声を上げたランドとは異なり、一九六二年九月にCSISが創設された時の年間予算は一二万ドルにすぎなかった。
立ち上げたのは、下院共和党の外交問題スタッフをしていたデイビッド・アブシャイアである。当時、三四歳。アブシャイアは、ウエストポイント出身。陸軍将校として韓国で勤務をした後、ジョージタウン大学で博士号を取得した。専攻は歴史。東南アジアやアフリカにおける地域紛争が内戦や代理戦争となるのを見て、米ソの核戦争、さらには軍事力だけに照準を当てた戦略研究では不十分であることを痛感し、ジョージタウン大学に付設する形で「ジョージタウン大学戦略研究センター」を設立した(当初は、「国際」が名称に入っていなかった。それを入れたのは六年後である)。
アブシャイアがモデルとしたのは、英国の国際戦略問題研究所(International Institute for Strategic Studies:IISS)である。
IISSは、一九五八年、フォード財団の資金援助の下で設立された英国の独立系シンクタンクであり、その使命は「人間社会たる国際関係(civilized international relations)の維持と、国際平和および安全保障の促進に向けた確たる政策提言を行うこと」。当初の重点研究分野は核抑止と軍備管理であったが、その後研究対象となる分野や地域を拡大、現在はロンドン、ワシントン、シンガポールおよびマナーマ(バーレーン)に拠点を有している。IISSの看板出版物は、『ミリタリー・バランス』と『サバイバル』であり、看板イベントは、アジア太平洋の安全保障に関する政策協議の主要な場であるシャングリラ・ダイアログ(正式名称「IISSアジア安全保障会議」)である。
創設に当たって、アブシャイアは、アーレイ・バーク元海軍作戦部長に会長を引き受けてもらうことにし、ありとあらゆる伝手を頼って、バークを口説いた。
バークは、第二次世界大戦の国民的英雄。南太平洋では、駆逐艦の艦長として日本海軍と死闘を演じた。バークは「米国史上、もっとも長く勤めた海軍作戦部長」を最後に退官したばかりだった。通常の海軍作戦部長は三年程度の任期だが、バークは六年もその職にあった。
バークは卓越した戦略家だったが、その根本思想は「リーダーシップも戦略も、人間的要素を決して忘れてはならない」という点にあった。それはアブシャイアの考えでもあった。国際政治とパワーの動態を分析するには、歴史を踏まえた地政学的なアプローチと国際政治の本質であるリアリズム、つまり現実主義的アプローチで臨まなければならない。
否応なしに、それはランドの数量的アプローチへのアンチ・テーゼの色彩を帯びることになった。アブシャイアは、政治学、歴史学、地域研究などの専門家を研究員として招き、徐々にプログラムを充実させていった。その際、空軍系ではなく陸軍系、海軍系の軍人を巻き込んだ。ランドとの違いを明瞭に出すということとともに、アブシャイアやバークの軍歴とも関連していただろう。
冷戦をいかに戦うか。いかに勝ち抜くか。その点では、CSISもランドも課題は同じだった。しかし、バークもアブシャイアも、戦略の概念を軍事的な概念を超えて、広く定義した。戦略とは「ある目的を達成するために最大限の資源を手にすることだが、それは静止したイデオロギー的なマインドセットに囚われていては望めない変化を生むアート」でもある。
アブシャイアは書いている。「歴史上、いかに多くの国々が、軍事機構が硬直的になりすぎ、革新できず、あるいは彼らの経済システムが競争力を失い、投資資本を生み出せず、あるいは政治があまりにも階層化し、身動きが取れず、それゆえに能力のあるものがトップに上がっていけないことによって、死に絶えたことか」。
中ソの間の対立にいち早く注目し、その意味合いについて考察したのもアブシャイアだった。一九六五年の春、米下院外交委員会のクレメント・ザブロッキ同委員会アジア太平洋小委員会委員長は、中ソ対立に関するヒアリングを開いた。それまで中ソを中心とする共産圏は一枚岩と見られていただけに、この公聴会は画期的な意味を持った。ザブロッキに公聴会を開催するよう促し、そのための理論構成や資料収集や専門家の人選などを手伝ったのがCSISだった。アブシャイアは、共産圏が中ソ対立だけでなく多元化し、それがまた自由陣営の中の対立と多元化をもたらす可能性があると見ていた。この公聴会の証言を中心にザブロッキが編集した報告書が『中ソ対立──米国の政策への意味合い』である。
バークもアブシャイアも、保守派だったが、単なる冷戦戦士ではなかった。二人とも、複眼的な見方をしていた。その戦いが、米ソの核対決であり、イデオロギー対立であることは言うまでもない。しかし、冷戦は「間違った戦争」であるとバークは考えていた。「なぜなら、冷戦は、我々のイマジネーションの中でのみ存在する戦争だ。その結果、共産主義は前進し、西側はその誤解によってハンディ・キャップを負ったままだ。真の敵はソ連でも中国でもない。それは共産党国家のパワー・エリートなのだ」。
アブシャイアも、冷戦を必死に戦うが故に、守るべきものまで失ってしまっては元も子もないと懸念していた。米国も西側も、一体、何を守るために冷戦を戦っているのか。それをもっと明確にする必要がある。簡単に言うと、守るべきは、保守であり、自由主義である。
しかし、保守とは何か。アブシャイアによれば、保守には、①現状維持を求める保守、②過去を理想化し、変化を拒否する保守、③人間の性質と政治行動の持続的かつ時代を超越した一般理論を受け入れる保守、の三つの保守がある。アブシャイアの保守は、この三つ目の保守、すなわち時代に即し、変化を受け入れるダイナミックな保守である。守るために、変える、そうした保守、である。「保守に含まれるあの純粋な現状維持の要素を正すものとして、何がしかの自由主義が重要な役割を持つ」というのである。
一九六九年一月、ニクソン政権発足とともにアブシャイアは国務次官補として政権入りしたが、一九七二年末に辞任した。引退を決めたバークが、アブシャイアに後任の会長を託することにし、CSISに戻ってくるよう言い渡したのだった。一九七三年、アブシャイアはCSIS会長として帰ってきた。バークがアブシャイアに言ったことはただ一言だった。
「CSISをいつまでもわくわくするところにしてくれ」
キッシンジャーとブレジンスキー
アブシャイアの「わくわく」イニシアティブの第一弾は、ヘンリー・キッシンジャー前国務長官をCSIS顧問兼評議会メンバーに迎え入れたことである。
一九七七年一月、彼が国務長官を辞職した時、ハーバード大学、コロンビア大学、エール大学などの間で激しいキッシンジャー争奪戦が起こった。しかし、キッシンジャーはワシントンのジョージタウン大学で教えながら、CSISに本拠を置き、ワシントンでの活動を維持することにした。CSISはキッシンジャーを会長とする国際評議会を設置した。評議会には日本からも盛田昭夫ソニー会長と豊田英二トヨタ会長が名を連ねた。
一九八一年には、カーター政権で大統領補佐官(国家安全保障担当)を務めたズビグニュー・ブレジンスキーがやはりCSIS顧問で加わった。戦後の米国を代表する地政学者であり、外政家である二人がCSISに籍を置いたのである。
キッシンジャーとブレジンスキーを評議会メンバーとしたことは、CSISの信用をさらに高めることになった。キッシンジャーが率いた評議会の場合、評議員は年間五万ドルを寄付することが慣例のようになり、ファンド・レイジングの面でもプラスに働いた。
二人の貢献は計り知れなかった。「とくに知的貢献という意味では、ズビグニューの果たした役割は大きかった。ヘンリーはイベントには来てくれたが、ズビグニューは研究プログラムにも参加し、議論に加わってくれた」とジョン・ハムレ所長は回想する。
CSISの大きな業績の一つとして、一九八六年のゴールドウォーター・ニコルズ国防総省再編法(GW‐N法)への貢献がある。GW‐N法は、米軍の統合運用の強化のための、国防総省および統合参謀本部の大規模な組織改革を内容とする国内法令である。米国の四軍(陸海空軍海兵隊)が、軍種の対立を超えて相互に連携しながら作戦を進める基礎をつくりあげた画期的な法律として知られる。この法案作成に当たっては、CSISが組織した専門家パネルの研究成果である「より効率的な防衛──防衛組織プロジェクトの最終報告書」(一九八五年)の出版が果たした役割が大きかった。その後もCSISは、GW‐N法の実施状況を継続的にフォローアップしている。
アジア戦略
CSISのもう一つの強みは、アジア戦略への取り組みである。マイケル・グリーン(日本・朝鮮半島・アジア全般)、ヴィクター・チャ(朝鮮半島)、エイミー・シーライト(東南アジア)、マシュー・グッドマン(地経学)らのいずれも政治任命者として政権入りした経験のあるアジア専門家を擁している。
その成果の一つが、『アジア太平洋リバランス2025』(二〇一六年)である。これは、二〇一五年に米国議会と国防総省が、CSISに委託したプロジェクトで、今後二〇年間におけるアジア・太平洋での米国の軍事戦略、戦力態勢ならびに同盟国・パートナー諸国の状態に関する独立評価と政策提言を行った。マイケル・グリーンらが執筆した報告書は、従来オバマ政権で行われてきた、アジアにおけるリバランス政策の実行では国益を守るには不十分であり、また一部国家の行動が米国の関与の信頼性に挑み続け、米国の能力向上が仮想敵のもたらす挑戦に追いつけないことから、地域の軍事バランスは米国にとって不利なものになりつつあると分析している。それを踏まえ、米太平洋軍(PACOM)の担当地域(AOR:Area of Responsibility)における防衛および抑止を強化すべきであり、効果的なアジア太平洋戦略を遂行するには明確で着実かつ機敏なアプローチが必要であると分析している。
その他にCSISのアジア関連プロジェクトで近年大きなインパクトを与えたのは、オンライン上のプラットフォームであるアジア海洋透明性イニシアティブ(Asia Maritime Transparency Initiatives:AMTI)の開設である。デジタル・グローブ社が撮影した民生用衛星画像を使って、中国の南シナ海でのいわゆる人工島の軍事化の進展を偵察し、点検する。そこでのリアルタイムの情報を共有しつつ、アジア太平洋地域の海洋問題に関する分析、情報提供、政策対話を実施している。目的は、地域の透明性確保によって一部の国の独断的な行動を抑制し、地域各国の協力、信頼醸成を促進することである。
現在、CSISは、防衛、エネルギー、アジアを重要項目としているが、ハムレは、今後一〇年、貿易政策に照準を当てていく方針である。
ハムレは私に語った。
「民主党員のうちTPP(環太平洋経済連携協定)に賛成するのは五九%に達している。しかし、民主党は党としては、労働組合の圧力で反対の立場。一方、共和党はワシントンの共和党は全般的に賛成だが、草の根共和党では三九%しか支持していない。双方ともねじれている。その中で、どのように自由貿易体制を維持し、支持する国内政治的基盤を再構築するかを研究しなければならない」
これからの最大のテーマは、「世界における米国の指導力の再建」である。しかし、その前提として「米国の国内政策の再建」に取り組まなければならない、とハムレは言った。
PIIEとTPP
PIIEの前身のIIE(Institute for International Economics:国際経済研究所。二〇〇六年にPIIEに改称)はカーター政権の財務次官補(国際経済担当)・財務次官(金融担当)だったフレッド・バーグステンが退官後、ジャーマン・マーシャル基金(GMF)から国際経済専門のシンクタンクをつくる提案を受け、一九八一年に立ち上げた。GMFは、同研究所創設に際して「アカデミックに走りすぎないこと、そして現実に世界情勢に即した研究課題を選ぶこと」と「スピーディーかつタイムリーに出版すること」の二つの条件をつけた。
それはバーグステンの考えていたことでもあった。
とりわけ、スピーディーかつタイムリーに成果物を世に問うことにかけては、バーグステンには天賦の才があった。
彼の数ある政策提言の中で、最初のインパクトのある仕事は、一九八五年のプラザ合意から八七年のルーブル合意に至るG5の政策協調過程で主要通貨の為替調整の際のレファレンスとなった「ターゲット・ゾーン」の概念を提案したことである。それは、ブレトンウッズ体制開始後、もっとも重要な国際通貨制度の再編という大きなビジョンの一環として打ち出された構想だった。
もう一つが、早い段階からTPPの理論的な裏づけを行い、それを支持、推進したことである。その成果の一つが、キャサリーン・シミノ・アイサックスとジェフリー・ショットの共著『TPP──評価』(二〇一六年)である。これは、TPPの経済効果とコストを分析し、労働基準や農業など全二〇項目に関するTPPのプラスとマイナスについて論じたものである。米国と日本などのTPP加盟国は、それによって蒙る恩恵が大きい、と主張した。
二〇〇九年に誕生したオバマ政権は、当初、TPPにどのように臨むべきか定まっていなかった。
その政権を背後から後押ししたのがバーグステンはじめPIIEの研究員たちだった。
こんなガイアツ(外圧)型の後押しもあった。二〇〇九年一〇月、シンガポールのリー・クアン・ユー内閣顧問が、オバマ大統領と会談するため、ワシントンを訪問した。リー・クアン・ユーはこの時のワシントン訪問の際、公開スピーチを行ったが、「太平洋に自らの足場を置いておかないと、米国は世界のリーダーにはなれない」と述べ、米国に太平洋国家としてのコミットメントを再確認し、リーダーシップを発揮するよう求めた。
ただ、その同じメッセージは、バーグステンとの内輪の会合では、より直截だった。オバマとの会談の日の前夜、リー・クアン・ユーとバーグステンは食事をした。
リー・クアン・ユーは言った。
「米国という鬼の居ぬ間に、アジアで中国はやりたい放題です。こんなことでいいんですか。もし米国がTPPに入らないと、中国がアジア太平洋の貿易を支配することになるでしょう。私は、それを心配しているんです」
バーグステンは答えた。
「それをそのままオバマに伝えたらどうですか」
「大統領に第三国のことをあまり露骨に言わないほうがいいんじゃないですか」
「いや、違います。できるだけ明確に言わないとメッセージは伝わらない。ぜひ、明確に言うべきです」
翌日、リー・クアン・ユーとオバマとの会談が終わって、一時間ほどしたところで、ローレンス・サマーズ国家経済会議(NEC)委員長からバーグステンに電話が入った。
「TPPについて、ちょっと専門家たちの話を聞きたい。明日、来てくれないか。何人かこれはというのを集めてほしい」
翌日、一〇人ほどの専門家をマサチューセッツ通りのPIIEに集まってもらい、サマーズにブリーフした。
もっとも、サマーズはその時はまだ、気乗り薄のように見えた。
「シンガポールやニュージーランドのようなちっぽけな国々と自由貿易協定をやって、何になるのか」という態度だった。
バーグステンはサマーズを諭すように言った。
「日本も入ると思う。そうなればまったく話は変わってくる」
PIIEは当初から一貫して自由貿易を推進する立場を維持している。
リーマン・ショック後、そして、トランプ政権登場後、世界に共通して見られるポピュリズムと管理貿易と保護主義の逆風の中、PIIEの役割にはさらに大きな期待が寄せられている。
一九八七年、まだIIEの時代、私は客員フェローとして、ここで国際通貨政治の研究をした。
設立して数年も経たないころで、予算も、研究員の数も、間借りのオフィスも小さかった。しかし、小粒でもピリリと辛い革新的な研究に取り組んでいたし、研究員の誰もが燃えていた。財務省に就職の決まった大学院生がインターンとして私の研究を手伝ってくれたが、彼女の話から、経済専攻の大学院生たちの間で、もっとも人気のあるシンクタンクのインターン先がIIEであることを知った。
それ以後、IIE(PIIE)は目覚ましく発展した。数年前のことだが、CSIS理事長のジョン・ハムレはこんな風に言ったものである。
「ここ二〇年近くで一番成功したシンクタンクは、フレッド・バーグステンのPIIEだと思う。研究員の人数を絞り、レベルのきわめて高い、革新的な提言を常に出している。あそこの研究員になれば大いに箔がつくと見られている。ああいうのが新たなモデルと言える」
現実の状況に即し、的を絞ったテーマ設定の先取り、的確な分析、質の高い刊行物の「スピーディーかつタイムリーな」出版、そして政府要職者との信頼感に裏打ちされた連携が、PIIEの政策起業力と言えるだろう。
関連コンテンツ(第1章)

時代がシンクタンクをつくり、シンクタンクが時代をつくる
世界のトップ・シンクタンクの多くは、歴史上の転換点を契機にして生まれている。第一次世界大戦、大恐慌、第二次世界大戦、終戦、冷戦、ベトナム戦争、核戦争・核不拡散の危機、チェルノブイリ原発事故、冷戦終結、EU(欧州連合)誕生、中国台頭、九・一一テロとイラク戦争、リーマン・ショック、福島原発事故、気候変動などをきっかけに、シンクタンクは生まれてきた。そうした社会と世界を動かす危機や悲劇、そして秩序の大転換をきっかけに、人々は、既存の体制やルールへの疑問を抱き…
第3章以降はこちら(Amazonサイトに遷移します)

<参考文献>
David Adesnik, 100 Years of Impact: Essays on the Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Endowment for International Peace, 2011.
Rapahel Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress (Foundations of the Laws of War), Lawbook Exchange Ltd, 2nd edition, 2008.
Leonard S. Spector, The New Nuclear Nations, Vintage Books, New York, 1985.
Gorge Perkovich et al, Universal Compliance: A Strategy for Nuclear Security, Carnegie Endowment for International Peace, 2007.
Robert D. Schulzinger, The Wise Men of Foreign Affairs: The History of the Council on Foreign Relations, Columbia University Press, 1984.
Dayna L. Barnes,
Oona A. Hathaway and Scott J. Shapiro, The Internationalists: How A Radical Plan to Outlaw War Remade the World, Simon & Schuster, 2017.
J. L. Gaddis, George F. Kennan: An American Life, Penguin Press, 2012.
James Allen Smith, Brookings at Seventy-Five, Brookings Institution Press, 1991.
Bruce D. Jones, ed., The Marshall Plan and the Shaping of American Strategy, Brookings Institution Press, 2017.
Michael J. Hogan, The Marshall Plan: America, Britain and the Reco of Western Europe, 1947-1952, Cambridge University Press, 1987.
Bruce L. R. Smith, The RAND Cooperation, Harvard University Press, 1966.
Neil Irwin, “Topics For the former Federal Reserve chief to take up in his new blog,” The New York Times, April 1, 2015,
アレックス・アベラ『ランド世界を支配した研究所』牧野洋訳、文藝春秋、2008年。(文春文庫、2011年)。
アンドリュー・クレヴィネビッチ、バリー・ワッツ『帝国の参謀―リュー・マーシャルと米国の軍事戦略』北川知子訳、日経BP社、2016年。
Aaron L. Friedberg, Beyond Air-Sea Battle: The Debate Over US Military Strategy in Asia, Routledge, 2014.
Daniel Ellsberg, The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner, Bloomberg Publishing PLC, 2017.
Michael D. Rich, Making a Difference, RAND Cooperation, 2018.
Jennifer Kavanagh and Michael D. Rich, Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, RAND Corporation, 2018.
James Allen Smith, Strategic Caling: The Center for Strategic and International Studies 1962-1992, The Center for Strategic and International Studies. 1993.
Clark A Murdock and Pierre Chao, Beyond Goldwater-Nichols Phase II Report: U.S. Government and Defense Reform for a New Strategic Era, Center for Strategic and International Studies, 2005.
Michael Green, By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacifc Since 1783, Columbia University Press, 2017.
Michael Green et al, Asia-Pacific Rebalance 2025: Capabilities, Presence, and Partnerships, Center for International and Strategic Studies, 2016.
C. Fred Bergsten and Russell A. Green, International Monetary essons from the Plaza Accord After Thirty Years, Washin Peterson Institute for International Economies, April 2016.
Cathleen Cimino-Isaacs and Jeffrey J. Schott et al, Trans-Pacific Assessment (Policy Analyses in Interational Economics Book 104), Peterson Institute for International Economics, 2016.
ストロブ・タルボット (Nelson Strobridge “Strobe” Talbott III、インタビュー、2015年10月15日。
フレッド・バーグステン (C.FredBergsten)、インタビュー、2016年8月。
マイケル・グリーン (MichaelGreen)、インタビュー、2016年8月4日。
続きはこちら(Amazonサイトに遷移します)

 APIニュースレター 登録
APIニュースレター 登録