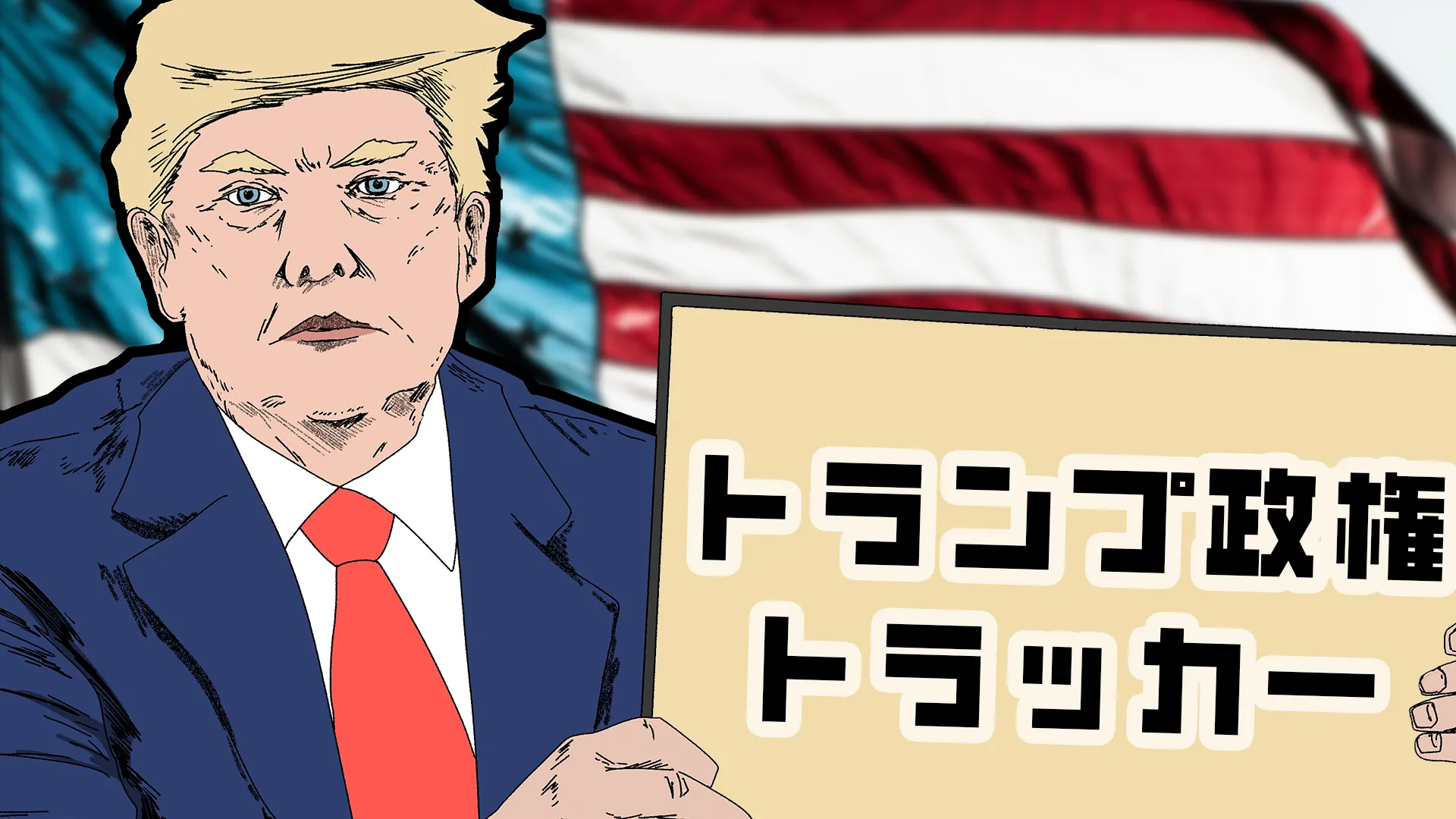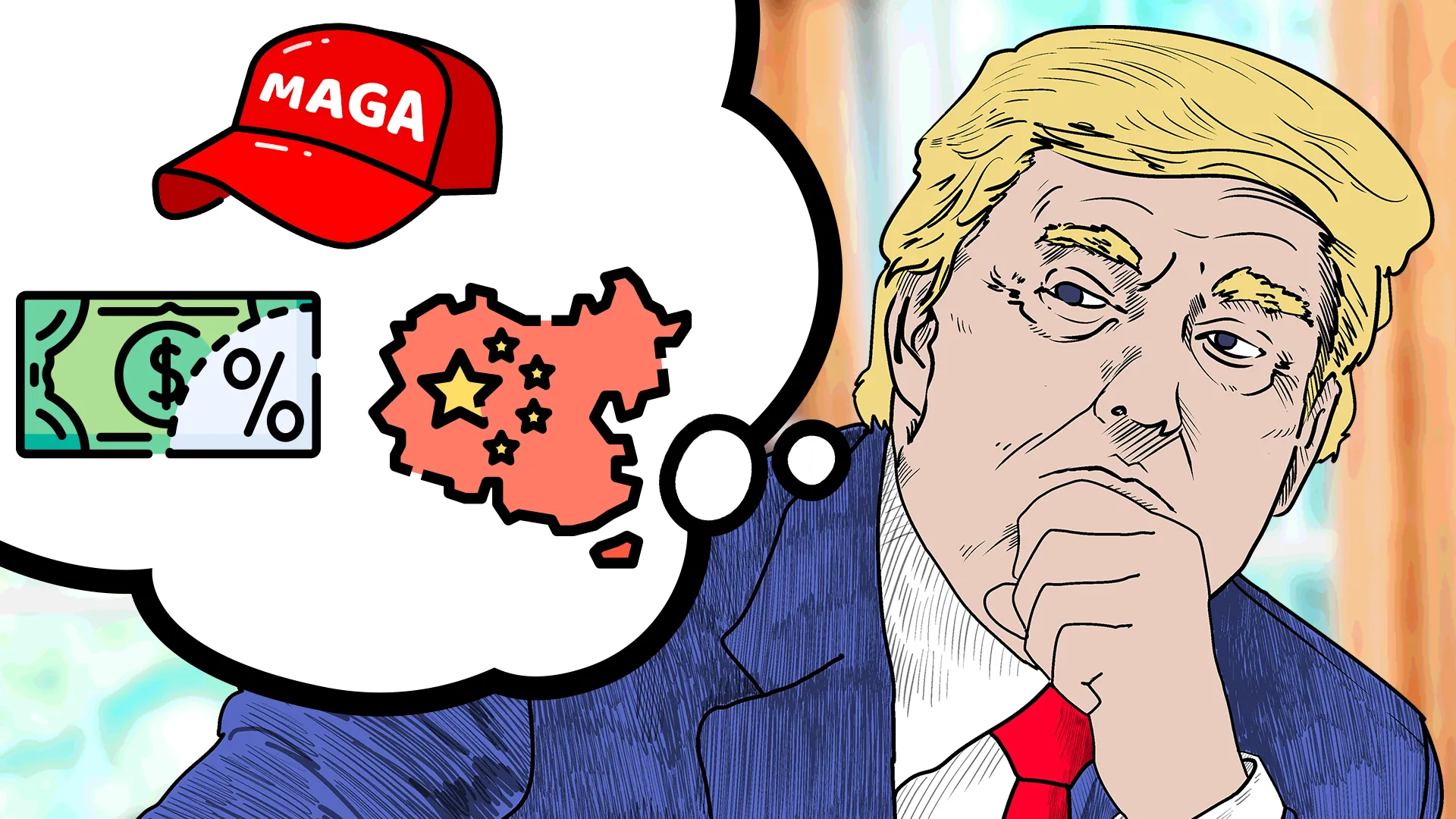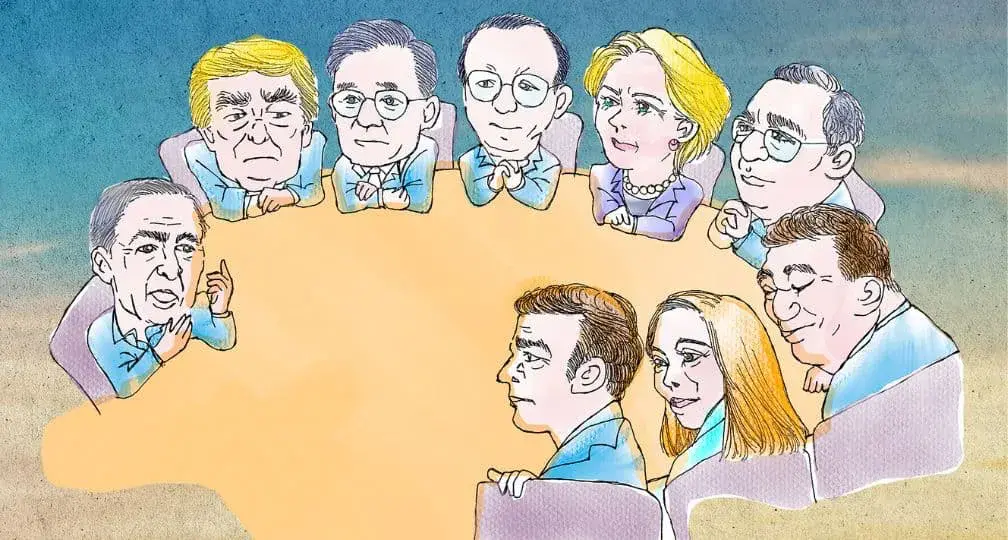需要が主導する国際市場における防衛装備移転の機会と要請
これとは少し異なるが、同様に安全保障と経済という2つの要素が混合した分野に、防衛産業がある。防衛産業は、防衛装備品を製造する機能を有するという意味で国家安全保障そのものの構成要素である。一方、その機能は経済アクターである企業に依存しているという経済的側面を有する。したがって、経済安全保障が、安全保障における経済的要素の高まりを象徴する概念であるのと同様に、防衛装備品が高コスト化し高度な技術が求められる中、防衛産業の持続性を考える上で、その経済性を考慮することが益々重要となってきている。しかしながら、従来の防衛産業に関する議論では、防衛産業の経済的側面についての考慮が薄かった。具体的には、防衛産業を産業の一分野として持続可能な形で維持していく姿勢が乏しかったと言える。それを最も端的に表しているのが、防衛装備品の海外移転を抑制してきた旧武器輸出三原則であり、その間口を少しだけ広げた防衛装備移転三原則だった。
防衛装備移転だけではなく、先端技術を有する企業の新規参入を含む防衛産業全体の強化策については、地経学研究所が2023年に発表した報告書『各国防衛産業の比較研究―自律、選択、そして持続可能性』で詳述している。一方本稿では、上記のような問題意識の下、防衛装備品を巡る国際的な動向に特に着目し、装備品の海外輸出に係る日本にとっての機会とその役割に対する要請について考えてみたい。
強い供給サイドが主導する国際防衛市場
一般に、世界で防衛支出が大きい国は、武器輸出の規模も大きい。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2022年の防衛費上位10か国は、上から米、中、ロ、印、サウジ、英、独、仏、韓、日であり、2018-2022年の5年間における武器輸出規模上位10か国は、米、ロ、仏、中、独、伊、英、スペイン、韓、イスラエルの順だった[1]。防衛費上位10か国のうち、武器輸出規模上位10か国に入っていないのは、国内防衛産業基盤の弱いインド及びサウジと、武器輸出を抑制してきた日本のみである。防衛装備品の開発・生産には大きな初期投資と高度な技術を要する上、量産数量に限りがあり、安定的な経営のためにはまとまった需要が必要となる。ある程度の規模の防衛産業を国内で維持していくために、海外輸出が不可欠の手段であることは、このような国際的動向を捉えれば明らかである。
また、近年、世界の武器輸出規模は増加傾向にあるが、その伸びを上回るペースで、米国の武器輸出規模が拡大している。世界の上位100か国の武器輸出規模は、過去20年で1.8倍となったが、米国のそれは、この間で3倍となり、世界全体の40%を占めるに至っている[2]。世界的な武器輸出規模の拡大は、武器に対する需要面の拡大を表す一方、技術面で優位性の高い米国製品のシェアの大幅な拡大は、供給面における競争の激化を示唆している。2024年2月時点でSIPRIのデータにまだ反映されていない2023年度の武器輸出について、米国務省の公表資料を参照すると、対外有償援助(FMS)の規模は2022年度の519億ドルから809億ドルへと55.9%増加している[3]。このうち、米国の予算を用いない有償での取引額は623億ドルにとどまるが、それでも前年度の総額を大幅に上回っている。
供給サイドが主導してきた国際市場において、武器輸出の後発国がシェアを急激に拡大することは容易ではない。日本は2014年に防衛装備移転三原則を策定し、従来の商業的な武器輸出を一律に抑制する方針を転換したが、後発国としての強みの欠如により、輸出可能な装備品の分野が限られてきたことも相まって、海外輸出を拡大できずにいた。
国際的サプライチェーンへの参画を可能とする防衛装備移転三原則の改正
このような状況への危機感から、政府は、2023年12月に防衛装備移転三原則とその運用指針を改正した。改正された三原則では、防衛装備の海外移転が望ましい安全保障環境の創出や侵略を受けている国への支援のため重要な政策手段であることを強調した。これは、侵略国に対応する場合はもちろんのこと、防衛装備移転は、維持整備や教育訓練等を通じて輸出先国との関係を中長期的・構造的に構築し、日本を取り巻く安全保障環境を改善することに資するとの認識に基づくものである。加えて、三原則では同時に、海外移転が防衛力そのものと位置付けられる防衛生産・技術基盤の維持・強化や防衛力の向上に資することが明確に規定された。これは、防衛生産・技術基盤の強化にとって、防衛企業における事業の持続可能性を確保することは不可欠であり、防衛装備移転はその持続可能性の確保に寄与するという認識の表れだろう。
また改正の具体的内容としては、国際共同開発された装備品に組み込まれている日本の部品や技術の第三国への直接輸出や、従来米国への部品の輸出のみに限定されていたライセンス生産品のライセンス元国への輸出(ライセンス・バック)の解禁、さらには、あらゆる種類の部品の輸出等が認め得ることになった。
一方で、共同開発品の完成品を日本から第三国へ直接輸出することや、国内で独自に開発された完成品の輸出を、いわゆる「5類型」(救難、輸送、警戒、監視及び掃海)に関するものを超えて広く認めることについては、2023年末時点で、自民党・公明党間の与党協議において一致できなかった。第二段階の見直しに向けた検討が進められている。
これらを踏まえると、先般の三原則見直しは、殺傷性を有する武器の完成品を日本が主導的に輸出することに依然としてためらいを残す一方で、それに至らないレベルで実践的にメリットのある輸出案件を三原則が妨げることがないよう、慎重に配意されたものとなっていることが分かる。特に、国際共同開発に関しては、開発パートナー国が主導する第三国輸出案件に対して拒否権を発動し、国際共同開発全体のメリットを損なうリスクを低減するための手当てだと言える[4]。また、ライセンス生産品の輸出の全面解禁や、部品レベルの輸出の解禁は、海外防衛プライム企業が確立した国際販路を利用する形で、日本の防衛産業を国際的なサプライチェーンに組み込むことを可能とするものであり、輸出後発国の戦略としては現実的で妥当なものだ。
一方、共同開発された完成品の日本から第三国への直接輸出や5類型以外の装備品の海外輸出を可能としない限り、日本の防衛企業が国際的な防衛プライムとして飛躍することは依然として困難な状況にある。この点、残された論点を検討するため、2024年の早い時期に二段階目の三原則見直しを議論する与党協議が再開され、今後の方向性が検討される予定である。
2023年末の改正により、日本の防衛産業ができることは格段に増えた。しかし、残された上記のような課題は、なるべく早期に処理した方がよいと筆者としては考えている。その理由は大きく3つある。
需要牽引型の防衛市場の現出
第一に、従来は、大きな国内防衛産業を有する国が互いに競争して輸出拡大を企図する供給主導型の市場だった防衛装備品の取引が、需要牽引型に転じつつある。大国間競争の再燃により、数年前からこの兆候は見られていた。しかしそれは、ウクライナ戦争の長期化によりさらに顕著になっている。
ウクライナに対する最大の武器支援国である米国は、米軍自身が、航空優勢を含め、圧倒的な軍事力と技術的優位により短期戦で勝敗を決する戦力構成をとってきたため、地上の消耗戦で重要となるりゅう弾砲の砲弾や携行型の対戦車・対空ミサイルの在庫を多く保持してこなかった。このため、消耗戦に対応した武器支援で弾薬やミサイルが不足しても、その部品や生産ラインがボトルネックとなり、増産に長期のリードタイムを要している[5]。また、弾薬・ミサイルの在庫不足は、米国だけでなく欧州のNATO加盟国においても共通の課題となっている[6]。加えて、ウクライナへの武器支援を巡っては、米議会でも下院を中心に共和党の反対が根強く、支援に必要な予算を確保できる見通しが立っていない。結果、2024年1月時点で、ロシアが1日当たり1万発の砲弾を消費できるのに対し、ウクライナ側の消費量は1日当たり2,000発にとどまり、火力の不均衡が徐々に拡大しているとされる[7]。
この点、米国防省が2024年1月に公表した「国防産業戦略(NDIS)」においては、米国の防衛生産サプライチェーンが余剰在庫を持たず「ジャスト・イン・タイム生産」による効率化を重視した姿となっていることを課題として位置付けている。そして、サプライチェーンの可視化やリスク低減、余剰生産能力への投資や防衛生産に関する国際的な生産拡大のための同盟国・パートナー国の参画促進を提言している[8]。その一環として、同戦略が、防衛装備品の質のみならず量や冗長性も重視し、同盟国等との協力を求めていることは、見方を変えれば、輸出後発国日本にとって米国市場に参画する好機となる。そして、その参画は、日本の防衛産業基盤の維持強化に寄与するのみならず、弾薬や装備品不足により不利な立場に置かれつつあるウクライナを間接的に支援することにもつながる。
また、国防産業戦略が認めるとおり、米国の防衛生産サプライチェーンは、その下層レベルに行くほどリスクに対する脆弱性が増すとされる。そうであれば、部品レベルで日本製品が米国市場に参画していく余地は、今後さらに高まっていく可能性がある。ただし、ウクライナを含め、国際的に求められる防衛生産は、米国を通じた部品輸出での参画のみにはとどまらない。特に、米議会でウクライナ支援予算の通過が危ぶまれている中では、完成品の輸出を含め、日本がより大胆に役割を果たすことが求められていると言えるだろう。
軍事技術の拮抗が生む消耗戦
第二に、消耗戦による紛争の長期化は、ウクライナ戦争という個別の紛争に特有の様相にはとどまらない可能性を示唆している。2023年1月、米国のシンクタンクCSISが台湾有事を想定した机上演習の成果を報告書にまとめた際には、米国におけるスタンドオフ・ミサイルの打ち尽くしによる在庫量不足が懸念されていた[9]。
戦略研究においては、一般に、近代的軍隊が戦闘を行う場合、火力投射・領土確保のための前進と、部隊の分散・隠匿による生存性の確保の間にあるトレード・オフにバランス良く対処する必要性が指摘される。ところが、近年の研究では、火力の精密性・致死性が向上した今世紀の防衛技術により、当該トレード・オフの均衡点が、より生存性を重視する方向へと動いていることが明らかにされている[10]。
その結果、部隊が生存するためには、広く分散した部隊配置をとり、敵のミサイルやドローンなどの精密火力により一網打尽に無力化されないことを徹底する必要が生じる。しかしそのことにより逆に、戦力の集中により敵の防衛線を突破し、領土を確保することが従来より難しくなる。実際、ウクライナ戦争では、早い段階からウクライナ軍の兵力を分散させて生存性を確保する戦い方が指摘されていた[11]。そしてさらに、集中的な無力化が困難な分散した敵に対しては、極めて多くの弾薬が必要となり、また、文民・民用物が巻き沿いになる機会も多くなる。
これらを踏まえれば、ミサイルやドローンなど、敵の兵力を奪える一方で、領土や一定のエリアの確保には直接貢献しない拒否的な軍事技術が発展し、紛争当事者の能力が拮抗する状況が現出すれば、戦線が膠着することは避けられない。ウクライナ戦争において、かつてないほどドローンやミサイルが多用されていることと、消耗戦が常態化していることは、決して無関係ではないのである。そして、米中が同様の非対称的能力を伯仲させれば、武力紛争が起きた時、それが長期化し、装備品や弾薬の量が決定的に重要となる可能性は高い。これまで、軍事技術の革新による短期戦やハイブリッド戦争、物理的破壊を伴わない新しい戦争の在り方が論じられてきたが、能力が伯仲した当事者間で依然として消耗戦が展開されている事実は、現代の戦争をより長期的・歴史的観点で位置付け直す必要性を示していると言える。
物量が求められる戦闘の形態が認識されている以上、消耗戦に備えた余剰生産能力の向上は、現在に限られた一時的なものではなく、中長期的な要請である。このため、台湾海峡や朝鮮半島という潜在的紛争地域に近接した日本としては、国際的な防衛生産能力の冗長性の要請に対し、中長期的な観点から応えていく必要性があるだろう。
サプライチェーンにおけるデリスキングの必要性
第三に、経済安全保障の観点から論じられる中国に関するデリスキングの考え方も、今後、国際的な防衛生産サプライチェーンに同様の影響を及ぼすと考えられる。上記で挙げた米国の国防産業戦略でも、敵対的な関係にある国家に材料や技術、部品、資本を依存していることへの懸念が指摘されており、その観点からもサプライチェーンの可視化や同盟国等との防衛生産協力の重要性が述べられている。中国が大きな供給割合を占める重要鉱物の中には、レアアースなど、防衛装備品の製造に不可欠のものもあり、抑止を企図する相手方にサプライチェーンのボトルネックを握られている状況は、決して戦略的に好ましいものとは言えない[12]。
一方、国防産業戦略では同時に、防衛産業に関わる熟練労働力が先細ってきていることも懸念されており、政府が急激に産業基盤強化のための予算を投下したところで、それのみで、一旦海外に出てしまったサプライチェーンを国内回帰することは容易ではない。
もちろん、サプライチェーンの海外依存や労働力不足の問題は、日本においても無縁のものではない。しかし、米国を始めとする同盟国・パートナー国との間で、互いに脆弱性を有するサプライチェーンを相互補完する取組は、今後さらに求められるようになっていく可能性が高い。
この点、防衛生産サプライチェーンにおけるデリスキングの取組も、部品に関する協力から始めるのが最も現実的だろう。その一方で、完成品の輸出や同盟国・パートナー国における現地生産を含め、あらゆる選択肢を排除しないことも重要である。防衛装備品の分野におけるデリスキングとして真っ先に行うべきことは、投資でも補助金でもなく、まずは自国や同盟国の脆弱性を解消する機会をブロックするような障壁を取り除くことかもしれない。その観点からは、2023年末の三原則改正で可能となった部品全般の移転のみならず、航空機や艦船など大型プラットフォームに搭載する構成品(機能発揮できるものは部品とは位置付けられていない)の輸出なども、全面的に可能とすべきだ。また、米国政府の機微情報を含む調達に日本企業が柔軟に参画できるよう、日本から米国への働き掛けも重要となってくる。
地経学研究所が2023年末に実施した経済安全保障100社アンケートでは、サプライヤーの変更や多元化等を行う先として重視する国の上位に、日本(国内回帰)のほか、米国、インド、EU等の同盟国・友好国が掲げられた。防衛産業や装備品の海外移転の文脈でも、そうした国内回帰やフレンド・ショアリングの要請が同様の観点から高まっている。加えて、従来極めて輸出を抑制的に管理してきた分野であるにもかかわらず、国際的な需要の中長期的な拡大が見込まれる防衛装備品については、三原則の見直しの効果がかつてないほど高まっているという固有の事情もある。日本としてこの状況に的確に対応していくことは、防衛産業基盤の強靭化の有効な手段となると同時に、望ましい国際安全保障環境を主導的に創出していくという責務を果たすことにもつながる。
注
- ・[1]SIPRI, SIPRI Yearbook 2023 (SIPRI, September 2023).
- ・[2]SIPRIが独自に設定した武器輸出の規模を示すトレンド指標値(TIV)による。SIPRI Arms Transfers Database, https://www.sipri.org/databases/armstransfers.
- ・[3]Department of State, “Fiscal Year 2023 U.S. Arms Transfers and Defense Trade” (January 29, 2024), https://www.state.gov/fiscal-year-2023-u-s-arms-transfers-and-defense-trade/.
- ・[4]改正前の三原則下においても、共同開発の相手方が日本由来の部品や技術を組み込んだ完成品を第三国に移転することを一律に否定していたわけではなく、審査の上、事前同意を与えることは可能であった。その中でも特に、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合(米国によるF-35部品の国際的部品融通システム(ALGS)への参画など)や部品等をライセンス元に納入する場合(F-15・F-16戦闘機搭載F-100エンジン部品の米国への納入)等においては、防衛装備品移転協定の下での事前同意手続にはよらず、仕向先国の輸出管理体制の確認をもって第三国移転を可能とする簡易な手続がとられてきた。2023年末の改正においては、これらに加え、共同開発の相手方が日本由来の部品や技術を組み込んだ完成品を第三国に移転するに当たって、維持整備等のため日本から当該部品や技術を第三国に直接輸出することが求められる可能性を考慮し、それら部品・技術の第三国への直接輸出を可能とした。また、移転協定の下での事前同意手続によらず仕向先国の輸出管理体制の確認をもって第三国移転を認める簡易な手続の対象に、そうした場合(技術的機微性が高い場合を除く。)が加えられた。これらを踏まえれば、例えば日英伊共同開発戦闘機(GCAP)の完成品が英国又はイタリアの工場で完成品として組み立てられた場合、日本が事前同意又は第三国の輸出管理体制の確認を行うことにより、それらを英国又はイタリアが第三国に輸出することは可能である。ただし、GCAPの戦闘機は日英伊企業のジョイント・ベンチャー(JV)により製造されることとされているので、第三国輸出のため「平等なパートナーシップの精神」(2022年12月日英伊共同首脳声明)の下で製造分担を行う中で、日本から完成品を輸出することが求められるケースも想定される。2023年末の改正では、こうしたケースへの手当てが依然として行われず、三原則が、GCAPにおける製造分担の議論に日本が主導的役割を果たすことへの制約となっていることは事実である。
- ・[5]John Ismay and Eric Lipton, “Pentagon Will Increase Artillery Production Sixfold for Ukraine”, The New York Times (January 24, 2023), https://www.nytimes.com/2023/01/24/us/politics/pentagon-ukraine-ammunition.html; Doug Cameron, “Why Ukraine Hasn’t Been a Boon to U.S. Defense Companies”, The Wall Street Journal (January 31, 2023), https://www.wsj.com/articles/why-ukraine-hasnt-been-a-boon-to-u-s-defense-companies-11675176026.
- ・[6] “Europe needs a decade to build up arms stocks, says defence firm boss”, BBC News (February 13, 2024), https://www.bbc.com/news/world-europe-68273449.
- ・[7]“Ukraine Uses Five Times Less Artillery Ammunition Than Russia – RUSI”, Defense Express (January 8, 2024), https://en.defence-ua.com/industries/ukraine_uses_five_times_less_artillery_ammunition_than_russia_rusi-9125.html.
- ・[8]Department of Defense, “National Defense Industrial Strategy 2023” (January 11, 2024), https://www.businessdefense.gov/docs/ndis/2023-NDIS.pdf.
- ・[9]Mark F. Cancian, Matthew Cancian, and Eric Heginbotham, “The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan” (Washington DC: Center for Strategic and International Studies, January 9 2023), https://csis-website
- ・prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/230109_Cancian_FirstBattle_NextWar.pdf?VersionId=WdEUwJYWIySMPIr3ivhFolxC_gZQuSOQ.
- ・[10]Stephen Biddle, Nonstate Warfare: The Military Methods of Guerillas, Warlords, and Militias(Princeton: Princeton University Press, 2020), chs. 3, 4, and 10.
- ・[11]Mykhaylo Zabrodskyi, et al., “Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022” (London: Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, November 30, 2022), 53, 62-63.
- ・[12] 小木洋人「米国の防衛産業政策におけるデリスキングの取組」『海外事情』第71巻第5号、拓殖大学海外事情研究所、令和5年9・10月号、51-68頁。

経済安全保障100社アンケート
地経学研究所(IOG)は、初回である2021年から数えて3回目となる経済安全保障100社アンケートを実施しました。ウクライナ情勢を受けて、対ロ制裁は企業のコスト増や事業の将来性など経済活動に様々な影響を及ぼすとともに、米中対立や台湾有事への危機意識も高まっています。そのような中で、日本企業は、情報管理の強化やサプライチェーン強靭化など、安全保障と経済活動のはざまで苦悩しつつ様々な取組を進めています。経済安全保障をめぐり、企業は何を課題とし、どのように対処しようとしているのか、アンケートの結果などを踏まえて考察を深めます。


主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る