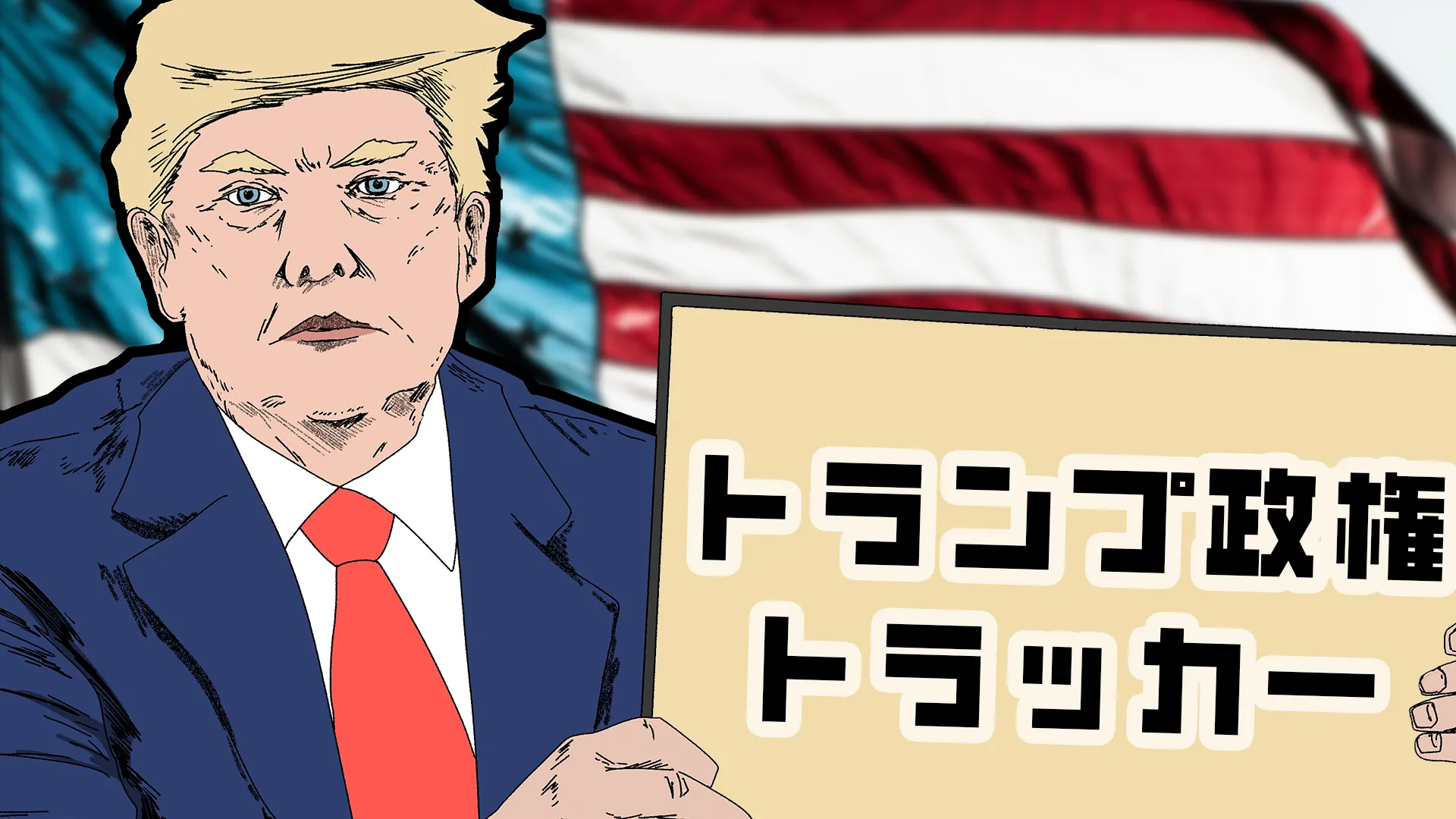習近平政権のチャーム・オフェンシブ

習近平政権が抱える課題群をどう見るか
3月半ばに「両会」(全国人民代表大会と全国政治協商会議)を終えた頃より、習近平政権のチャーム・オフェンシブ(対外的な魅力攻勢)が続いている。まず顕著になったのが外資誘致の強化である。3月19日に国務院弁公庁は「ハイレベルの対外開放の着実な推進と外資の誘致・利用の促進に関する行動計画」を発出、海外企業による投資を「中国の現代化推進に参与し、中国経済と世界経済の共同での繁栄と発展を促進する重要な力」と位置づけて、参入規制の緩和や知的財産保護の強化など促進策を表明した。続く22日には国家インターネット情報弁公室がデータの国外移転を管理するための規則を施行して「その年の1月以降の累計が10万人未満」を手続き対象外とし、事実上のデータ越境の規制緩和と受け止められた。
外交攻勢も続く。3月の全人代記者会見では王毅共産党政治局員兼外相が「積極的な外交」「秩序ある多極化」「大国関係の安定」を強調、グローバルサウスへのアピールも明示的であった。また習近平国家主席は3月にはカリブ海の島国ドミニカのスケリット首相、南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領、オランダのルッテ首相、4月にはインドネシア次期大統領となるプラボウォ国防相、ドイツのショルツ首相などとの首脳会談を北京で実施した。習主席は5月5日から10日には、およそ5年ぶりの訪欧としてフランス、セルビア、ハンガリーを訪問して関係強化を演出、これは米欧連携にくさびを打つ狙いとも指摘されている。
こうした習近平政権の動きには、対米競争と経済活性化という2つの狙いがある。習政権が第3期に入ってより、経済では労働人口の減少等を理由とした構造的なピークアウトに加え、不動産問題、地方財政問題、消費の減退、外資の撤退など、重たい課題が次々に表面化してきた。他方で、米中間の競争も先進的科学技術の競争に軸足をおいた経済安全保障の鍔迫り合い、半導体やEVへの規制や制裁関税の強化、あるいは鉄鋼やアルミニウムの過剰生産批判などの形で顕在化している。過剰生産の問題は欧州において市場競争を歪める補助金の問題としてEV、太陽光発電関連設備や風力発電タービンが調査対象となった。ウクライナ戦争が長期化するなかでのロシアとの蜜月関係も欧州諸国の不信を高めている。
現下の中国の目的は、国際社会における中国の立ち位置を改善し、外資を呼び込むことで中国経済を活性化して各国の経済的な対中依存を高め、さらに国際的な立場を高めるという好循環のスパイラルを形成することにある。この足元の動向を注視する必要はあるだろう。だが、こうした外資優遇は経済を回復軌道に乗せるための短期的アプローチに終わる可能性もある。中国のチャーム・オフェンシブに惑わされることなく状況を理解するためには、より長期的な観点から眼前に広がる課題群を位置づけ、大きなトレンドから中国の動向を考察する必要がある。
こうした観点から本特集では中国の構造的な課題に焦点を当て、今後の4回にわたって中国外交、中国経済、米中関係、日中関係という4点から習近平政権を考察する。
化かし合いの中欧関係
中国版チャーム・オフェンシブには社会主義の伝統的な戦術である統一戦線工作の手法、すなわち中国共産党に協力するアクターを取り込む戦術論がある。この観点から5月の習氏訪欧は、フランスを引き寄せることでEUを揺さぶることと、いわゆる「17+1」の対話枠組みが機能しなくなった中東欧・西バルカン諸国のなかから際立って親中的なセルビア、ハンガリーの二国をしっかり取り込むことの2点に主眼があったと評価できる。事実上の個人独裁に近い中国の政治環境においては、習氏本人が首脳外交を展開するにあたって十分に習氏のメンツが立つ勝算があるかという検討もなされただろう。
中国の基本的なアプローチは巨大な国内市場の魅力をテコに経済アクターを取り込むことにあり、欧州側にとっても中国との経済関係は重要である。マクロン仏大統領やショルツ独首相は訪中するにあたり、エアバスやBMWなどの代表的な企業からなる経済団を帯同していた。首脳外交の目的の一つに、商談の取り付けがあったことは事実であろう。他方で中小国においては、インフラ開発や生産拠点化も主要な取り込み手段となる。例えばハンガリーでは、中国のEVバッテリーメーカー大手の寧徳時代(CATL)が2022年に、完成車大手の比亜迪(BYD)が2023年に進出を決定している。
ただしこのことは、米国が主導する対中デリスキングが進むなかでEU諸国が「経済的利益を最優先にした」結果とは限らない。EU全体としては、ロシアを経済的に支える中国への認識は厳しくなっている。ショルツ首相訪中直後の4月23日に、ドイツ国内で中国に関わるレーザー関連技術および欧州議会情報の漏洩によりスパイ活動が摘発を受けたことは、首相訪中前からドイツ国内の中国に対する警戒認識は高まっていた証左と考えられる。
EU諸国による経済重視のメッセージはむしろ、中国側の対欧認識に働きかけ、得失の方程式を複雑にする外交戦術であったとも評価できるだろう。実際にデュアルユース技術の管理や重要物資のサプライチェーンの脆弱性は、以前より強く意識されるようになっている。2023年6月に欧州理事会(EU首脳会議)が採択した「ロシアによるウクライナ侵攻に関連した今後の支援策、安全保障と防衛、域外政策のほか、対中政策や経済安全保障に関する総括」は、中国に関する項を立て、経済における対中依存度を下げること、中国はロシアに戦闘行為を止めるよう働きかけること、台湾海峡の緊張に対する懸念、チベットや新彊での人権問題や香港政策への懸念を示した。また欧州委員会が提案し、EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会が23年11月に政治合意した「重要原材料法案」では、アルミニウムや人造黒鉛を「重要原材料」および「戦略的原材料」に指定することを決め、重要物資の対中依存軽減を実行に移している。24年1月に欧州委員会は、投資と貿易の両面での経済安全保障に関する政策パッケージ案を示していた。さらに欧州委員会は、4月に太陽光発電関連の企業に対する補助金の調査を開始しており、5月13日には調査対象であった中国企業によるルーマニアの太陽光発電施設計画からの自主的な撤退を発表することで決着した。
訪仏にあたり習近平国家主席は、5月5日付のフィガロ紙に署名入り文章を寄せ、フランスの対中外交が西側諸国を率先してきた60年の歴史、中国のさらなる対外開放がもたらす効果、世界平和に貢献する中国の意思を表明した。この中で習主席は自ら「私はグローバル発展イニシアティブ、グローバル安全保障イニシアティブ、グローバル文明イニシアティブを相次いで提唱し、グローバル・ガバナンスの改善と人類の発展問題の解決に対して中国の解決策をもって貢献し、世界の100以上の国や国際機関から支持されてきた」と評価した。しかし中国に対する不信や懸念が認識される事実からすれば、グローバル・ガバナンスにおいて中国が担うべき役割についての中国自身と他国との認識ギャップが存在することは間違いない。いわば中国のチャーム・オフェンシブは「信頼を欠く」という本質的な限界を内包しており、EU全体を惹きつけることは難しい。そのため中国は二国間アプローチに傾斜しているのだろう。
日本もまた、多元化のアプローチを
こうした中国との外交合戦から一歩引いたように見えるのが日本である。4月に岸田首相が訪米、初の日米比首脳会談を実施して南シナ海と東シナ海を一体とする安全保障の構図を描いたことに、中国は強く反発した。2024年版の『外交青書』では5年ぶりに「戦略的互恵関係」を書き込むことで中国に対して融和的なメッセージを送ったが、中国側は『外交青書』は「基本的事実を無視している」として批判した。
習政権第3期に入ってから、日中間に目立った政治的な往来はない。しかし実のところ、中国側が否定的なシグナリングで揺さぶりをかけているタイミングで日中対話を必要以上に追求する必要もない。日本はこれまでのところ、中国以外の地域での外交を推進してきた。5月に岸田首相はフランス、ブラジル、パラグアイを歴訪し、上川外相は4月下旬から5月上旬にかけてマダガスカル、コートジボワール、ナイジェリア、フランス、スリランカ、ネパールを歴訪した。日本のプレゼンスを高めることが結果的に、日中関係のモメンタムをもたらすことにも繋がるだろう。
中期的な観点からすれば、日本もまた中国の対日認識の方程式を多元化させるべく、硬軟織り交ぜた対話重視のアプローチに移行すべきである。月末に日中韓の首脳会談を控えて、当面は水面下での交渉を継続することになるかもしれない。しかし、例えばビザ免除が再開されるなどの変化があれば積極的に捉え、対話の糸口をつかみに行くことが現実的な対中アプローチとなるだろう。
(Photo Credit: Xinhua / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


上席研究員,
中国グループ・グループ長
学習院大学法学部教授。専門は現代中国政治、日中関係、東アジア国際情勢。スタンフォード大学国際政治研究科修士課程および慶應義塾大学法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、日本貿易振興機構アジア経済研究所副主任研究員、シンガポール国立大学東アジア研究所客員研究員、北京大学国際関係学院客員研究員などを経て現職。 [兼職] 学習院大学法学部政治学科教授
プロフィールを見る