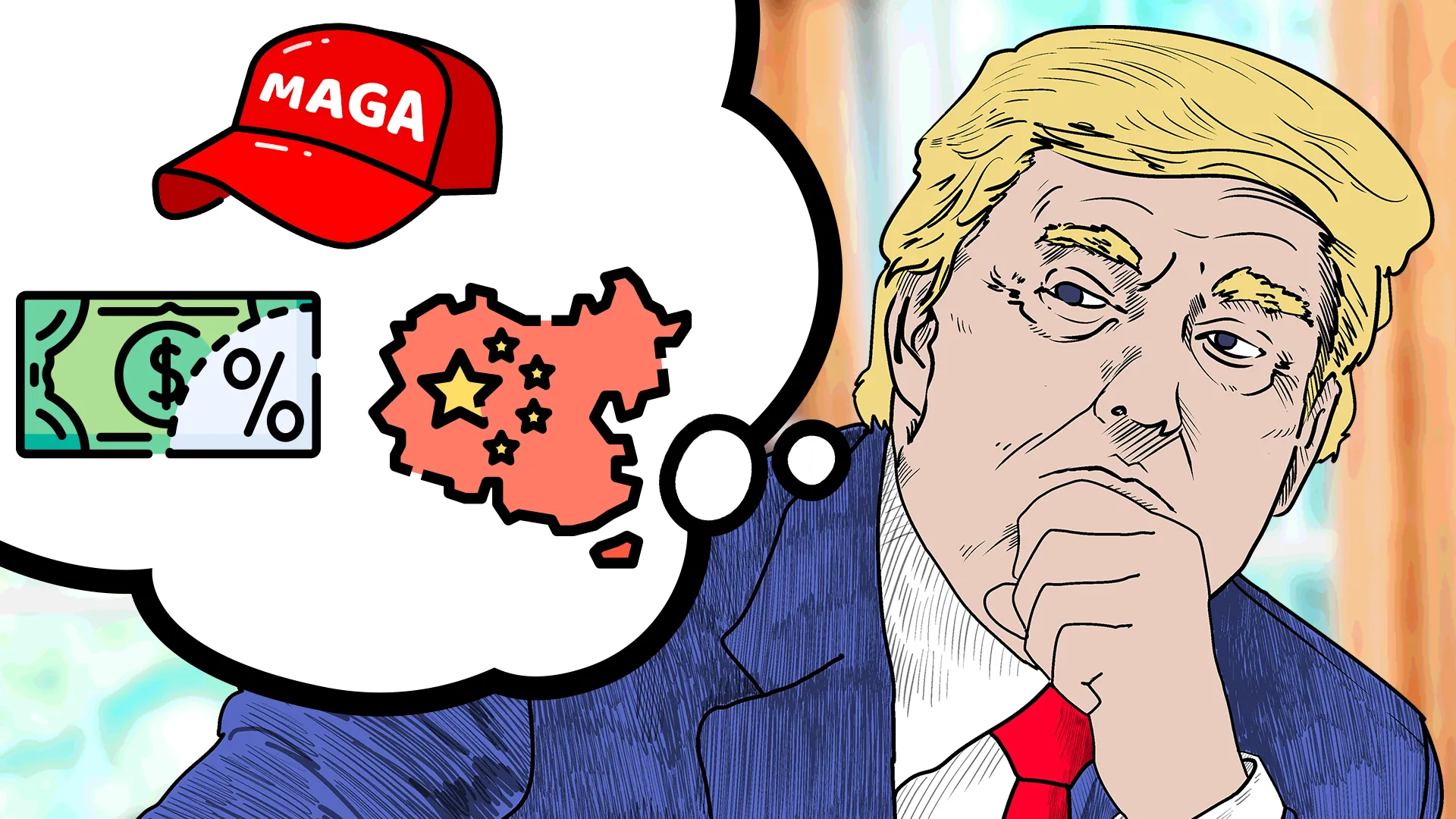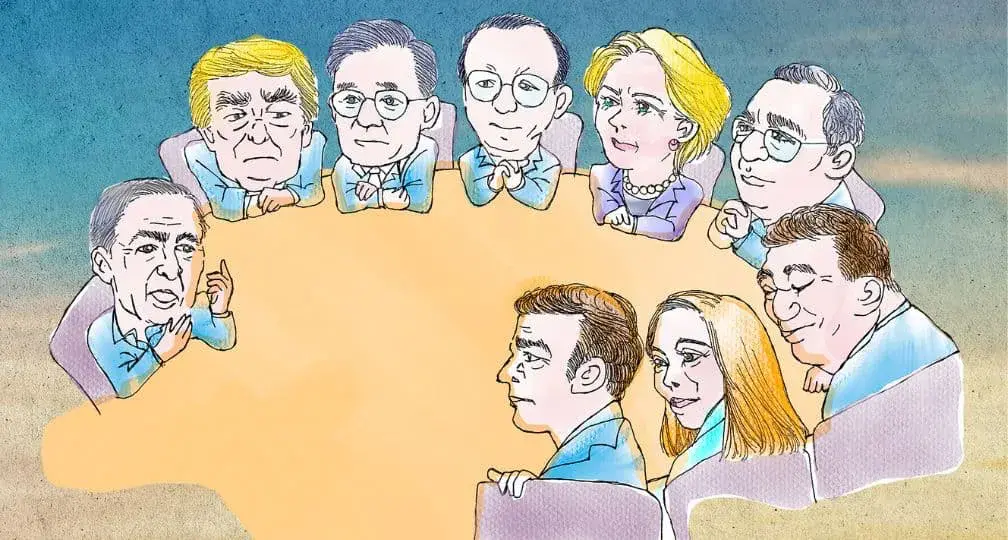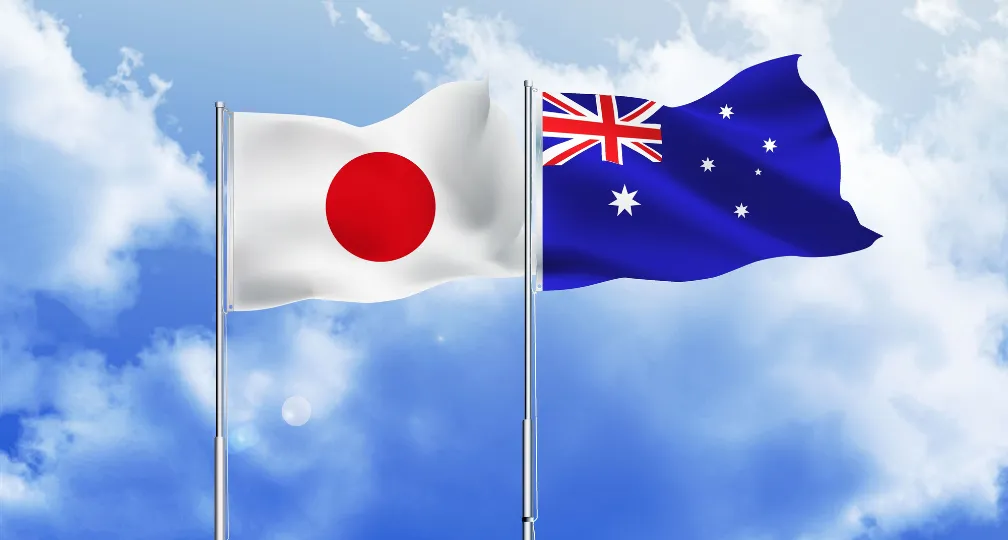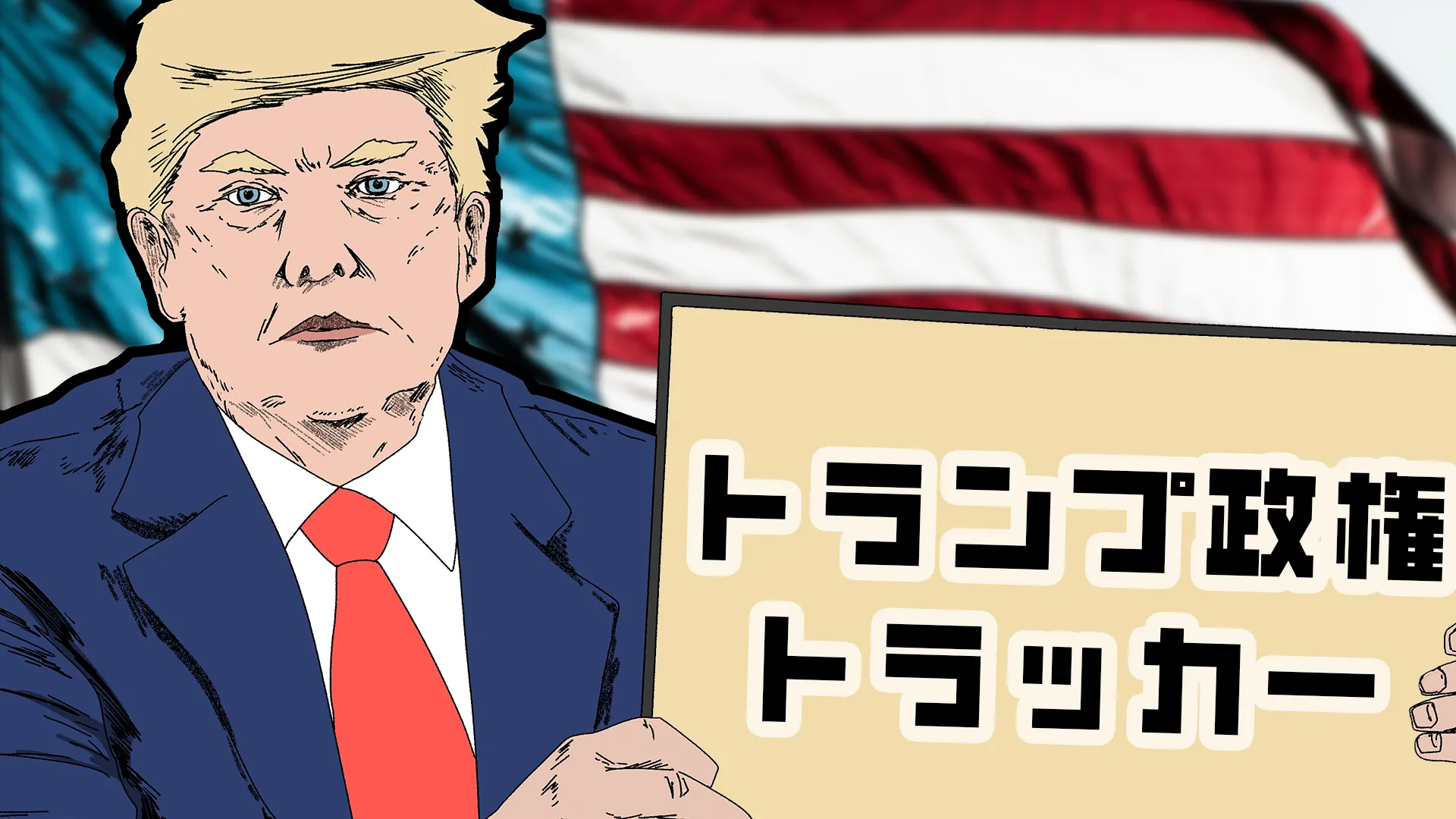激化する国際社会における「正しさ」をめぐる争い - 〝発信力〟を高める中国にどう対峙するか

本特集ではこれまで、独自の情勢認識に基づいて東アジアの国際秩序を変えようとする中国の外交戦略と、その反作用としての日本、ASEAN諸国、韓国の対応を論じてきた。
先行する3本の論考から浮かび上がったのは、経済的影響力を梃子として国際社会に独自の言説を刷り込み、「あるべき秩序」の概念そのものに揺さぶりをかける野心的な中国外交の姿である。
だが中国国内を顧みれば、コロナ禍を脱して徐々に経済回復すると見込まれるものの、直近の経済指標は予想を下回り、コロナ感染者数の再拡大も懸念されている。さらに4月には都市部の16~24歳の失業率が20.4%と過去最高を記録し、雇用の悪化が社会不安を誘発する可能性すらある。
国内に課題が山積するなか、中国が積極的な外交を展開する意図をどう理解するか。本稿では、3期目に入った習近平政権が描く外交戦略の論理を展望する。
理論武装がもたらす外交の硬直化
振り返ればこの数カ月、中国の大使レベルの外交官が硬直的な発言をする事例が相次いだ。
例えば、4月には盧沙野駐フランス大使がウクライナやバルト3国などの旧ソ連諸国について、主権国家であることを認めた国際的合意がないとして当該国の強い反発を招いた。
日本では、4月末に呉江浩駐日大使が台湾有事を日本の安全保障と結びつけるならば「日本の民衆が火の中に連れ込まれる」と述べ、これを5月の衆議院外務委員会で林芳正外相が「きわめて不適切」と批判した。
6月上旬には崔天凱元駐米大使がシンガポールの英字紙「ストレイツ・タイムズ」の取材に対して、米中対話ができないのはアメリカ側の意識が弱く、問題行動を起こすからだと主張した。
また、韓国では邢海明駐韓大使が李在明「共に民主党」代表との会談で、中韓関係の悪化は「韓国の責任」であり、米中対立についても「アメリカが勝利し、中国が敗北すると賭けるのは誤った判断だ。後で必ず後悔する」などと発言した。韓国外務省はこれを「外交慣例に反する非常識で挑発的な発言」として正式に抗議した。
これらのタフな主張に共通する特徴は、特定のイシューにおける中国国内でのナラティブ(語り)をそのまま海外に発信したことにある。結果的に中国は相手国からの批判を招いており、外交としては悪手であった。ではなぜ、こうした硬直的なナラティブを、外交のプロであるはずのシニア外交官が繰り返すのか。
これまでも中国の外交官が繰り返す攻撃的な発信が「戦狼外交」と呼ばれ、物議を醸してきた。
こうした発信が急増した要因の1つに、2019年に元党中央組織部副部長である斉玉が外交部党委員会書記に就任して外交部内の管理を強化したことが指摘されている。
斉書記の主導により外交部党委員会は2019年に「主題教育領導小組」(テーマ教育を指導する組織)を新設、部内教育プログラムを「月次計画、週次手配、日次進捗(月计划、周安排、日跟进)の作業メカニズム」のもとで実施してきた。この部署は外交部の各組織と在外公館に対して、それぞれの状況に応じた指導を強化することで「誤差を適時に是正し、『時差』『温度差』をなくす」ことを目指す、と位置付けられている。
つまり4年余りにわたる党主導の教育プログラムの結果として、国内の解釈をそのまま発信する外交官の増加が大使レベルにまで及んだと考えられる。
また、この枠組みのもとで、2023年4月上旬には「新時代の中国の特色ある社会主義思想をテーマとする教育動員部署会」というプログラムが実施されており、在外公館においてイデオロギー教育が強化されたタイミングであった。
国際的な「ディスコースパワー」の競争
中国外交におけるナラティブを本質的に理解するうえで重要なのが、習近平政権が追求する「国際的なディスコースパワー(国際話語権)」の概念である。「ディスコースパワー」とは、発言する権利とその発言を相手に受け入れさせるパワー(権力)を含む言葉である。
昨年、地経学ブリーフィング(「中国の民主主義と人権の「認知戦」に要警戒なワケ」)で指摘したように、習政権は自らの主観に基づき、今の中国がもつ総合的国力と国際社会での中国の立場に見合うディスコースパワーの形成を目指している。この概念を支えるのは、国際社会におけるナラティブの影響力は国力(パワー)とリンクするとの認識から、中国がより強くなることで自らのナラティブへの支持を獲得できるとの自信である。
だが徐々に単に自国のナラティブを強く打ち出すのでなく、相手国に受け入れやすいナラティブを選択的に発信する、以前より洗練された手法になりつつあった。たとえば習政権が「多極化」や「内政不干渉」といったキーワードをしきりに強調するのは、アメリカをけん制すると同時に発展途上国・新興国の支持を得やすいナラティブの浸透を図っている。
一方、中国政府は目下、経済の再活性化や技術の内製化を図るための外資導入を優先している。しかし1980年代からの市場経済化の経験を踏まえれば、経済を開放するほどに「西側」の思想が流入することは自明だ。
中国社会に普遍的価値が浸透するのを警戒する習政権は、国内外の情報源となりうる海外の華人・華僑ネットワークに対する監視を強化し、中国に批判的な言説を取り締まることで自国に有利な世論形成を画策してきた。
こうした経緯を踏まえれば、外交官らが中国国内のナラティブをそのまま海外でも用いることをためらわなくなったのは、対象諸国の批判を厭わず攻めに出たとも考えられる。習政権は既に「ディスコースパワーをめぐる闘争で西側に勝つ」との方針を固めているのであろう。
安全保障の利益に基づいたディスコースパワーの追求
安全保障の領域もまた、国際的ディスコースパワーの戦場となっている。中国では遅くとも2020年には人民解放軍のなかで「グローバルな安全保障のテーマ設定者となり、グローバルな安全保障話語における主導者となる必要性」が議論されていた。
中国の論者がいう「国際問題を定義する力の優位」、すなわちアジェンダセッティングのパワーを得ることで、闘争のプロセスが最適化されるとの考え方である。例えばこれをウクライナ戦争の停戦の議論にあてはめれば、戦闘行為を「ロシアによる侵略戦争」とするか、「NATOによる圧力への抵抗」と捉えるかでその意味も、終わらせ方も全く異なってくる。
あるいは中国が台湾問題をめぐる問題のすべての責任を、アメリカと「台湾独立派」に求めるのは、こうした「定義する力」の追求である。
6月上旬にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議(シャングリラ会合)では、オースティン国防長官と李尚福国防大臣の会談は中国側の拒否によって実現しなかった。その原因について中国側はアメリカ側に完全な責任があるのだと強調し、2018年から李国防大臣がロシア制裁違反を理由にアメリカの制裁対象になっていることを挙げた。
だが中国は、5月31日に北朝鮮が行った衛星発射実験を協議する国連安全保障理事会緊急会合では、北朝鮮を擁護して「一つの当事者に指をさしてすべての責任を負わせることが建設的なのか。明らかに違う」と主張した。この論理に則れば、米中対立についても米中双方に責任を求めるべきである。
習政権がいかなる安全保障問題についても「アメリカこそが問題の根源」と主張するのは、アメリカを「悪役」に仕立てることでアメリカに違和感を有する国を惹きつけるための論法である。だがその先に国際秩序の再編までを見通したとき、反米感情に基づく求心力には限界がある。
虚実ないまぜのナラティブへの備えを
習政権はそれを自覚しているがゆえに、国際情勢をどのように解釈するかという「認知」を誘導し、国際社会の「正しさ」の定義、すなわち価値規範をすり変えることを試みている。ディスコースパワーの不足を改善するという防衛的な姿勢から、より積極的に「正しさ」の獲得に動いていると言ってよい。
たとえそれが虚実ないまぜのナラティブであっても、一部の国内アクターが共鳴して世論が混乱することはどの国でも起こりうる。日本社会もまた、情報リテラシーを高める必要に迫られてている。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


上席研究員,
中国グループ・グループ長
学習院大学法学部教授。専門は現代中国政治、日中関係、東アジア国際情勢。スタンフォード大学国際政治研究科修士課程および慶應義塾大学法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、日本貿易振興機構アジア経済研究所副主任研究員、シンガポール国立大学東アジア研究所客員研究員、北京大学国際関係学院客員研究員などを経て現職。 [兼職] 学習院大学法学部政治学科教授
プロフィールを見る