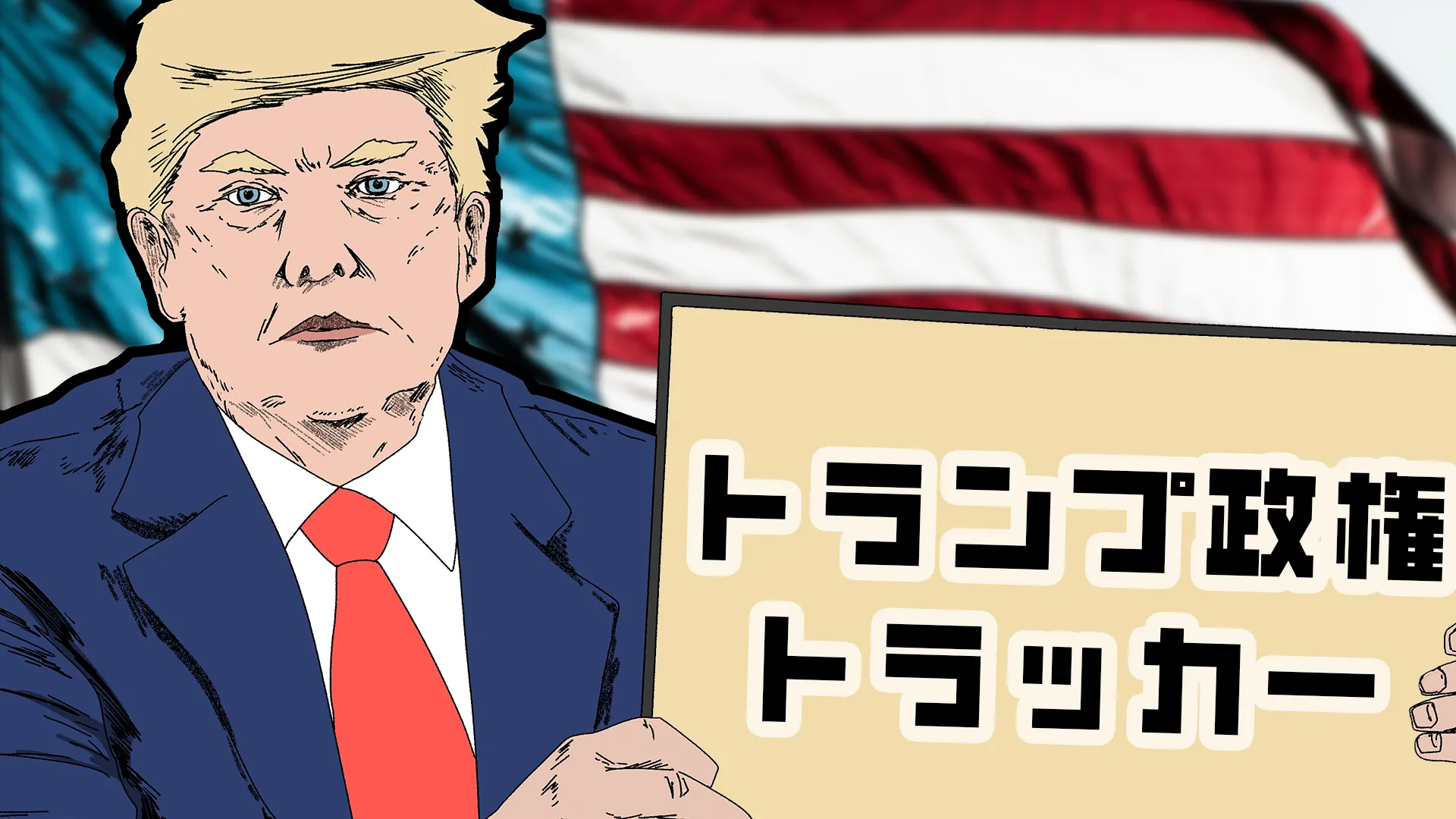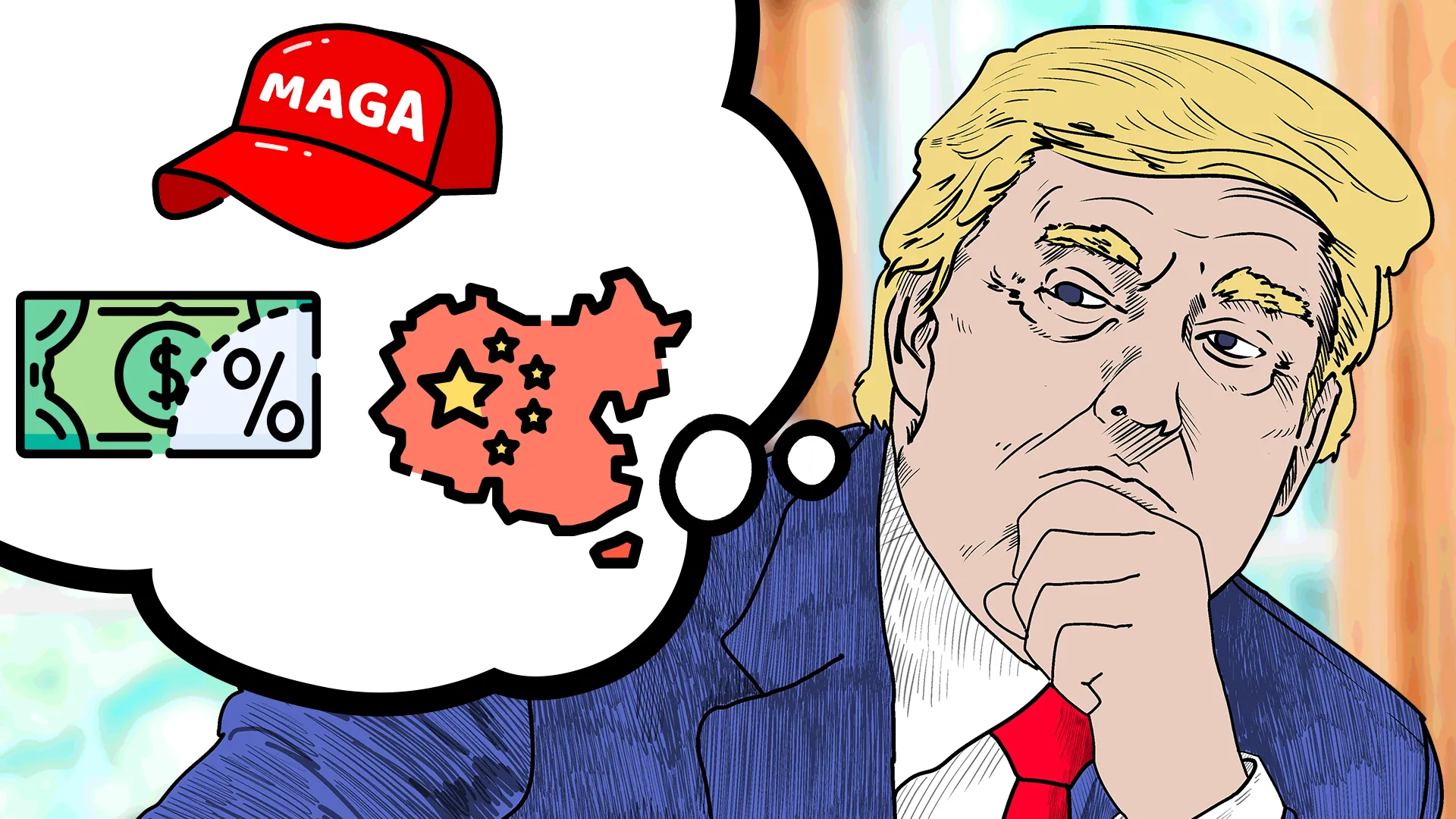ロシア・ウクライナ戦争が日本に及ぼす最大影響

こうした中、今後の欧州安全保障はどのようなものになるのだろうか。また、欧州防衛の中核を担うアメリカは、ロシアの脅威と中国との競争の狭間で、どのように防衛資源の配分を行うのか。それが日本を含むインド太平洋にどのような影響を与えるのだろうか。
抑制的な前方兵力強化
ロシア・ウクライナ戦争を受けて、NATOは6月の首脳会合で、12年ぶりとなる新戦略概念を採択し、対露防衛強化に動いた。しかし、そこで明らかとなったのは、「隅から隅まで加盟国の領土を防衛する」との強い言葉とは必ずしも釣り合わない前方配置部隊の抑制的な増強だった。
新戦略概念は、ロシアを「最も重大かつ直接的な脅威」と位置づけて前方防衛を強調し、また、有事増援部隊の核として、現行4万人の即応部隊に代わる30万人体制の新戦力モデルへの移行が合意された。
しかし、実際の前方兵力が大きく増強されたわけではない。NATOは、これまで展開してきたバルト三国とポーランドに加え、新たにスロヴァキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアにも大隊規模の多国籍戦闘群を展開したが、それらは6月時点で計1万人にとどまる。
また、首脳会合の宣言では、これら大隊の旅団規模への増強に合意したが、「必要な場所と時に」増強するとされ、配置のタイミングや常駐か否かは明らかにされなかった(その後9月にドイツ率いるリトアニア配置の旅団司令部要員100人の同地到着が発表されたが、その指揮下の戦闘部隊は、訓練でのローテーション展開とする計画のようだ。)。
新戦略概念と同じ時期にアメリカが発表した在欧アメリカ軍強化策でも、ロシアの侵略開始以来、アメリカ軍2万人を増派していることに触れつつ、ポーランドへの陸軍第5軍団前方司令部の設置や、ルーマニアへの1個旅団戦闘団の追加展開などを決めたが、劇的な兵力の増派はない。
アメリカ軍司令部のポーランド設置は、ポーランドを前方部隊の拠点とする姿勢を表すものでありつつも、依然として在欧米陸軍主力4万人はドイツに所在し、主力部隊が東部正面の奥に控える「二段構え」の態勢を構成していると言える。
この抑制的な前方防衛態勢は、西ドイツの東側国境を防衛するため8個軍団40万人以上の兵力を国境沿いに張り付けていた冷戦期NATOのそれとは対照的である。
NATOの戦略的優位性の高まり
NATOの前方兵力が劇的に増えていないのは、欧州諸国による準備が追い付いていないこともあるが、より根本的なのは、ロシア・ウクライナ戦争以前から、計350万人の加盟国兵力を擁するNATOが通常戦力ではロシアを圧倒してきたという事実である。そして、ロシア・ウクライナ戦争は、ロシア軍を消耗させることにより、その国力の中核たる軍事力の低下を招き、その傾向に拍車をかけたのである。
6月時点で、ロシアはウクライナ東部地域に兵力を集中し、一進一退しつつも前進していた。しかしその被害は甚大であり、ウクライナの発表によれば、ロシア軍は、開戦以来3.5万人の兵力を失った。ロシア全体で地上兵力が計33万人と見積もられていることを踏まえると、この時点で、増援部隊を含めず、東部正面における3万人のNATO前方兵力と30万人のホスト国兵力のみで、すでにロシア軍全体の常備地上兵力を上回っていた可能性もある。
このようなロシアの軍事力の低下は、短期的には回復しえない基調となった。ウクライナ軍がアメリカ等から供与された精密誘導兵器を用いて敵の力を弱めつつ、その高い機動力を生かして被害を抑え前進しているのに対し、ロシア軍は、機動力の低さと火砲・ミサイルの精度の粗さにより被害を拡大している。
ロシア軍の損耗はロシア・ウクライナ戦争が続く限り拡大する構造的なものであり、またそれが終わったとしても、人員装備の損耗や武器生産能力の低下により直ちに回復はできない。
ロシアに強みのある核についても、これまで戦術核の使用が懸念されてきたが、その被害や影響がロシア軍にも及びうることを踏まえると、戦況を好転させることに必ずしも貢献するものではない。
こうしたロシアの苦戦を受けて、アメリカは、今後同様の侵略を仕掛けられないほどロシアの軍事力を衰退させるという明確な意思を持ってウクライナへの武器援助を続けている。いわば「出血戦略」である。
アメリカのオースティン国防長官は、本年4月、アメリカのウクライナにおける目標を問われた際、「ロシアがウクライナを侵略したような行為を再びできないくらいロシアの力を弱めること」であると答え、このことを認めている。また、新たに発表された国家安全保障戦略においても、「ロシアのウクライナにおける戦争を戦略的失敗とする」ことを掲げている。
NATOの前方兵力の抑制的な増強は、ロシア・ウクライナ戦争を契機としたロシアの短期的脅威に対応するものである一方、戦争で加速したロシアの軍事力の低下や、それを促すためのアメリカによる「出血戦略」と併せて解釈しなければ不十分となる。
NATOとしては、目に見える形で前方兵力を増やし、また増援部隊の即応性を高めることは、ロシアの脅威の最前線に立つ東欧諸国に安心を供与するため必要であった。しかし、それが劇的に増えないのは、ロシアの軍事力の相対的、中長期的な低下という明示的には表現されていない認識が影響しているためだと思われる。
もっとも、今ロシア軍は出血し続けているが、それが消滅するまで出血することを期待するのは現実的ではなく、その底は見えていない。したがって、NATOが示した中間的な前方防衛強化策は、今後の短期的不確実性に備えるため徐々に実施に移され、当面継続する可能性が高い。
一方でその後は、低下したロシアの軍事力に対応するに当たり、独仏等へより大きな役割が求められるような見直しが行われる可能性がある。それまでの間は、当面アメリカ軍の増派が継続することになろう。
アメリカのインド太平洋シフトへの影響
これら欧州の戦力バランスの変化は、アメリカのインド太平洋シフトにどのような影響を及ぼすのか。アメリカ軍の増派は、艦艇や航空機もあるが、主要なものは、増派済み2万人に含まれる2個旅団戦闘団や、増派する1個旅団戦闘団等の地上部隊だろう。
この点、アメリカ軍においては、海兵隊で戦力の見直しが行われようとしており、中国のA2/AD脅威への対応として、ミサイルや無人機を擁する小型で分散した部隊への転換が提唱されている。
その一環として、戦車等の旧来型の装備品を廃止する方向性が打ち出され、退役する戦車は陸軍に移管する計画だ。一方、陸軍も、長射程の地上発射型ミサイルを装備したマルチドメイン任務部隊の編成に注力しており、欧州に増派された旅団戦闘団のような部隊は、控えめに言っても余力がある。
しかし、そうした旧来型部隊における余力が投げかけるのは、戦略レベルでは、新たな国家安全保障戦略で中国を「唯一の競争相手」と位置づけたにもかかわらず、その実施レベルでは、いまだアメリカ軍全体が対中シフトに最適化した戦力構成にはなっていないという現実である。
対中防衛シフトを加速させる契機に
現状、欧州に拠出しやすい旅団戦闘団等の部隊は、地続きのロシアと対峙する欧州とは戦略環境がまったく異なる西太平洋で、中国の海空ミサイル戦力に対処しうる戦力ではない。仮に、ロシア・ウクライナ戦争により弱体化し通常戦力では欧州のみで対処しうるかもしれないロシアへの対処を口実に、旧来型の部隊が広く温存され、アメリカ軍全体の戦力の優先順位付けが妨げられるとすれば、それがロシア・ウクライナ戦争がインド太平洋にもたらす最も大きな懸念となる。
そして、現在、アメリカすら地上発射型ミサイルや無人アセットを十分戦力化できているわけではないということは、日本が欧州のアメリカ同盟国より戦略的に死活的な立場に置かれうることを意味する。欧州と比べてインド太平洋でアメリカがいまだ十分な手段を提供する準備ができていないということは、反撃能力の保有を始めとする日本の自助努力やそれに基づく日米相互運用性のさらなる向上が、地域の安全保障にとってカギとなることを示しているからである。
これが、ロシア・ウクライナ戦争が日本に及ぼしうる最も大きな影響かもしれない。日米両国は、そのリスクを自覚したうえで、これをむしろ対中防衛シフトを加速させる契機とすることが求められる。
(Photo Credit: AP / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る